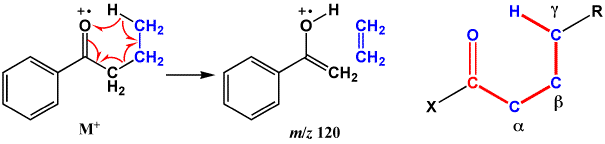質量スペクトル(MS)とは、有機分子を何らかの方法でイオン化して加速電極で加速したものを磁場の中に誘導し、イオンを質量電荷比(m/z)ごとに分離して記録したものである。有機分子のイオン化法にはいくつかあるが、低分子化合物を対象としてもっとも広く採用されているのは高真空下で気化した試料に電子ビームを衝突させてイオン化させる電子衝撃法(EI; Electron Impact)である。この方式では電子ビームの物理的衝撃により分子から電子がはじき出され正の電荷をもつイオンを生成する。通例、イオン化した分子(分子イオンという)は電子ビームから受けた衝撃エネルギーにより分子内の結合が開裂して小さなイオンに分解し、これをフラグメントイオンと称する。この過程(フラグメンテーションという)はかなり規則的に起きるので、構造解析上の有用な情報をスペクトルから得ることができる。電子衝撃法の特徴として、フラグメントイオンが出やすことがあげられ、電子衝撃質量スペクトル(EI-MS)は核磁気共鳴(NMR)スペクトルとともに構造解析上非常に有用である。実際の質量スペクトルの例として、1-phenyl-1-butanone (C10H120)のEI-MSを下に示す。

図1. 1-フェニル-1-ブタノンの質量スペクトル
質量スペクトルはNMRスペクトルと比べると上図のようにかなりシンプルである。横軸は質量電荷比(m/z)であり、mは質量数、zは電荷数を表わすが、通例、分子量が1,000以下の低分子化合物では分子から2つ以上電子がはじき出されることは稀であるので、質量電荷比(m/z)はz=1としてイオンの質量と考えてよい。したがって、分子イオンピークの質量電荷比が分子量を表わすことになる。高解像度の質量スペクトル(HR-MS)では正確な分子式を求めることも可能である。因みに図1のスペクトルではm/z 148が分子イオンピークである(→こちらをクリック;もとの図に戻す)。縦軸のrelative abundanceとは、 イオン量のもっとも多いピーク(基準ピークという)を100%として表わした各イオンの相対強度をいう。図1ではm/z 105が基準ピークである。もっとも生成しやすいフラグメントイオンが基準ピークを構成するのであるが、分子イオンが基準ピークとなることもある。
質量スペクトルでは分子イオン以外のピークをフラグメントイオンピークと称する。フラグメントイオンは親イオンの結合の切断で生成するが、どの結合が切れやすいか有機化学的見地から予測が可能である。したがって、質量スペクトルの解析から試料の構造を推定することが可能である。下図2に有機化合物の構造のうちで特にフラグメントイオンを生成しやすい部分を挙げるが、顕著なフラグメントイオンを生成するか否かは共鳴等によるイオンの安定化が起きるかどうかに関わっている。

図2. 主なフラグメントイオンの生成
一置換ベンゼン誘導体では置換基部分が切断されてC6H5+を生成するが、これは6員環の環状イオン(アリールカチオン)として安定化するので、強いイオン強度をもつフラグメントイオンとしてよく観測される。これとよく似たものにベンジル誘導体から生成するベンジルカチオン(m/z 91)があり、この場合は7員環イオンとして安定化し、アリールカチオンと同様強いイオンピークとして観測される。一般に、鎖状オレフィン誘導体ではアリル位で切断してアリルカチオンとして安定化するようフラグメンテーションが起きる。しかし、二重結合の転位を伴うことが多く、複雑なフラグメンテーションが起きて解析は容易ではない。一方、6員環状オレフィン(シクロヘキセン誘導体)ではレトロディールズアルダー反応による特徴的な環の開裂が起きる。カルボニル誘導体では、酸素原子の隣のC-C結合の開裂が起き、アシリウムイオンとして共鳴安定化するので、ケトン、カルボン酸エステル、アミド誘導体ではごく普通に出現するフラグメントイオンである。アルカンではアルキル基が多い炭素の隣の結合で切断しやすい。これはアルキル基に電子供与性があり、その結合の電子密度が高いからである。フラグメントイオンとして出現しやすいのはイオンとしてもっとも安定な3級イオンであり、以下2級、1級、メチル基の順に安定度、出現度が減少する。
1-phenyl-1-butanoneの質量スペクトルで観測されるフラグメントイオンm/z 77、m/z 105の生成は右図のように示す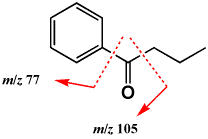 ことができるが、いずれも図2の開裂様式にしたがって起きている。一方、m/z 120はイオン強度はそれほど強くないが、この生成は上述の開裂様式のいずれにも該当しない。このイオンは質量スペクトルのフラグメンテーションに特有のMcLafferty転位(下図3の左側;一般の有機化学反応では知られていない)と称する結合の転位を伴ってエチレンが脱離して生成するものである。この転位反応は下図3の右側に示すような一定の構造を有するもの、すなわち「カルボニル化合物であってγ位炭素上に水素をもつ化合物」に特異的に起きるものであり、図3のように6員環の遷移状態を経て水素が転位し、中性のオレフィンが脱離する。カルボニルの代わりに二重結合であってもこの転位反応は起きうるが、カルボニル誘導体ほど鮮明ではない。McLafferty転位によるフラグメントイオンを用いる分析としてもっともよく知られているのは生体試料中の脂肪酸分析である。この場合、ガスクロマトグラフィーに質量分析計を直結したGC-MSというシステムが用いられるが、ガスクロマトグラフィー上の分離したピークが脂肪酸エステルであるか否かはMcLafferty転位によるフラグメントイオンピークの有無で確認することができる。
ことができるが、いずれも図2の開裂様式にしたがって起きている。一方、m/z 120はイオン強度はそれほど強くないが、この生成は上述の開裂様式のいずれにも該当しない。このイオンは質量スペクトルのフラグメンテーションに特有のMcLafferty転位(下図3の左側;一般の有機化学反応では知られていない)と称する結合の転位を伴ってエチレンが脱離して生成するものである。この転位反応は下図3の右側に示すような一定の構造を有するもの、すなわち「カルボニル化合物であってγ位炭素上に水素をもつ化合物」に特異的に起きるものであり、図3のように6員環の遷移状態を経て水素が転位し、中性のオレフィンが脱離する。カルボニルの代わりに二重結合であってもこの転位反応は起きうるが、カルボニル誘導体ほど鮮明ではない。McLafferty転位によるフラグメントイオンを用いる分析としてもっともよく知られているのは生体試料中の脂肪酸分析である。この場合、ガスクロマトグラフィーに質量分析計を直結したGC-MSというシステムが用いられるが、ガスクロマトグラフィー上の分離したピークが脂肪酸エステルであるか否かはMcLafferty転位によるフラグメントイオンピークの有無で確認することができる。