薬学部の六年制移行に伴い、大半の薬系大学において「漢方医学」を必修科目として履修するようになった。この傾向は医学部においても同様であり、漢方医学は医学生・薬学生にとってより身近な存在となった。いうまでもなく漢方医学は中国の古医方に源流があり、約二千年の歴史を経て今日に伝えられているのであるが、近代医学よりはるかに長い歴史をもつが故に、時代によって大きな変遷を余儀なくされてきた。したがって、日本の漢方医学は本家の中国のみならず朝鮮など周辺諸国の伝統医学とはかなり内容を異にするに至っている。これを理解するには中国を中心とした地域における伝統医学の歴史ならびにその薬物学たる本草学の歴史の把握なくしては成り立たない。薬系大学のカリキュラムにあっては、生薬学の分野において本草学・医学の歴史に触れることが多いのであるが、いずれの生薬学教科書においてもごく簡単に述べるにすぎない。一方で、平成21年度よりCBTが新たに学生の事実上の進級試験として課されるのであるが、これまでに行われたトライアルでは本草学・医学の歴史に関する出題があったといい、生薬学の教科書の範囲を越えるものであったという。おそらく薬系教員でも本草学・医学の歴史について精通するものはごく少ないと思われる。この背景には本草学・医学の歴史を概説する資料(出版年度が古く、ほとんどは絶版)の入手が困難であることがあげられるだろう。筆者は本草等の関連資料を十年以上の長きにわたって入手し、本草学・医学の歴史について概説するに十分な資料を蓄積するに至った。これを基に本ページにて日本および中国における本草学・医学の歴史について概説してみたいと思う。まだ不十分のところがあるかと思うが、諸兄のご感想を賜れば幸いである。
第一節 上代〜平安時代の本草書・医書
日本の歴史で初めて登場した薬物書は『藥經太素』二巻で和氣廣世(奈良時代から平安初期;生没年不詳)が著したといわれる。和氣廣世は和氣清麻呂(733年-799年)の子で典藥頭・大学頭を勤め、この書が成立した正確な年代は不明であるが、清麻呂の存命中であったから、799年より以前の奈良時代であることは間違いないといわれる。しかしながら、原本は伝わらず、写本が『群書類從』(塙保己一
編、1819年)の續編に収載されているが、原型をとどめないほど書き換えられたかあるいは加筆されたといわれ、当時の薬物書がいかなるものであったか判断するのは困難といわれる。実質的な意味では、平安時代中期の『本草和名』全二十巻が日本の歴史で最初の薬物書といえるだろう。 本書は深江輔仁(生没年不詳)撰と伝えられ、深江(深根ともいう)は延喜十八(918)年に勅命により『掌中要方』を撰進しているので(『日本紀略』延喜十八(918) 年9 月 17 日の条に「右衞門醫師深根輔仁撰掌中要方」とある)、同時期に『本草和名』も撰進したと考えられている。『類聚符宣抄』の延長 三 (925)年に深江が「權醫博士」であったことから、925年以降に「大醫博士」に任じられ、『本草和名』を撰進したと考えるのが自然だから、その成立は延喜年間末期と推定される(『和名抄』の序には「大醫博士深根輔仁奉敕撰集新鈔和名本草」、延喜年間の成立とある)。しかしながら、『本草和名』は平安時代に成立した百科事典である『和名抄』(『倭名類聚鈔』ともいう)の序および引用書の中に名を留めるのみで、久しく散佚したと思われていた。ところが、江戸時代の中期に、医学者の多紀元簡(1754年-1810年)が偶然幕府の書庫から古写本を発見し、内外の古書によって誤字を校訂し、頭注および序跋を加えて寛政八(1796)年に復刻したのが今日に伝わっている。本研究で用いたのは、幕末の考証家森立之(1807年-1885年)・約之(1837年-1871年)親子が書き込みをしたものの影印本(右上図)であり、原文の誤りを書き込みで訂正してあるので、事実上の注釈本の体裁をなす。立之本は1925年に日本古典全集刊行會により復刻出版されている。収載内容については、右上図にある記述でわかるように、本草内薬850種、諸家食經105種、本草外薬70種、併せて1025種の薬物(生薬)が収載されている。さらに細別すると、玉石類81種、草本257種、木本110種、禽獣類69種、虫魚類113種、果類45種、菜類62種、穀類35種、有名無用193種ほかとなっている。ここで本草内薬850種というのは唐の勅撰本草書である『新修本草』(659年成立、蘇敬撰)にある薬物をことごとく引用したことを表し、それ以外の中国の本草書等の収載品を併せると1025種になり、また生薬類の配列もそれに拠っている。引用する文献は三十以上あるが、全て唐代およびそれ以前のもので、『本草和名』が成立した時代すなわち五代・宋代の漢籍の引用は皆無である。引用する本草書のうち、陶景注とあるのは中国六朝梁の道家・本草家である陶弘景(456年―536年)の著になる『本草經集注』の引用である。『本草經集注』は中国最古の薬物学書・『神農本草經』をベースにして『名醫別錄』を合冊して注釈を加えたものであり、各生薬がどの部位を用い、その基原が何であるか、この書によって初めて明らかになった。そのほか、蘇敬注とあるのが『新修本草』であり、そのほか陳藏器(生没年不詳)撰の『本草拾遺』(739年)も引用され、『本草和名』では「拾遺」の名で出てくる。『本草拾遺』は「水類」約三十品目のほか、人血・人肉・人胆など、後世の医家などの非難を受けた品目も収載しているが、『本草和名』ではこれらは全く無視されている。また、薬物は各文献によって基原等の見解が異なることが多く、そのため多くの同物異名が発生するが、本書ではこれらをほとんど収録し、日本に基原植物(動物)が産する場合は、万葉仮名で和名が記され、またごく一部ではあるが、国内の産地も記載されている。単なる中国本草のコピーではなく、体裁からして漢籍本草書や医書を読むための手引きとしての性格を併せ持つといえる。
本書は深江輔仁(生没年不詳)撰と伝えられ、深江(深根ともいう)は延喜十八(918)年に勅命により『掌中要方』を撰進しているので(『日本紀略』延喜十八(918) 年9 月 17 日の条に「右衞門醫師深根輔仁撰掌中要方」とある)、同時期に『本草和名』も撰進したと考えられている。『類聚符宣抄』の延長 三 (925)年に深江が「權醫博士」であったことから、925年以降に「大醫博士」に任じられ、『本草和名』を撰進したと考えるのが自然だから、その成立は延喜年間末期と推定される(『和名抄』の序には「大醫博士深根輔仁奉敕撰集新鈔和名本草」、延喜年間の成立とある)。しかしながら、『本草和名』は平安時代に成立した百科事典である『和名抄』(『倭名類聚鈔』ともいう)の序および引用書の中に名を留めるのみで、久しく散佚したと思われていた。ところが、江戸時代の中期に、医学者の多紀元簡(1754年-1810年)が偶然幕府の書庫から古写本を発見し、内外の古書によって誤字を校訂し、頭注および序跋を加えて寛政八(1796)年に復刻したのが今日に伝わっている。本研究で用いたのは、幕末の考証家森立之(1807年-1885年)・約之(1837年-1871年)親子が書き込みをしたものの影印本(右上図)であり、原文の誤りを書き込みで訂正してあるので、事実上の注釈本の体裁をなす。立之本は1925年に日本古典全集刊行會により復刻出版されている。収載内容については、右上図にある記述でわかるように、本草内薬850種、諸家食經105種、本草外薬70種、併せて1025種の薬物(生薬)が収載されている。さらに細別すると、玉石類81種、草本257種、木本110種、禽獣類69種、虫魚類113種、果類45種、菜類62種、穀類35種、有名無用193種ほかとなっている。ここで本草内薬850種というのは唐の勅撰本草書である『新修本草』(659年成立、蘇敬撰)にある薬物をことごとく引用したことを表し、それ以外の中国の本草書等の収載品を併せると1025種になり、また生薬類の配列もそれに拠っている。引用する文献は三十以上あるが、全て唐代およびそれ以前のもので、『本草和名』が成立した時代すなわち五代・宋代の漢籍の引用は皆無である。引用する本草書のうち、陶景注とあるのは中国六朝梁の道家・本草家である陶弘景(456年―536年)の著になる『本草經集注』の引用である。『本草經集注』は中国最古の薬物学書・『神農本草經』をベースにして『名醫別錄』を合冊して注釈を加えたものであり、各生薬がどの部位を用い、その基原が何であるか、この書によって初めて明らかになった。そのほか、蘇敬注とあるのが『新修本草』であり、そのほか陳藏器(生没年不詳)撰の『本草拾遺』(739年)も引用され、『本草和名』では「拾遺」の名で出てくる。『本草拾遺』は「水類」約三十品目のほか、人血・人肉・人胆など、後世の医家などの非難を受けた品目も収載しているが、『本草和名』ではこれらは全く無視されている。また、薬物は各文献によって基原等の見解が異なることが多く、そのため多くの同物異名が発生するが、本書ではこれらをほとんど収録し、日本に基原植物(動物)が産する場合は、万葉仮名で和名が記され、またごく一部ではあるが、国内の産地も記載されている。単なる中国本草のコピーではなく、体裁からして漢籍本草書や医書を読むための手引きとしての性格を併せ持つといえる。
本草学は、中国ではあくまで医学書の手引きという位置づけであるから、その影響を色濃く受けた古代日本でも薬物書があれば必ず医書もあったはずである。伝存しなかったとはいえ、『藥經太素』という邦人の著になる薬物書があったわけだから、それに相応する何らかの医学書があってしかるべきである。しかしながら、古代日本の支配階級は外来医学を導入して病気の治療を行っていたのが実情であり、固有の医学はほとんど実態のないものだったと思われる。『日本書紀』には、允恭天皇三(413)年八月に新羅王の調貢大使であり医師であった金武が天皇の病を治し、雄略天皇三(459)年に天皇の徴に由って百済が高麗の良医・徳来を来朝させ、欽明天皇十四(553)年六月に勅使を百済に派遣して医博士、薬物を得たことなどが記述されているのはその証左であろう。このころの日本にはまだ中国医学の片鱗すら存在せず、飛鳥・奈良朝以前の日本は専ら朝鮮の韓医方(中国古医方のコピーに近いものであったと思われる)を積極的に導入していたといわれる。この状況に変化があったのは七世紀に入ってからであり、推古天皇十六(608)年九月に、惠日・福因が唐に在留すること十五年、唐医方を学んで帰朝してからは韓医方に変って唐医方が隆盛することになった。推古時代、四天王寺に療病院・施藥院が設けられたのはよく知られるが、これも本格的な唐医方を導入・実践したものである。大寶元(701)年に大寶律令が制定され、唐の律令制度を採用した国家統治が始まってから、いっそう唐医方の影響が強まり、中務省に内藥司、宮内省に典藥寮が設置された。内藥司では正一人、佑一人、令史一人、侍醫一人、藥生十人など、また典藥寮では頭一人、助一人、允一人、大属一人、少属一人、醫師十人、醫博士一人、醫生四十人、針師五人、針博士一人、針生廿人、按摩師二人、按摩博士人、按摩生十人、藥園師二人、藥園生六人などの人員が配置された。針師とは今日の鍼師であり、草根木皮の生薬の湯液を用いた内服療法のみならず針灸療法も含まれ、広く唐医方を導入したことを示している。永觀二(984)年に成立した日本初の医学書・『醫心方』を著した丹波康頼(912年-995年)が帰化漢人の子孫であったように、古代日本で医療に従事した人物の多くは帰化漢人であったと思われる。また、医薬の教育も整備され、典藥寮に属する大学で行われ、選抜は唐から導入した科挙の制に従って行われた。唐でもそうであったが、仏僧が医師を兼ねることが多く、唐から帰化した鑑眞(688年-763年)は後に鑑眞方といわれる薬方を日本にもたらした。平安時代になると陰陽 五行説を中国から導入し、陰陽寮 ・陰陽博士を設置し、病疫に対して陰陽学の占断が医の診断に先立つこともしばしばあったといわれる。嵯峨天皇時代は漢学を推進したこともあって、遣唐留学生によって唐医方の吸収もいっそう進んだといわれる。宇多天皇の時代には医方薬物書は百六十部以上、千三百九巻にのぼったが、その大半は随唐の書であったが、この蓄積が後に『本草和名』、『醫心方』の出版につながったのである。
古代日本の医学は唐医学の大きな影響下にあったのは紛れもない事実であったが、日本固有の薬方がなかったというのは早計であろう。承和七(840)年に成立した『日本後紀』の大同三(808)年五月三日の条に、平城天皇(大同元(806)年 - 大同四(809)年在位)あるいは桓武天皇(天応元(781)年-延暦二十五(806)年在位)の勅命により、安倍眞直と出雲廣貞(いずれも生没年不詳)に撰集させていた『大同類聚方
』百巻が完成し献上されたと記述されている。これは諸家に古くから伝わる医方を収集・編纂したものであり、平城天皇はみだりに異邦の薬種を使わないようこれまでの医学のあり方を根底から変えたといわれ、古くからの日本の古医方が散佚するのを憂えていた結果として『大同類聚方』も編纂されたともいう。しかしながら、平城天皇は即位からわずか四年で退位し、後継の嵯峨天皇(大同四(809)年 - 弘仁十四(823)年在位)は前述したように一転して唐医方を重視する政策に転じ、『大同類聚方』は利用されることがなくなり、まもなく散佚したとされている。現在に残るのは江戸後期の写本で、それも不完全なものしかないといわれる。ところが、国学者本居宣長(1730年-1801年)の弟子として知られる佐藤方定(生没年不詳)はそれを偽書と断じ、その理由として各写本の体裁が一定でないこと、文体が宣命書きの詔辞であること、一部の薬物の産出地に当時存在しない国名が出てくることなど、その具体的な論拠を挙げている。また、梅毒の症状とよく似た症例が記述されており、土肥慶三博士は、十五世紀のコロンブスの新大陸発見後に、梅毒が世界に広まったものであり、当時の日本になかったはずだとして、佐藤方定の偽書説を支持した。もっとも、梅毒は古代からあったという説もあって、現在では十五世紀説が有力という程度で完全な定説に至っていない。近年、奈良県大神神社に伝えられた写本を底本として『校注大同類聚方』(平凡社、1979年)が出版され、槇佐知子氏による『全訳精解大同類聚方』全五巻(新泉社、1992年)が出版された。用薬の部をみると、上代から古代の文献に見られない和名のものがある一方で、中国医方特有の薬味などが記載されていてその強い影響も随所に見られる。処方の部では、症例ごとに諸家(実名入り)伝来の処方が記されているが、典型的な民間療法の形態であって、後世の『醫心方』などに見られるような中核となる基礎理論は記述されていない。現在では後世の俗医の偽撰による偽書と断じられることが多いのであるが、多くは渡来の医方を実践したように思われるものの、日本古来の民間療法の痕跡が少なからず残されている可能性は否定できず、全く資料的価値はないとするのは早計と思われる。江戸時代の日本では、現在、漢方医学として知られる正当伝統医学に基づかない薬方が各地で用いられていたことは、『和方一萬方』などの各種民間療法書を見れば一目瞭然である。『懷中傭急諸國古傳秘法』という文化十四(1803)年に成立した民間療法書に出雲國古傳方・伯州米子田代氏一子相傳など各地域に秘伝された家伝方が多く収載されている。この療法書は衣關順庵(生没年不詳)が著したもので、「神國自然ノ毉道復古ニ珮志ヲ抱ク添多年大ニ憤悱兎諸國ヲ歷遊シ千辛万苦兎神國古傳ノ經驗数百万ヲ傳授セリ云々」とかなり国粋主義色の濃い後序から、順庵が古医方の収集に務めていたことが窺える。意外にも順庵は西洋流の解剖学を基盤とした眼科の蘭医であり、その名声を考えると決して民間の俗医ではない。また、古方派漢方の巨頭・吉益東洞(1702年-1773年)は伯州散という薬方を多用したことで知られるが、それは中国医学書のどこにも載っていないような出雲地方の民間薬方であった。大同類聚方にある薬方は、通説にいう俗医の撰ではなく、案外、順庵などのような名医が収集したものであって、中には類聚方残巻というべきものから拾い上げたものもあっても不思議ではない。確かに『大同類聚方』は古代からそのままの形で残っているものではないが、そもそも薬方は長い歴史的実践を通せばどんなものでも古態が失われるのが普通である。実際、中国でも多くの医書は後世に大幅に書き換えられているのである。また、たとえ偽撰書であってもその内容が無価値というわけではないことは、明末の『食物本草』を見れば明らかであろう。
実質的な意味で日本初の医書は、『本草和名』よりやや遅れて成立した『醫心方』全三十巻(丹波康頼著、左図)である。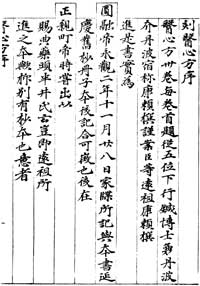 『醫心方』の写本は複数の系統があるが、いずれもその存在が世に知られるようになったのは、江戸時代後期に成ってからであり、それまでは秘蔵されてきた。室町時代に正親町天皇(弘治三(1557)年-天正十四(1586)年在位)から典藥頭半井光成(生没年不詳)に下賜され,以後半井家に伝来したのが半井家本である。今日、引用されるのはもっぱら半井家本であるが、ながらく世に知られることはなく、幕末になって徳川幕府は半井家から『醫心方』を借り出し、安政元(1854)年、考証学派医家・多紀元堅(1795年-1857年)に命じて書写させ、ようやく世に知れ渡ることとなった。この書写版は巻子本であり、現在宮内庁書陵部に所蔵され、宮内庁本といわれている。それを冊子体として安政六(1859)年に刊行したものが『安政版醫心方』であり、この時、元堅はこの世になく、子の多紀元琰(1824年-1876年)が校勘総理として出版にあたった。原本の半井家本は幕府に貸し出して以来、所在不明となり、幕末に書写されたものだけが今日に残る。醫心方・本文の両側にしばしば朱黒の附記・フリガナが付されているが、朱書は後世に付け加えられ、墨書はもともとあったものと考えられている。しかし、宮内庁本・安政版ともに墨だけで書写されたから、朱黒のいずれであったか区別できないという考証学上の難点がある。
『醫心方』の写本は複数の系統があるが、いずれもその存在が世に知られるようになったのは、江戸時代後期に成ってからであり、それまでは秘蔵されてきた。室町時代に正親町天皇(弘治三(1557)年-天正十四(1586)年在位)から典藥頭半井光成(生没年不詳)に下賜され,以後半井家に伝来したのが半井家本である。今日、引用されるのはもっぱら半井家本であるが、ながらく世に知られることはなく、幕末になって徳川幕府は半井家から『醫心方』を借り出し、安政元(1854)年、考証学派医家・多紀元堅(1795年-1857年)に命じて書写させ、ようやく世に知れ渡ることとなった。この書写版は巻子本であり、現在宮内庁書陵部に所蔵され、宮内庁本といわれている。それを冊子体として安政六(1859)年に刊行したものが『安政版醫心方』であり、この時、元堅はこの世になく、子の多紀元琰(1824年-1876年)が校勘総理として出版にあたった。原本の半井家本は幕府に貸し出して以来、所在不明となり、幕末に書写されたものだけが今日に残る。醫心方・本文の両側にしばしば朱黒の附記・フリガナが付されているが、朱書は後世に付け加えられ、墨書はもともとあったものと考えられている。しかし、宮内庁本・安政版ともに墨だけで書写されたから、朱黒のいずれであったか区別できないという考証学上の難点がある。
『醫心方』は本格的な医書であるが、『千金翼方』のように、一部の巻すなわち序説篇と食養篇に多くの薬物を列挙・概説している。ここでも邦産する薬物については和名が記されているが、『醫心方』の記述で多用される「本草云ふ」というのは『本草和名』ではなく『新修本草』からの引用であることに留意する必要がある。因みに、ほぼ同時代に成立した『和名抄』が引用する「本草云ふ」とは『本草和名』のことである。しかし、挙げられた和名のほとんどは『本草和名』と同じであるから、それを『本草和名』に拠っていることは間違いない。唐代の代表的な本草書である『新修本草』は今日に伝わっていないので、『醫心方』はその逸文のソースとして貴重な存在であり、尚志鈞輯校復原本『新修本草』(安徽科学技術出版社、2005年)には『醫心方』からの引用がとりわけ多い。『醫心方』は邦人の著した事実上初の医書といえるのであるが、決して頻繁に利用されたものではなかった。しかし、中国で散佚し今日に伝わらない文献の逸文が多く含まれている点で、その資料的価値は非常に高いものがある。また、記述の大半が平安時代院政期を書写したものであることもあって、内容がほとんど改変されておらず、今日に伝わる漢籍医書の多くが構成の大幅な改変を受けている中で、中国伝統医学の真の姿を探る上でも貴重な史料であり、このため半井家本は幕末の写本ながら国宝に指定されている。
『醫心方』は多くの唐医学書を引用かつその内容を咀嚼して記述したものであって、単なるコピーではないが、内容のほとんどは中国古医書を引用したもので、撰者独自の見解に基づく記載はほとんどないから、日本独自の医書というにはほど遠いものである。『本草和名』も同様であったが、わが国の本草・医学のいずれも長い歴史を通して中国の強い影響下にあり、新しい本草書や医書が漢土で刊行されればほどなくして日本に伝えられるという状況にあったことが、独自の医学や本草が育たなかった理由と思われる。しかしながら、『本草和名』・『醫心方』のいずれも中国文化の国風化の著しい時期に編纂されたのであり、日本の歴史に於いてその存在意義は決して小さくはない。因みに日本の風土に合わせて熟成した本草・医学の発生は江戸中期になってからである。
第二節 鎌倉・室町時代の本草書・医書
『本草和名』・『醫心方』はいずれも唐の典籍を引用しているのであるが、宋代以降の漢籍を引用した和籍本草書が刊行されたのは『本草和名』より三百年以上後の弘安七(1284)年、惟宗具俊(生没年不詳)が著した『本草色葉抄』(右図、『節用本草』ともいう)八巻であった。 本書は、『證類本草』を主として『本草衍義』(寇宗奭撰全二十巻、1119年成立)・『外臺祕要』・『范汪方』・『太平聖惠方』・『濟生方』・『千金要方』・『千金翼方』などを参考に編纂したもので、各品の漢名を伊呂波順に配列し、正名によってその異名を知り、異名により正名を考索するのに便利なように編纂され、いっそうわが国の実情に配慮したものとなった。特に、『證類本草』に収載されるものには全てその巻数を記したことで、索引の貧弱な證類本草の索引としても利用できるのが特徴である。しかし、当時の日本の医師たちは漢籍を直接参照することが多かったようであり、『本草色葉抄』はあまり利用されることはなかった。因みに、和本の本草書が本格的に刊行され、広く利用されるようになったのは江戸時代になってからである。
本書は、『證類本草』を主として『本草衍義』(寇宗奭撰全二十巻、1119年成立)・『外臺祕要』・『范汪方』・『太平聖惠方』・『濟生方』・『千金要方』・『千金翼方』などを参考に編纂したもので、各品の漢名を伊呂波順に配列し、正名によってその異名を知り、異名により正名を考索するのに便利なように編纂され、いっそうわが国の実情に配慮したものとなった。特に、『證類本草』に収載されるものには全てその巻数を記したことで、索引の貧弱な證類本草の索引としても利用できるのが特徴である。しかし、当時の日本の医師たちは漢籍を直接参照することが多かったようであり、『本草色葉抄』はあまり利用されることはなかった。因みに、和本の本草書が本格的に刊行され、広く利用されるようになったのは江戸時代になってからである。
鎌倉・室町期の医書として、梶原性全
(1266年-1337年)の『頓醫抄』をまず挙げねばならないだろう。嘉元二(1304)年あるいは正安四(1302)年に成立したといわれ、全五十巻からなる。主に北宋の『太平聖惠方』に依拠するが、唐代の『新修本草』・『千金要方』から宋代の『大平惠民和劑局方』・『三因方』など広く引用し、人体の解剖図(あまり写実的ではないが)も付している。『醫心方』と根本的に異なる点は、漢文ではなく「かな混じり文」で記述され、また一部に性全自身の意見も記されていることである。但し、巻四十八・四十九の二巻は、『醫心方』と同様、本草の解説に充てられているが、この部分は漢文に一部和文が混ざり内容的にも新鮮味に欠けるので、性全があまり本草に詳しくないことを物語っている。性全は漢文の医書『萬安方』五十巻(嘉暦二(1327)年成立)も著しているが、新たに『聖濟總錄』(全200巻、曾孝忠ほか撰;宋・政和年代に成立、1117年ころ)・『傷寒論』(林億による宋改本と思われる)・『紹興本草』(王継先撰、1159年成立)を引用している。このことから『頓醫抄』は中国医学を日本の風土に最適化し、普及を図ろうとする意図をもって編纂したと思われる。室町時代になると日明貿易が盛んにな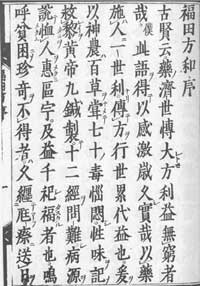 ったが、その余波は学術分野にも及び竹田昌慶(?年-1415?年)・田代三喜(1465年-1537年)などは明に留学して金元医学を学んだ。安土桃山時代から江戸初期かけて田代三喜の弟子である曲直瀬道三(1507年-1594年)が李東垣 (1180年-1251年)・朱丹溪(1281年-1358年)に代表される金元医学の日本化に務めた。道三の子である曲直瀬玄朔
(1549年-1631年)は『醫法明鑑』(寛永(1628)五年以前に成立)を著している。
ったが、その余波は学術分野にも及び竹田昌慶(?年-1415?年)・田代三喜(1465年-1537年)などは明に留学して金元医学を学んだ。安土桃山時代から江戸初期かけて田代三喜の弟子である曲直瀬道三(1507年-1594年)が李東垣 (1180年-1251年)・朱丹溪(1281年-1358年)に代表される金元医学の日本化に務めた。道三の子である曲直瀬玄朔
(1549年-1631年)は『醫法明鑑』(寛永(1628)五年以前に成立)を著している。
室町時代を代表する和籍の医書といえば、僧・有隣
(有林)(生没年不詳)の著した『有林福田方』(右図)がある。本書は貞治年間(1362年-1367年)の成立といわれるが、百余の漢籍を抄出し、自らの知見も加味して和文で著したものである。単なる中国医学の集録ではなく、頓醫抄に始まる医学の日本化を更に進めた書として注目に値するが、やはり中国医学の影響から脱することはなかった。