モルヒネ(Morphine)はわが国では麻薬ということで医師、患者の双方で使用をためらう傾向があるが、欧米ではモルヒネは十分にコントロールできるという意識が定着しており、麻薬(narcotic)というより鎮痛薬(analgesic)という意識の方が強い。欧州ではモルヒネの製造原料植物ケシの園芸用栽培も許可しているところがある。ケシはモルヒネというかけがえのない薬の恵みの植物という意識が定着しているのであろう。欧州にはCPS法(→麻薬アヘンの歴史と生産の現状を参照)による粗アルカロイド生産のため、かなりの規模でケシPapaber somniferumを栽培している国がかなりある(→アヘンの原料植物ケシについてを参照)が、これらの国でアヘンが蔓延して社会問題となっていることはあまり聞かない。日本人の多くがアヘンに対してあまりにセンセーショナルに反応するのは、一般に対してアヘン、モルヒネなどに対する正しい情報があまり伝わっていないためであろう。もっとも際立った例として癌患者に対するがん緩和ケア(疼痛治療)が挙げられよう。欧米では癌の除痛にモルヒネを用いるのはごく普通であり、世界保健機構(WHO)も推奨している標準治療法なのであるが、わが国ではようやくその端緒についたにすぎない。WHOはがん緩和ケアのガイドラインを定めており、第一段階はアスピリン(Aspirin)、アセトアミノフェン(Acetoaminophene)などの非オピオイド鎮痛剤、第二段階にコデイン(Codeine)等の弱オピオイド、第三段階にモルヒネなどの強オピオイドという風に段階を経て疼痛のコントロールを行うよう推奨している。欧米では疼痛が増大してからではなく、癌治療を開始した時点でがん緩和ケアを導入しているほどであり、「オピオイド鎮痛薬によるがん緩和ケアは患者の権利であり医師はそれに答える義務がある」という意識が社会的に浸透している。末期癌患者に対しては第三段階のモルヒネ投与で疼痛を制御するのであるが、経口投与であり、除痛に必要な用量は数百mg、時に数グラムに達することがある。これは薬物中毒患者の常用量を越えるレベルであるが、これでも欧米での例では麻薬中毒になる危険性は 非常に低いことが報告されている。また、最近の製剤技術の進歩により、たとえば硫酸モルヒネ徐放錠(MSコンチン錠;右写真)では持続時間は12時間であり、一日2回の投与で済むようになった。また、モルヒネを繰り返し投与すると鎮痛効果が減弱する”モルヒネ耐性”に遭遇することもあるが、最近では、モルヒネをシードとして創製された合成鎮痛薬フェンタニル(Fentanyl; 麻薬性)を補助剤として用いること(フェンタニル・パッチという塗布型の製剤で皮膚から吸収させ、効力は数日間持続する。わが国では平成14年から発売された)で対応できることが明らかとなった。また、フェンタニル・パッチは経口投与や座薬の使えない喉頭癌や直腸癌の患者には第一薬として使われている。欧米ではモルヒネと合成鎮痛薬の併用による疼痛コントロールは進んでおり、服薬ノウハウもわが国よりはるかに蓄積されている。前述したような多様な合成鎮痛薬も開発され、選択肢も格段に増えた現在、これらのオピオイド薬物の大半が麻薬指定であっても薬物依存の危険性はほとんどないといってよい。わが国では、硫酸モルヒネ徐放錠は1989年
非常に低いことが報告されている。また、最近の製剤技術の進歩により、たとえば硫酸モルヒネ徐放錠(MSコンチン錠;右写真)では持続時間は12時間であり、一日2回の投与で済むようになった。また、モルヒネを繰り返し投与すると鎮痛効果が減弱する”モルヒネ耐性”に遭遇することもあるが、最近では、モルヒネをシードとして創製された合成鎮痛薬フェンタニル(Fentanyl; 麻薬性)を補助剤として用いること(フェンタニル・パッチという塗布型の製剤で皮膚から吸収させ、効力は数日間持続する。わが国では平成14年から発売された)で対応できることが明らかとなった。また、フェンタニル・パッチは経口投与や座薬の使えない喉頭癌や直腸癌の患者には第一薬として使われている。欧米ではモルヒネと合成鎮痛薬の併用による疼痛コントロールは進んでおり、服薬ノウハウもわが国よりはるかに蓄積されている。前述したような多様な合成鎮痛薬も開発され、選択肢も格段に増えた現在、これらのオピオイド薬物の大半が麻薬指定であっても薬物依存の危険性はほとんどないといってよい。わが国では、硫酸モルヒネ徐放錠は1989年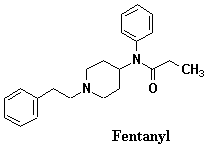 に発売されたが、同年のモルヒネ製剤消費量(塩酸モルヒネ、硫酸モルヒネの合計をモルヒネ換算したもの)は138Kgに達し、1979年の8Kgに比べて大幅に増加した。その後、1992年、289Kg、1995年、528Kg、1998年、719Kg、2001年は842Kgに達し順調に増加した(→厚生労働省統計による)。しかし、人口当たりの使用量に関しては、1996年のデータによれば11.0Kg/100万人であり、同年の先進諸国の消費量は、トップのオーストラリアが97.8Kg、以下カナダが84.8Kg、イギリス84.3Kg、アメリカ59.0Kg、フランス43.9Kg、ドイツ16.2Kgであり、これら諸国と比較して少ないのは歴然としている。モルヒネはがん緩和ケア以外に使うことはほとんどないので、これらのデータはがん緩和ケアの水準を表わしたものと考えてよいだろう。ドイツが意外と低いのはモルヒネの使用に対して事務的手続きが煩雑なので医師が躊躇しているからだという(ハイデルベルグ大学薬学部M. Wink教授の談、2005年7月20日、XVIIth International Botanical Congress、ウイーンにて)。同国では伝統療法の植物療法(phytotherapy)の割合が非常に高いのであるが、がん緩和ケアでアヘンチンキなど伝統的アヘン製剤を使うことはないようである。現在、モルヒネに関する啓蒙活動が活発に行われているので、いずれわが国におけるモルヒネ消費量も先進国の水準に近づくであろうが、末期癌患者の終末医療は在宅が主流になる思われるので、医薬分業が普及した現在、膨大な量の麻薬モルヒネの管理およびそれに伴う重い社会的責任が薬剤師に課されることも忘れてはならない。
に発売されたが、同年のモルヒネ製剤消費量(塩酸モルヒネ、硫酸モルヒネの合計をモルヒネ換算したもの)は138Kgに達し、1979年の8Kgに比べて大幅に増加した。その後、1992年、289Kg、1995年、528Kg、1998年、719Kg、2001年は842Kgに達し順調に増加した(→厚生労働省統計による)。しかし、人口当たりの使用量に関しては、1996年のデータによれば11.0Kg/100万人であり、同年の先進諸国の消費量は、トップのオーストラリアが97.8Kg、以下カナダが84.8Kg、イギリス84.3Kg、アメリカ59.0Kg、フランス43.9Kg、ドイツ16.2Kgであり、これら諸国と比較して少ないのは歴然としている。モルヒネはがん緩和ケア以外に使うことはほとんどないので、これらのデータはがん緩和ケアの水準を表わしたものと考えてよいだろう。ドイツが意外と低いのはモルヒネの使用に対して事務的手続きが煩雑なので医師が躊躇しているからだという(ハイデルベルグ大学薬学部M. Wink教授の談、2005年7月20日、XVIIth International Botanical Congress、ウイーンにて)。同国では伝統療法の植物療法(phytotherapy)の割合が非常に高いのであるが、がん緩和ケアでアヘンチンキなど伝統的アヘン製剤を使うことはないようである。現在、モルヒネに関する啓蒙活動が活発に行われているので、いずれわが国におけるモルヒネ消費量も先進国の水準に近づくであろうが、末期癌患者の終末医療は在宅が主流になる思われるので、医薬分業が普及した現在、膨大な量の麻薬モルヒネの管理およびそれに伴う重い社会的責任が薬剤師に課されることも忘れてはならない。
わが国でモルヒネや他の麻薬性オピオイド鎮痛薬に対する心理的抵抗が根強いのはやはり麻薬中毒患者の悲惨さからくるのであろう。わが国では「中毒患者は廃人」として社会復帰はできないと考えられているようであるが、治療技術も着実に進歩していることをわすれてはならない。わが国では中毒患者に対する一般認識という観点では、戦後直後から時計の針が止まったままといえよう。モルヒネは”経口投与である限り”そのような悲惨さとは無縁であり、また悲惨な結果をもたらすのは多くの場合モルヒネよりは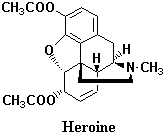 るかに多幸感をもたらし中毒性の強いヘロイン(Heroine; Diacetyl morphine)によるもので、それとて適切な治療をうければ社会復帰は可能である。アヘン禍が起きているところ、あるいは起きたところでは確かに中毒患者は廃人と化したが、東南アジアの例を見ればわかるように、喫煙あるいは注射による投与でもたらされたものである。欧州では歴史的にアヘンチンキ(Laudanum)が使われてきたが、薬物依存症になった例はあるが、廃人になった例はきわめて少なかった。英国ではトーマス・ド・クィンシー、エリザベス・B・ブラウニング、ジョン・キーツという著名な文人もアヘンの虜になったが、廃人というにはほど遠いレベルであった(→麻薬アヘンの光と陰を参照)。欧州ではアヘンの喫煙の習慣は定着せず、専ら経口投与であったので深刻なアヘン禍は起きなかったのである。中国はアヘン戦争の後遺症もあって国民の間にアヘンアレルギーが極めて強いのであるが、それでも1992年にモルヒネ徐放錠の発売を認可し癌疼痛の治療にモルヒネの使用を国を挙げて推進するようになった。前述したように、医師や薬剤師の観察下であればモルヒネは十分安全な薬であるというのが世界で共通した認識である。前述したように、現時点では、わが国のモルヒネの使用量は欧米先進国平均のの数分の一以下のレベルであるが、医療機関側の意識改革も進み、また患者およびその親族に対する活発なコミュニケーションによりモルヒネに対する理解も向上しつつあるので、欧米の水準に達するのもそう遠くないであろう。国立がんセンターホームページでは癌の緩和療法についてかなり詳しく紹介されており、俳人正岡子規が、晩年、脊椎カリエスによる激痛に悩まされ、晩年の1年半をモルヒネの投与で痛みを鎮めていたという逸話が紹介されている(現在はリンク切れ、この話はここを参照)。これによって正岡子規が麻薬中毒になったという話は全くなく、創作活動にも影響は与えなかった。戦前、わが国はかなりの規模でケシを栽培しており、モルヒネの使用には現在ほど抵抗はなかったのであろう。つまり、アヘン、モルヒネに過剰反応するようになったのは戦後であり、1946年にケシの国内栽培が全面禁止されてからと思われる。1955年に試験栽培のレベルで再会されるのであるが、戦前のレベルにはほど遠い水準であった。戦前の日本でアヘン禍が社会現象となったことはなかったにもかかわらずモルヒネに対する抵抗感があるのは、TV映像等による外国における麻薬禍のセンセーショナルな報道と、それによって増幅されたアヘンを絶対悪視する風潮に起因するしているようだ。わが国では薬物中毒では覚せい剤の方がはるかに深刻であり、アヘンはそれに比べればずっと危険は少ない。覚せい剤には薬としてのメリットは全くないが、アヘンには頑固な痛みをも和らげることでは唯一無比のモルヒネという自然の賜物が含まれる。癌患者は苦痛から逃れる権利があり、この世でそれに答えられるのはモルヒネとその類縁薬物しかないのである。
るかに多幸感をもたらし中毒性の強いヘロイン(Heroine; Diacetyl morphine)によるもので、それとて適切な治療をうければ社会復帰は可能である。アヘン禍が起きているところ、あるいは起きたところでは確かに中毒患者は廃人と化したが、東南アジアの例を見ればわかるように、喫煙あるいは注射による投与でもたらされたものである。欧州では歴史的にアヘンチンキ(Laudanum)が使われてきたが、薬物依存症になった例はあるが、廃人になった例はきわめて少なかった。英国ではトーマス・ド・クィンシー、エリザベス・B・ブラウニング、ジョン・キーツという著名な文人もアヘンの虜になったが、廃人というにはほど遠いレベルであった(→麻薬アヘンの光と陰を参照)。欧州ではアヘンの喫煙の習慣は定着せず、専ら経口投与であったので深刻なアヘン禍は起きなかったのである。中国はアヘン戦争の後遺症もあって国民の間にアヘンアレルギーが極めて強いのであるが、それでも1992年にモルヒネ徐放錠の発売を認可し癌疼痛の治療にモルヒネの使用を国を挙げて推進するようになった。前述したように、医師や薬剤師の観察下であればモルヒネは十分安全な薬であるというのが世界で共通した認識である。前述したように、現時点では、わが国のモルヒネの使用量は欧米先進国平均のの数分の一以下のレベルであるが、医療機関側の意識改革も進み、また患者およびその親族に対する活発なコミュニケーションによりモルヒネに対する理解も向上しつつあるので、欧米の水準に達するのもそう遠くないであろう。国立がんセンターホームページでは癌の緩和療法についてかなり詳しく紹介されており、俳人正岡子規が、晩年、脊椎カリエスによる激痛に悩まされ、晩年の1年半をモルヒネの投与で痛みを鎮めていたという逸話が紹介されている(現在はリンク切れ、この話はここを参照)。これによって正岡子規が麻薬中毒になったという話は全くなく、創作活動にも影響は与えなかった。戦前、わが国はかなりの規模でケシを栽培しており、モルヒネの使用には現在ほど抵抗はなかったのであろう。つまり、アヘン、モルヒネに過剰反応するようになったのは戦後であり、1946年にケシの国内栽培が全面禁止されてからと思われる。1955年に試験栽培のレベルで再会されるのであるが、戦前のレベルにはほど遠い水準であった。戦前の日本でアヘン禍が社会現象となったことはなかったにもかかわらずモルヒネに対する抵抗感があるのは、TV映像等による外国における麻薬禍のセンセーショナルな報道と、それによって増幅されたアヘンを絶対悪視する風潮に起因するしているようだ。わが国では薬物中毒では覚せい剤の方がはるかに深刻であり、アヘンはそれに比べればずっと危険は少ない。覚せい剤には薬としてのメリットは全くないが、アヘンには頑固な痛みをも和らげることでは唯一無比のモルヒネという自然の賜物が含まれる。癌患者は苦痛から逃れる権利があり、この世でそれに答えられるのはモルヒネとその類縁薬物しかないのである。