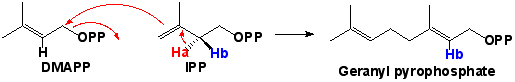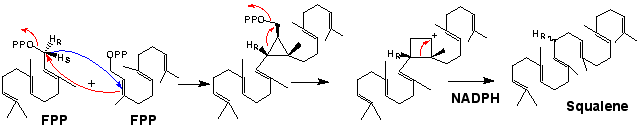1.イソプロテノイドの究極の前駆体DMAPPとIPP
テルペノイド(terpenoid)、ステロイド(steroid)、カロテノイド(carotenoid)などの化合物群は骨格がイソプレン(isoprene)に相当するC5単位で構成されており、天然物化学の黎明期において先駆的研究者により提唱されたイソプレン則はこのことを指摘したものである。今日でもイソプレン単位から構成される化合物群をイソプレノイド(isoprenoid)と総称することが多い。実際にイソプレン単位としてイソプレノイドを構築するのは、イソペンテニル二リン酸(Isopentenyl pyrophosphate; IPP)とそれがイソメラーゼの作用で異性化してつくられるジメチルアリル二リン酸(Dimethylallyl pyrophosphate; DMAPP)であるが、図1に示すようにアセチルCoAから生成するメバロン酸(Mevalonic acid)を経て生合成されるので、生合成経路の名称は”メバロン酸経路(Mevalonic acid pathway)”と称している。動物や酵母菌の産するテルペノイド、ステロイドは全てメバロン酸経路で生合成されると考えられている。コレステロールもこの経路で生合成されるので、メバロン酸生成の鍵酵素である3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoAリダクターゼ(HMG-CoA reductase)はコレステロール生合成を調節する薬物の標的分子として重要である。これについては次に述べる。
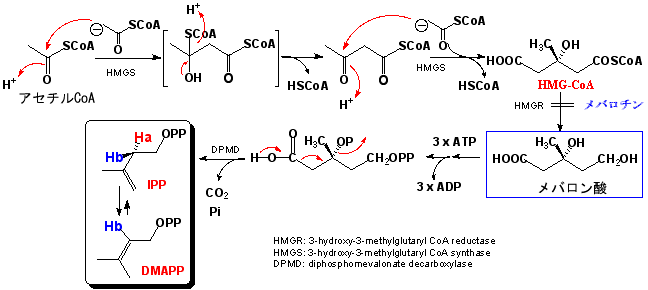
2.高脂血症治療薬はHMG-CoAリダクターゼの阻害剤である
動物の体内では3-ヒドロキシ-3-メチルグルタリルCoA(HMG-CoA)が還元されてメバロン酸を生成しコレステロール代謝の前駆体となるのであるが、高脂血症治療薬として広く用いられる薬物は本反応を触媒する酵素HMG-CoAリダクターゼの阻害剤である。1979年、邦人研究者によって紅麹菌Monascus ruberの代謝産物であるモナコリンK(Monacolin K)にHMG-CoAリダクターゼの阻害作用のあることが報告され、後に、そのナトリウム塩がメバロチン(Mevalotin)として市販された。モナコリンKは別名をロバスタチン(Lovastatin)とも称し、米国でもほぼ同時期に中国で古くから食品、薬用に用いられてきた紅麹から同じ成分がロバスタチンとして単離された。全く同じ構造を有する物質でありながら、異なる名前が付けられているのはその由来が異なるからである。モナコリンKは培養した紅麹菌Monascus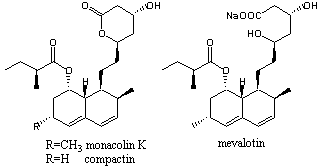 ruberから代謝産物として得られたものであり、一方、ロバスタチンは伝統的な食材、生薬である紅麹から得られたものである。紅麹とはM. purpureaなどMonasucus属に属する数種の菌類が粳米に寄生し発酵して生成したものである。因みに、天然由来のHMG-CoAリダクターゼ阻害物質として得られたのは紅麹菌代謝物が初めてではなく、1976年にPenicillium brevicompactumから得られた類縁物質コンパクチン(Compactin) の方が早く1978年にコレステロール生合成阻害作用を有することが報告されている。 モナコリンKとコンパクチンの構造の違いはごく軽微であるが、前者の方が広く医薬品として用いられているのは紅麹菌という食品の発酵に用いられているものから得られたことと無縁ではないだろう。因みに、わが国で味噌、醤油などの発酵食品に用いられる麹菌は「黄麹」と称されるAspergillus属糸状菌であり、繁殖力の弱いMonascus属糸状菌である紅麹菌は、紅麹カビの繁殖に有利な亜熱帯気候に属する沖縄県を除けば(豆腐に紅麹を発酵させてつくった沖縄の伝統食材「豆腐よう」はその一例である)、わが国における使用例はほとんどない。一方、中国では気温の高い華南で古くから紅酒、紅豆腐などをつくるのに広く用いられ、紅麹のように薬用に用いられているものもある。現在、米国で高脂血症予防のサプリメントとして販売され、Physician's Desk Reference (PDR)にも収載されているコレスチン(ファーマネクス社)は紅麹のエキスである。
ruberから代謝産物として得られたものであり、一方、ロバスタチンは伝統的な食材、生薬である紅麹から得られたものである。紅麹とはM. purpureaなどMonasucus属に属する数種の菌類が粳米に寄生し発酵して生成したものである。因みに、天然由来のHMG-CoAリダクターゼ阻害物質として得られたのは紅麹菌代謝物が初めてではなく、1976年にPenicillium brevicompactumから得られた類縁物質コンパクチン(Compactin) の方が早く1978年にコレステロール生合成阻害作用を有することが報告されている。 モナコリンKとコンパクチンの構造の違いはごく軽微であるが、前者の方が広く医薬品として用いられているのは紅麹菌という食品の発酵に用いられているものから得られたことと無縁ではないだろう。因みに、わが国で味噌、醤油などの発酵食品に用いられる麹菌は「黄麹」と称されるAspergillus属糸状菌であり、繁殖力の弱いMonascus属糸状菌である紅麹菌は、紅麹カビの繁殖に有利な亜熱帯気候に属する沖縄県を除けば(豆腐に紅麹を発酵させてつくった沖縄の伝統食材「豆腐よう」はその一例である)、わが国における使用例はほとんどない。一方、中国では気温の高い華南で古くから紅酒、紅豆腐などをつくるのに広く用いられ、紅麹のように薬用に用いられているものもある。現在、米国で高脂血症予防のサプリメントとして販売され、Physician's Desk Reference (PDR)にも収載されているコレスチン(ファーマネクス社)は紅麹のエキスである。
3.第2のイソプレノイド生合成経路ーデオキシキシルロース経路
近年、バクテリアや植物の産するテルペノイドはメバロン酸経路ではなく別の経路で生合成されることが明らかとなった。図2に示すようにグリセルアルデヒド-3-リン酸とピルビン酸から生成される1-デオキシ-D-キシルロース-5-リン酸(1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate)を経てIPPおよびDMAPPが生合成される。この経路では1-デオキシ-D-キシルロース-5-リン酸から2-Cメチル-D-エリスリトール-4-リン酸に至る反応経路では転位反応が起きているが、そのメカニズムはまだ明らかにされていないなどまだ未知の部分も残されている。カロテノイドは全てこの経路で生合成されることがわかっている。おそらくバクテリア、植物のテルペノイドもこの経路で生合成されるものが多いと思われ、この経路をデオキシキシルロース経路と称する。したがってイソプレノイドにはメバロン酸経路あるいはデオキシキシルロース経路から生合成される2つの系統があることになる。しかしいずれの経路でもIPPおよびDMAPPがイソプレノイドの直接の前駆体であることは確かなので、両経路を統合した代替名称としてイソプレノイド経路(isoprenoid pathway)が提唱されている。
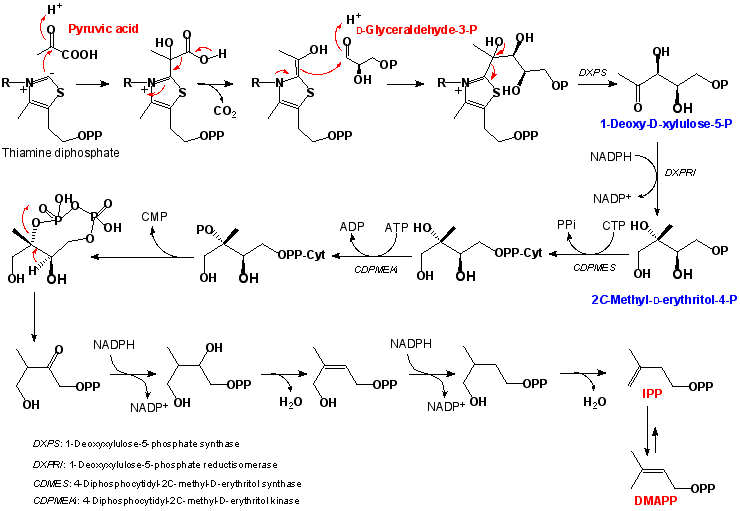
4.各種イソプレノイドの生合成の概要
イソプレノイドの生合成では、次式に示すようなメカニズムでDMAPPが頭となってIPPが縮合してC10単位のゲラニル二リン酸(Geranyl pyrophosphate; GPP)を生成し、これがモノテルペン(monoterpene)、イリドイド(iridoid)の前駆体となる。GPPを頭として1単位のIPPが縮合するとC15ファルネシル二リン酸(Farnesyl pyrophosphate; FPP)となり、同様にしてC20のゲラニルゲラニル二リン酸(Geranyl-geranyl pyrophosphate; GGPP)、C25のゲラニルファルネシル二リン酸(Geranyl-farnesyl pyrophosphate; GFPP)がつくられ、それぞれセスキテルペン(sesquiterpene)、ジテルペン(diterpene)、セスターテルペン(sesterterpene)の前駆体となる。トリテルペン(triterpene)、ステロイド(steroid)は2単位のFPPがtail-to-tailで縮合してできるスクワレン(Squalene)を経て生合成される、同様に、2単位のGGPPがtail-to-tailで縮合しC40のイソプレン鎖を生成し、カロテノイドの生合成前駆体となる。因みにモノ(mono)、セスキ(sesqui)、ジ(di)、セスター(sester)、トリ(tri)は1、1・1/2、2、2・1/2、3の意味であり、それぞれの骨格の炭素数を10で割った値に等しい。
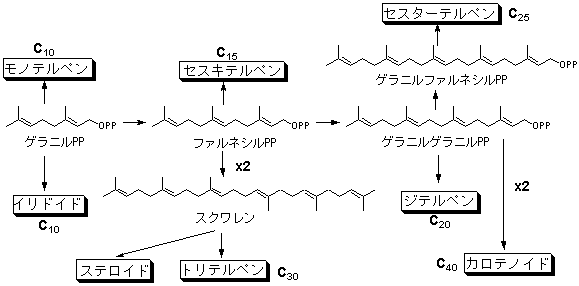
IPPのDMAPPへの異性化反応およびDMAPP、GPP等への縮合反応では、触媒酵素によりIPPのアリール位のプロキラリティが識別され、次の図に示すように、特定の配位の水素が脱離するなど詳細な反応メカニズムが明らかにされている。イソプレノイドに属する各化合物群については次のページに示す。