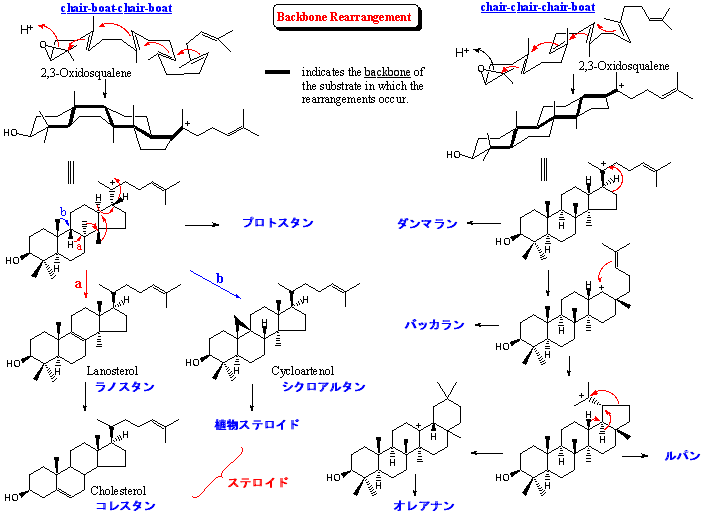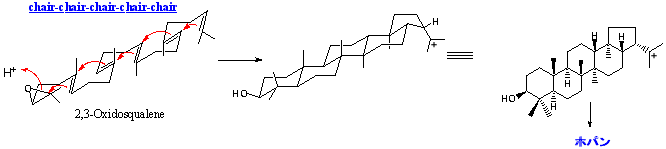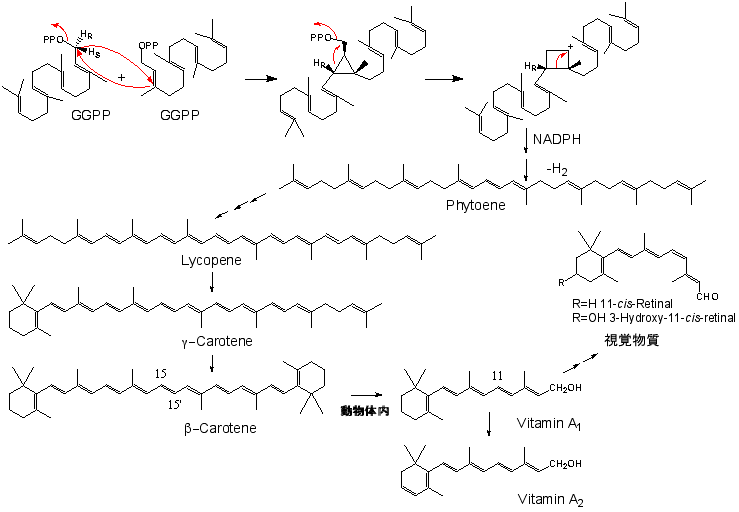1.ジテルペンの生合成
ジテルペンはC20のゲラニルゲラニル二リン酸(GGPP)を前駆体として生合成されるイソプレノイドである。ジテルペンは生合成のメカニズムが根本的に異なる2系列に大別される。一つは二リン酸残基の脱離により生成したカチオンに末端の二重結合が攻撃して生成する大環状カチオンに由来するセンブラン(cembrane)系と、もう一つは末端の二重結合にプロトンが攻撃することにより協奏的に順次6員環を形成して生成した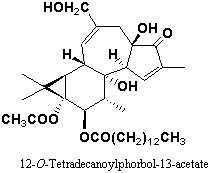 コパリル二リン酸(ラブダン(labdane)系)に由来するものである。センブラン系の植物界での分布は限られているが、生物活性の観点から注目すべきものが多い。トウダイグサ科ハズの種子(巴豆と称し、漢方では峻下剤・催吐剤として用いる)に含まれる強い皮膚刺激作用を有するティグリアン(tigliane)系ジテルペンの一つフォルボールエステル(TPA)は強い発癌プロモーター活性で知られ、実験動物に癌を発生させる試薬として用いられる。イチイ科イチイ属(Taxus
sp.)からはタキサン(taxane)骨格を有する一群のジテルペン誘導体が得られているが、そのうち北米西部山地に産するタイヘイヨウイチイ
コパリル二リン酸(ラブダン(labdane)系)に由来するものである。センブラン系の植物界での分布は限られているが、生物活性の観点から注目すべきものが多い。トウダイグサ科ハズの種子(巴豆と称し、漢方では峻下剤・催吐剤として用いる)に含まれる強い皮膚刺激作用を有するティグリアン(tigliane)系ジテルペンの一つフォルボールエステル(TPA)は強い発癌プロモーター活性で知られ、実験動物に癌を発生させる試薬として用いられる。イチイ科イチイ属(Taxus
sp.)からはタキサン(taxane)骨格を有する一群のジテルペン誘導体が得られているが、そのうち北米西部山地に産するタイヘイヨウイチイ
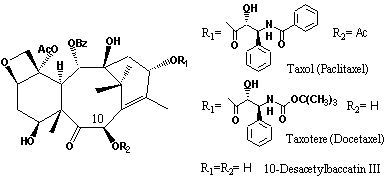
(Pacific yew; T. brevifolia)から初めて単離されたパクリタキセル(Paclitaxel)は現在抗癌剤として臨床で用いられている。パクリタキセル(商品名:Taxol)は極微量成分のため、ヨーロッパイチイ(Irish yew; Taxus baccata)の葉に多く含まれる10-Desacetylbaccatin III の10位水酸基に、別途合成した置換基部(R)をエステル結合させ、半合成で供給されている。現在、エステル部が非天然型のタキサン系抗癌剤の開発が進められ、ドセタキセル(Docetaxel)はその代表的なもので実際に臨床応用されている。ドセタキセル(商品名:タキソテール; Taxotere)はパクリタキセルより約3倍の抗癌活性があり、そのため投与量はパクリタキセルの3分の1ほどに押さえられている。しかし、両者は名前が紛らわしく、臨床の現場では用量を間違って投与した医療事故も発生している。
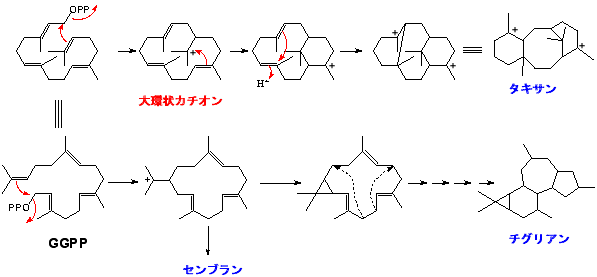
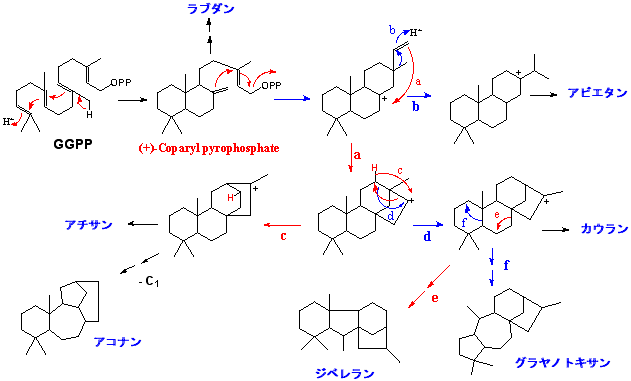
ラブダン系列に関しては、図1の下段に示すように、まずGGPPの末端二重結合が水素イオンの攻撃を受け、協奏的に環化してコパリル二リン酸を生成する。この二リン酸の加水分解で生成するのがラブダン(Labudane)である。インド原産でアユルベーダ医学で用いられたシソ科コレウスColeus forskoliiの根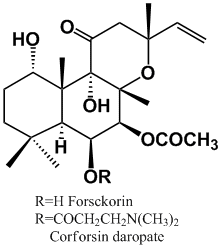 に含まれるフォルスコリンは代表的なラブダンジテルペンの一つである。血圧降下・強心作用があり、これをシードとして心不全治療薬コルホルシン・ダロパート(Corforsin daropate)が創製された。イチョウ科イチョウの葉などに含まれるギンコライドは血小板活性化因子(PAF)アンタゴニスト作用があり、脳血流循環障害に対して効果が期待されることをもって、欧米では医薬品あるいはサプリメント(イチョウ葉エキスEGb761ほか)として広く利用されている(詳細はこちらを参照)。ギンコライドは高度に酸化され、骨格的にきわめて複雑な構造を呈するが、ラブダン骨格から派生する変形ラブダンの一種と考えられている。その生合成経路はまだ解明されていないが、その複雑な骨格は図2の経路で構築されると推定されている。
に含まれるフォルスコリンは代表的なラブダンジテルペンの一つである。血圧降下・強心作用があり、これをシードとして心不全治療薬コルホルシン・ダロパート(Corforsin daropate)が創製された。イチョウ科イチョウの葉などに含まれるギンコライドは血小板活性化因子(PAF)アンタゴニスト作用があり、脳血流循環障害に対して効果が期待されることをもって、欧米では医薬品あるいはサプリメント(イチョウ葉エキスEGb761ほか)として広く利用されている(詳細はこちらを参照)。ギンコライドは高度に酸化され、骨格的にきわめて複雑な構造を呈するが、ラブダン骨格から派生する変形ラブダンの一種と考えられている。その生合成経路はまだ解明されていないが、その複雑な骨格は図2の経路で構築されると推定されている。
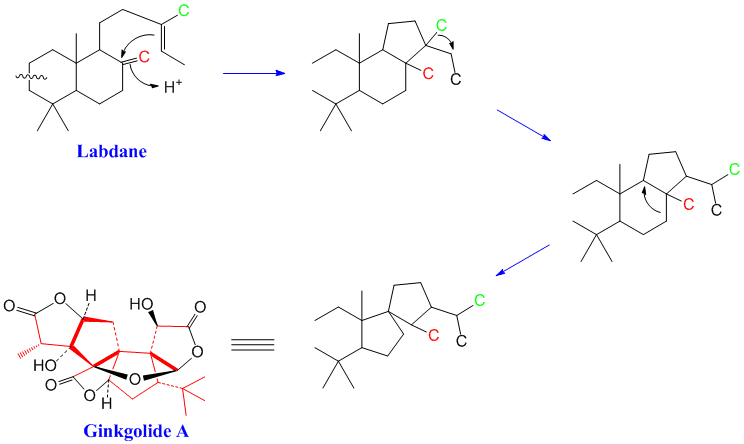
コパリル二リン酸の二リン酸残基の脱離で生成するカチオ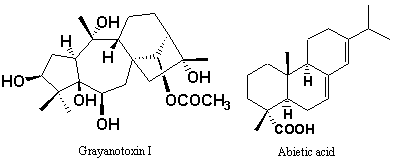 ンからexo-二重結合が攻撃し、さらに水素や炭素-炭素結合の転移により、様々な骨格が形成される。キク科ステビアの甘味成分ステビオシド(Stevioside)はカウラン(kaurane)系ジテルペン配糖体であり、良質な味から天然甘味料として広く利用される。アカマツなどマツ類の樹脂を水蒸気蒸留した残留物をロジンと称するが、主成分はアビエタン(abietane)系ジテルペンアビエチン酸(右構造式;Abietic
acid)である。アビエチン酸は印刷用インク原料、接着剤など工業原料として有用で
ンからexo-二重結合が攻撃し、さらに水素や炭素-炭素結合の転移により、様々な骨格が形成される。キク科ステビアの甘味成分ステビオシド(Stevioside)はカウラン(kaurane)系ジテルペン配糖体であり、良質な味から天然甘味料として広く利用される。アカマツなどマツ類の樹脂を水蒸気蒸留した残留物をロジンと称するが、主成分はアビエタン(abietane)系ジテルペンアビエチン酸(右構造式;Abietic
acid)である。アビエチン酸は印刷用インク原料、接着剤など工業原料として有用で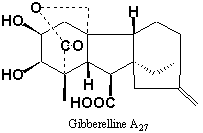 あり、また天然資源的にも豊富であるので、更なる有効利用ができるとして期待されている。グラヤノトキサン(grayanotoxane)系ジテルペンはツツジ科の有毒成分として広く分布するもので、その一つとしてグラヤノトキシン(右上構造式;Grayanotoxin
I)がある。イネにGibberella fujikuroiという病原菌が寄生して起きる病気を馬鹿苗病というが、これは病原菌が産生する代謝性産物ジベレリン(左構造式;Gibberellin)がイネの異常生育をもたらすために起きる。ジベレリンは一種の天然植物ホルモンであり、様々な植物に対して発育促進をはじめ開花、発芽、肥大、着花、着果などの促進作用があり、また果樹に対しては落果防止効果があるので、農業分野で広く用いられている。ジベレリンの基本骨格をジベレラン(gibberellane)と称する。
あり、また天然資源的にも豊富であるので、更なる有効利用ができるとして期待されている。グラヤノトキサン(grayanotoxane)系ジテルペンはツツジ科の有毒成分として広く分布するもので、その一つとしてグラヤノトキシン(右上構造式;Grayanotoxin
I)がある。イネにGibberella fujikuroiという病原菌が寄生して起きる病気を馬鹿苗病というが、これは病原菌が産生する代謝性産物ジベレリン(左構造式;Gibberellin)がイネの異常生育をもたらすために起きる。ジベレリンは一種の天然植物ホルモンであり、様々な植物に対して発育促進をはじめ開花、発芽、肥大、着花、着果などの促進作用があり、また果樹に対しては落果防止効果があるので、農業分野で広く用いられている。ジベレリンの基本骨格をジベレラン(gibberellane)と称する。
プソイドアルカロイドの中にはジテルペン由来のものがある。キンポウゲ科トリカブト属(トリカブト、ツクバトリカブトなど)には猛毒成分アコニチン(Aconitine)が含まれるが、C19のアコナン(aconane)骨格にアンモニア性窒素あるいはアルキルアミンが導入されて生成したプソイドアルカロイドと推察される。オクトリカブト、ハナトリカブトなどの根は生薬ブシ(附子)として漢方処方に配合されるが、これらも数ミリグラムで成人を死に至らしめるといわれる猛毒性分アコニチンをを含む。実際、漢方処方に配合されるのはトリカブトの根を火で焙ったり蒸したりして減毒した加工附子といわれるものである。生薬に減毒、あるいは薬効を高めるために行う操作を修治(しゅうち)と称する。ブシの場合、加熱処理という修治によって有毒成分であるアコニチンのエステル基が加水分解されて脱離し、それによって毒性が著しく低下することが知られている。ブシの修治は不完全であればアコニチンが残存するので危険を伴う操作であるが、現在では一定時間オートクレーブ処理で生薬ブシを供給しているので安全性は確保されている。トリカブト属には他にC20のアチサン(atisane)系ジテルペンアミンである毒性の低いアチシン(atisine)系化合物も共存する。トリカブト類の中にはアコニチンをほとんど含まない系統もあり、化学的、形態的多様性の著しい植物群である。
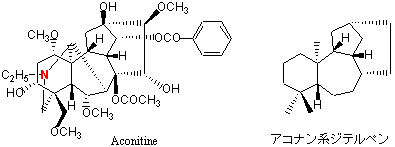
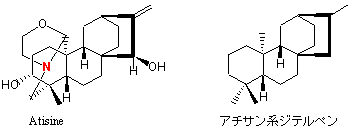
2.トリテルペン、ステロイドの生合成
イソプレノイドの中でトリテルペン・ステロイドは、モノテルペンなど他のイソプレノイドと異なり、ファルネシル二リン酸(FPP)がtail-to-tailで縮合して生成するC30のスクワレンを前駆体として生合成されるので、基本骨格の生成に二リン酸残基の関与はない。通常、スクワレンは末端二重結合が酸化を受けて2,3-オキシドスクワレン(2,3-Oxidosqualene)となり、プロトンによるエポキシ環の開裂により協奏的な環化反応が起きる。生成する基本骨格の様式は2,3-オキシドスクワレンの幾何学的配列に依存するが、その配列は関与する酵素により異なる。chair-boat-chair-boatの配列から閉環して生成するのがプロトスタン(protostane)であり、さらに脊梁転移(backbone rearrangement)によりラノスタン(Lanostane)とシクロアルタン(Cycloartane)を生成する。前者は動物や菌類、後者は植物に見られる。それぞれからメチル基の脱離や側鎖の切断などを経て生成するものがステロイドであり、炭素数はトリテルペンがC30であるのに対し、ステロイドはC21~C27、C28と様々である。植物の産するステロイド類を特にファイトステロール(phytosterols)と称する。オキシドスクワレンがchair-chair-chair-boatの配列から閉環して生成するのがダンマラン(dammarane)であり、さらに末端シクロペンタンから側鎖への脊梁転移によりバッカラン(baccharane)、ルパン(lupane)、オレアナン(oleanane)など多様な骨格群を生成する。chair-chair-chair-chair-chairの配列から生成するものをホパン(hopane)と称する(→こちらへ)。
天然界には少数例ながらトリテルペンが酸化を受けて生成したと思われる変形トリテルペンと称する成分群があり、ごく限られた分類群の植物に分布する。ナツミカンやダイダイなどミカン科カンキツ(Citrus)属の果皮に含まれる炭素数26個のリモニン(Limonine)およびそのグルコース配糖体は代表的なものである。柑橘類の中には苦味がほとんどないものがあり食用とされるが、リモニンが少ないのではなく、リモニンのほとんどが苦味のない配糖体として含まれているからである。生薬オウバク(キハダの樹皮)にも類似の苦味成分オウバクノン(Obakunone)が含まれているが、基本骨格はリモニンと同じであり、これらを総称してリモノイド(limonoid)と称される。リモノイドはミカン科に近縁なセンダン科にも含まれる。センダンの苦味成分はトウセンダニンを始めとするリモノイドである。柑橘類においては苦味が強リモニンの存在は果実の商業的価値を下げるものとして好ましくないものと考えられてきた。ところが、最近、癌を抑制しコレステロール値を下げる効果があると報告され、健康食品あるいはサプリメントとしての応用の観点からは有用成分として注目を集めつつある。リモノイドの生合成的起源としては、その構造から類推して図4に示すようにダンマラン系トリテルペンから派生したと考えるのが妥当である。分類学的にミカン科に近いニガキ科植物も変形トリテルペンのソースとして知られている。ニガキ(樹皮を生薬ニガキとする)に含まれるクァシン(Quassin)はその代表的なものであり、ニガキの苦味成分でもある。クァシンおよびニガキ科植物に含まれる類縁物質をクァシノイド(quassinoid)と総称するが、リモノイドよりさらに酸化が進んだものであり、炭素数は20しかない。ニガキ科とミカン科の類縁性およびリモノイド、クァシノイドの構造的類縁性を考慮すれば、リモノイドと同じくダンマラン系トリテルペンから派生したものと思われる。一部のクァシノイドに抗腫瘍活性が報告されており、抗癌薬として開発が試みられたこともある。
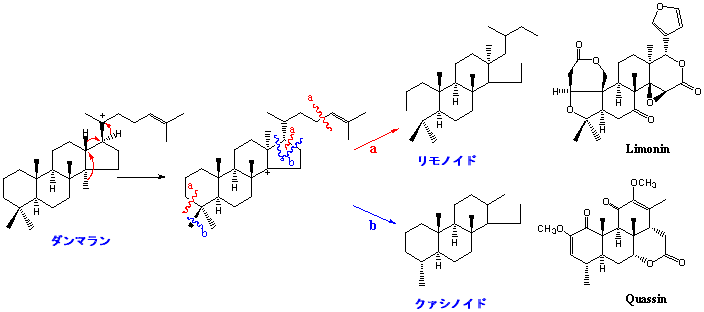
天然界にはトリテルペンやステロイドの多くは配糖体、すなわちサポニン(saponin)(→構造式一覧リンク)として存在する。オタネニンジンの根、すなわち生薬ニンジンの主サポニンはジンセノシドRg1を始めとするダンマラン系であり、他にオレアナン系を少量含む。一方、トチバニンジンの根茎(生薬チクセツニンジン)に含まれるサポニンは主にオレアナン系でダンマラン系は少ない。他にダンマラン系サポニンを含むものに生薬タイソウ(基原:クロウメモドキ科ナツメの果実)がある。一方、オレアナン系サポニンは天然界に広く分布し、含量の高いものは生薬として有用なものが多く、例えば、オンジ(イトヒメハギなどの根)、カンゾウ(ヨーロッパカンゾウの根)、キキョウ(キキョウの根)、ゴシツ(ヒナタイノコズチ、トウイノコズチなどの根)、サイコ(ミシマサイコの根)、セネガ(ヒロハセネガなどの根)、モクツウ(アケビ、ミツバアケビの茎)があげられる。ステロイドサポニンと称するものの大半スピロスタン(spirostane)またはフロスタン(furostane)をアグリコンとするものである(図5)。ステロイドサポニンを含む生薬にはジギタリス、チモ(ハナスゲの根茎)、バクモンドウ(ジャノヒゲの根の膨大部)、テンモンドウ(クサスギカズラの根)、サンヤク(ヤマノイモの根茎)、ビャクゴウ(オニユリなどの根)などあるが、天然界には比較的広く分布する。
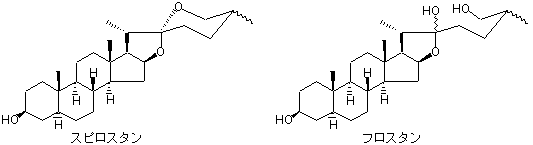
芽が出たジャガイモを食すると中毒を起こすが、その原因物質はソラニン(Solanine)という、ステロイドに窒素原子が挿.gif) 入され、更に配糖体となったものである。すなわち、サポニンアルカロイドともいうべきプソイドアルカロイドで、ソラニンにはサポニンに特有の溶血作用もある。ソラニンのアグリコンをソラニジン(Solanidine;右図)と称するが、C27-ステロイドアルカロイドであり、フロスタンにアンモニアが導入され環化したものと推定される。ジャガイモの属するナス科ナス属(Solanum
sp.)には類似のサポニンアルカロイドが多く存在する。その他、C27-ステロイドアルカロイドはユリ科バイケイソウ(Veratrum)属(ミカワバイケイソウなど)、リシリソウ(Anticlea)属、バイモ(Fritillaria)属(アミガサユリなど)などから見いだされているが、天然界での分布はかなり限られている。これらはいずれも有毒植物として知られるものであり、特にバイケイソウの仲間は芽生えが山菜として利用されるオオバギボウシと類似するので誤って採取、摂取による中毒事故が多く発生し、時に死に至る例もある。
入され、更に配糖体となったものである。すなわち、サポニンアルカロイドともいうべきプソイドアルカロイドで、ソラニンにはサポニンに特有の溶血作用もある。ソラニンのアグリコンをソラニジン(Solanidine;右図)と称するが、C27-ステロイドアルカロイドであり、フロスタンにアンモニアが導入され環化したものと推定される。ジャガイモの属するナス科ナス属(Solanum
sp.)には類似のサポニンアルカロイドが多く存在する。その他、C27-ステロイドアルカロイドはユリ科バイケイソウ(Veratrum)属(ミカワバイケイソウなど)、リシリソウ(Anticlea)属、バイモ(Fritillaria)属(アミガサユリなど)などから見いだされているが、天然界での分布はかなり限られている。これらはいずれも有毒植物として知られるものであり、特にバイケイソウの仲間は芽生えが山菜として利用されるオオバギボウシと類似するので誤って採取、摂取による中毒事故が多く発生し、時に死に至る例もある。
3.カロテノイドの生合成
カロテノイドは植物によって産生される黄色~赤色色素で、通例、クロロプラスト中のクロロフィルと会合する。高等植物のみならず藻類、菌類、地衣類も産生されるが、動物は産生しない。カロテノイドの名は、1831年、Wackenroderが野菜のニンジン(carrot)からその色素(実際には混合物であったが)を単離したことに由来する。生合成的には2単位のゲラニルゲラニル二リン酸(GGPP)がtail
to tailで結合(メカニズムはスクワレンの場合と同様で図6とともにこちらも参照)して生成したフィトエン(Phytoene)を前駆体とするイソプレノイドである。フィトエンは更に段階的に脱水素を受けてリコペン(Lycopene)に変換される。緑黄色野菜に多く含まれ、栄養学的に重要とされるカロテノイドは全てリコペンを前駆体とする。リコペンの末端の一方が環化したものがγ-カロテン(Carotene)、両末端が環化したものがβ-カロテンである。リコペンはトマトLycopersicon
esculentumの果実に多く含まれる鎖状炭化水素系カロテンの代表的なものである。β-カロテンはいわゆる緑黄色野菜に多く含まれるもっとも代表的なカロテノイドであり、食品着色料としても利用される。一時、発癌予防効果があるとされ注目されたが、その後、多量摂取すると癌のリスクをたかめるという全く逆の見解が出され、混沌として現在に至っている。しかし、動物の体内ではβ-カロテンは中央部(C15-C15')が切断されてビタミンA1のレチノール(Retinol)を生成し、更にレチナール(Retinal)に変換され視覚作用物質として生理的に重要な働きをするので、プロビタミンAとして重要な生理作用物質であ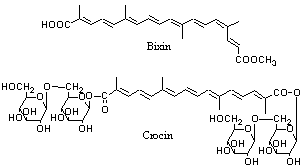 ることには変わりがない。そのほか、ビタミンAは皮膚粘膜や表皮組織の形成、成長促進などの生理作用があり、最近では制癌作用について広く検討されている。カロテノイドは前述の炭化水素系のほか、アルコール、カルボン酸、アルデヒドなどの官能基が挿入されたものもある。また、一端または両端から炭素鎖の一部が失われて短くなったものがあり、これらをアポカロテノイドとして区別し、ベニノキ科ベニノキの種子に含まれるビキシン(Bixin)やアカネ科クチナシの果実(生薬サンシシ)、アヤメ科サフランのめしべの柱頭に含まれるクロシン(Crocin)はその代表例である。ビキシンは脂溶性、クロシンは水溶性の色素であり、いずれも食用色素として用いられる。サフランの柱頭はフランス料理の高級食材であり高価なので、最近では同じ色素クロシンを含むクチナシの果実を代用に用いることが多い。
ることには変わりがない。そのほか、ビタミンAは皮膚粘膜や表皮組織の形成、成長促進などの生理作用があり、最近では制癌作用について広く検討されている。カロテノイドは前述の炭化水素系のほか、アルコール、カルボン酸、アルデヒドなどの官能基が挿入されたものもある。また、一端または両端から炭素鎖の一部が失われて短くなったものがあり、これらをアポカロテノイドとして区別し、ベニノキ科ベニノキの種子に含まれるビキシン(Bixin)やアカネ科クチナシの果実(生薬サンシシ)、アヤメ科サフランのめしべの柱頭に含まれるクロシン(Crocin)はその代表例である。ビキシンは脂溶性、クロシンは水溶性の色素であり、いずれも食用色素として用いられる。サフランの柱頭はフランス料理の高級食材であり高価なので、最近では同じ色素クロシンを含むクチナシの果実を代用に用いることが多い。
カロテノイドはイソプレノイドの一種であるが、その生合成前駆体であるGGPPはメバロン酸ではなく、グリセルアルデヒド-3-リン酸とピルビン酸から生成したイソペンテニルピロリン酸(IPP)から生成することが確認されているので、非メバロン酸イソプレノイドということになる。無論、メバロン酸由来のイソプレノイドもあるが、生合成経路としてのメバロン酸はすでに一般性を失ったと見てよいだろう。前述したように「イソプレノイド経路」と呼ぶ方が適当である(→イソプレノイド酸経路参照)。