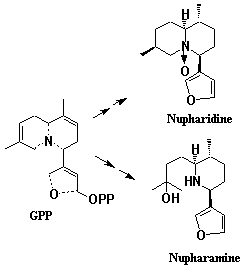1.モノテルペンの生合成
イソプレノイドの中でもっとも分子量の小さいのがモノテルペンであるが、ゲラニル二リン酸(GPP)を前駆体として生合成される。まず、GPPから二重結合がシス体に異性化してネリル二リン酸(Neryl pyrophosphate)となり、二リン酸残基の脱離で生成したカチオンが環化し、図1に示すような各種のモノテルペンが生合成される。これらのカチオンは多くの場合非古典的カチオン(nonclassical cation)として挙動し、複雑な骨格を生成する。
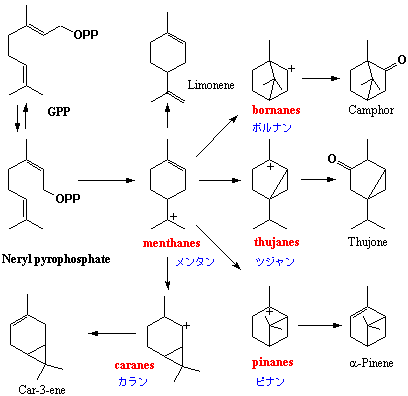
モノテルペンの多くは植物の精油(essential oil)成分として存在し、医薬品、香粧品として重要なものも多い。例えばクスノキから得られる(+)-カンフル(Camphor)は局所刺激作用があるため神経痛、炎症、打撲などの擦剤として重要である。その他、ハッカ、セイヨウハッカに含まれる(-)-メントール(Menthol)は鎮痛、制痔剤とするほか、歯磨剤、清涼剤として大きな用途がある。メントールは分子内に3個の不斉炭素が存在するので、23すなわち8種類の立体異性が存在し得る。体精油成分は一般に芳香があるが、柑橘類(ウンシュウミカン、ナツミカン、ダイダイなど)の芳香成分は(-)-リモネン(limonene)であり、香料として広く利用するほか、炭化水素系油成分なので溶剤として発泡スチロールを溶かすのに用いられている。モノテルペンの多くは分子内に不斉炭素(キラル炭素)を有し光学活性物質であるが、タチジャコウソウなどに含まれ消毒薬などに用いられるチモール(Thymol)は環が芳香化して不斉炭素を消失したフェノール成分である。アカマツなどマツ科Pinus属各種が分泌する松脂からはテレビン油と称する精油が得られるが、α-ピネン(Pinene)などピナン系モノテルペンを主成分とする。
モノテルペンに糖が結合した配糖体も少数ながら天然に存在する。生薬シャクヤク(シャクヤクの根)にはピナン系モノテルペン配糖体ペオニフロリン(Paeoniflorin)なる複雑な構造をした成分が含まれ、動物実験で鎮痙、抗炎症作用などが報告され、シャクヤクを配合する数多くの漢方処方の薬効を考える上でも重要な成分である。
2.イリドイドの生合成
GPPを前駆体とする二次代謝物の中で二リン酸残基の脱離で生成するカチオンを経ずに生合成される変形モノテルペンの一種である。中間体は10-ヒドロキシゲラニオールより生成するイリドトリアール(Iridotrial)であり、これが閉環してエノール-ヘミアセタールとなったものがイリドイドであり、通例、ヘミアセタールにはオリゴ糖鎖が結合する。ミズキ科サンシュユの果実(生薬サンシュユ)に含まれるロガニン(Loganin)はもっとも広く分布するイリドイドの一つであり、またこれを前駆体として様々なイリドイドが生合成される。生薬成分として重要なものも多く、クチナシの果実を基原とするサンシシの主成分はゲニポシド(Geniposide)などのイリドイドであり、胆汁分泌促進作用成分(実際に活性成分として作用するのは加水分解して生成するアグリコンのゲニピン(Genipin)である)として重要である。そのほか、キササゲの果実、アカヤジオウの根(生薬ジオウ)も多量のイリドイドが含まれ、その共通成分であるカタルポール(Catalpol)には利尿作用が確認されている。
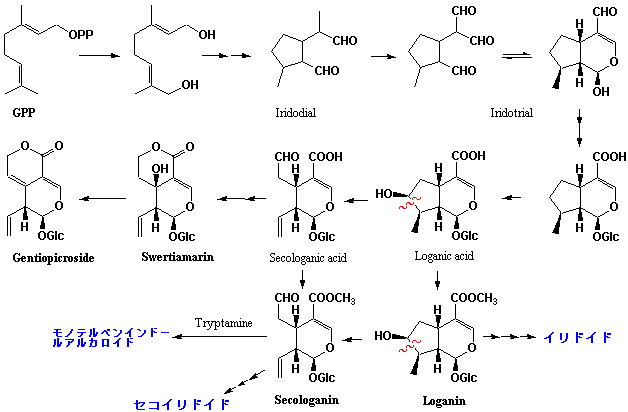
五員環部が開裂したものを別にセコイリドイド(secoiridoid)と称し、そのほとんどはセコロガニン(Secologanin)から生合成される。リンドウ科植物に含まれる苦味配糖体と称されるもの、例えばゲンチアナ、リンドウに含まれるゲンチオピクロシド(Gentiopicroside)、センブリのスウェルチアマリン(Swertiamarin)はセコイリドイドである。リンドウ科およびミツガシワ科ミツガシワなど近縁科植物にも同成分あるいは類似の成分が広く分布する。また、植物界に広く分布するセコロガニンはインドールアルカロイドの生合成前駆体として重要な存在である(→トリプトファン由来のアルカロイド)。そのほか、イリドイドから派生すると思われる二次代謝物として、マタタビ科マタタビに含まれるマタタビアルカロイド(Actinidia alkaloid)と総称されるピリジン系アルカロイドの一つアクチニジン(Actinidine)がある。標識化合物を用いた生合成実験からアクチニジンはイソプレノイド経路で生成することが明らかにされているが、その経路の詳細は明らかではない。その構造的特徴から次の図4に示すように、イリドイドの生合成経路からスピンアウトして生成すると推定されている。この推定経路では窒素原子は空気中の窒素に由来するアンモニアとして導入されるので、アクチニジンはアミノ酸を前駆体としないアルカロイド、すなわちプソイドアルカロイドと考えられている。アクチニジンは低分子量かつ疎水性であるので揮発性が高く、イエネコなどネコ属の動物がマタタビに誘引されるのもアクチジンを始めとする類縁の揮発性成分の存在による。マタタビのほか、同属種であるサルナシやオミナエシ科カノコソウなどにも含まれる。
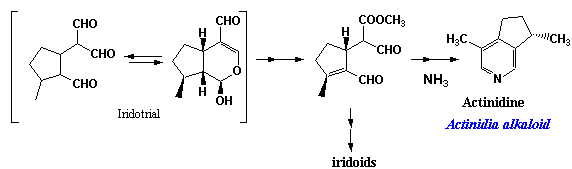
3.セスキテルペンの生合成
セスキテルペンはC15単位のファルネシル二リン酸(FPP)を生合成前駆体しとしゲラニル二リン酸(GPP)よりイソプレン単位が1個多いので、二リン酸残基の脱離で生成するカチオンからの骨格形成の様式はモノテルペンの場合よりはるかに豊かである。トランス,トランス-ファルネシル二リン酸(t,t-FPP)、及びそれが異性化したシス,トランス-ファルネシル二リン酸(c,t-FPP)からそれぞれ異なるタイプの環状カチオンが生成する。通例、非古典的カチオン(nonclassical cation)が関与するが、このカチオンにさらに分子内の他の二重結合の攻撃を受けて新しい環を形成したり、あるいは水素やアルキル基の転位を伴い、多様な基本骨格が形成される。カチオンは最終的には脱水素または水酸基アニオンの攻撃を受けてオレフィンとなるか、アルコールとなる。天然に存在するセスキテルペンは以上のようにして生成した基本骨格がさらに二次的な修飾を受けるのでもっとも多種多様な二次代謝産物の一つである。
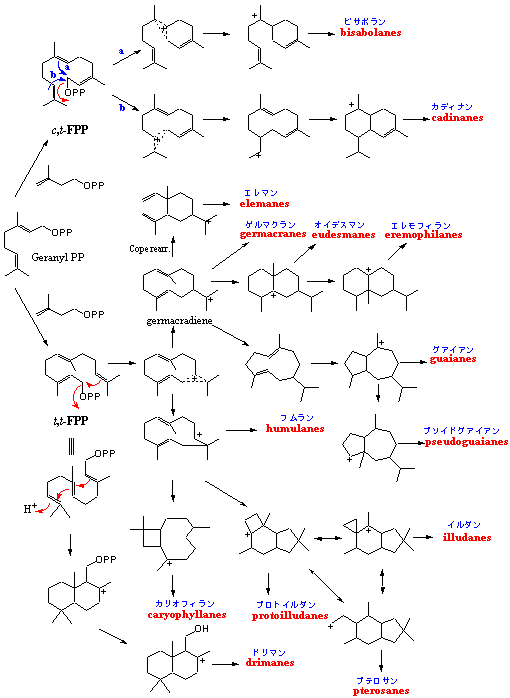
セスキテルペンはモノテルペンより分子量は大きくなるので精油成分として存在するものは限られる。フトモモ科チョウジのつぼみから得ら.gif) れる精油(チョウジ油; clove oil)に含まれるフムレン(Humulene)、カリオフィレン(Caryophyllene)は親水性官能基を持たない炭化水素成分であり、天然には比較的広く分布する。シナヨモギ(Seriphydium cinum)やミブヨモギなど同属種の未開花に含まれる駆虫成分サントニン(右構造式;Santonin)はオイデスマン(eudesmane)骨格をもつセスキテルペンである。ワタ(キダチワタなど)の種子(およびそれから得られる綿実油)に含まれるゴシポール(左構造式;Gossypol)は
れる精油(チョウジ油; clove oil)に含まれるフムレン(Humulene)、カリオフィレン(Caryophyllene)は親水性官能基を持たない炭化水素成分であり、天然には比較的広く分布する。シナヨモギ(Seriphydium cinum)やミブヨモギなど同属種の未開花に含まれる駆虫成分サントニン(右構造式;Santonin)はオイデスマン(eudesmane)骨格をもつセスキテルペンである。ワタ(キダチワタなど)の種子(およびそれから得られる綿実油)に含まれるゴシポール(左構造式;Gossypol)は.gif) ナフトールの二量体構造をとり完全な芳香族フェノール物質であるが、生合成的にはカディナン系セスキテルペンが芳香化したのち、ラジカル機構による酸化カップリングで二量化したものである。クソニンジンには、カディナン(cadinane)骨格の一部が切断され、ペルオキシドによって環化されたアルテミシニンなる特異成分を含み、抗マラリア薬として用いられている。ドクウツギ科ドクウツギに含まれる神経毒成分コリアミルチン、ツチンも同じ結合が切断されながら、まったく異なる環化を経るので、アルテミシニンとは構造が大きく異なる。東南アジアの熱帯に産するツヅラフジ科Anamirta cocculusに含まれるピクロトキシニンもドクウツギの成分と同類の変形カディナンで、いずれもGABAアンタゴニスト作用に基づく神経毒なので、これをピクロトキサン(Picrotoxane)と総称することもある(以上、図5)。一方、ニガヨモギは前述のクソニンジンと同じヨモギ属の一種であるが、いずれとも異なるグアイアン(guaiane)二量体のアブシンチンなる強苦味成分を含む。サントニンを含むシナヨモギ・ミブヨモギは最近の分類学では別属(Seriphydium)に区別されたが、ヨモギ属にごく近縁であることにかわりはない。ヨモギ属はセスキテルペノイドを含む共通の化学的特徴があるが、化学的に非常に多様である。イルダン(illudane)は担子菌とシダ類の一部種に見られるシクロプロパンがスピロ結合した構造をもつユニークなセスキテルペンである。コバノイシカグマ科ワラビには発がん作用成分として知られるイルダン配糖体プタキロシドを含む。ワラビは山菜として比較的広く利用されているが、通常のあく抜きの過程で不安定なプタキロシドはほとんど分解するため、発がん性の心配はほとんどない。イチョウ科イチョウにはビロバライドなる高度に酸化されたきわめて複雑な構造をもつ成分が含まれる(詳細はこちらを参照)。ビロバライドは15個の炭素から構成されるが、前述の骨格のいずれにも該当せず、その生合成は不明とされてきた。最近の知見によると、共存するジテルペン成分ギンコライドからC5単位が失われて生成するという。
ナフトールの二量体構造をとり完全な芳香族フェノール物質であるが、生合成的にはカディナン系セスキテルペンが芳香化したのち、ラジカル機構による酸化カップリングで二量化したものである。クソニンジンには、カディナン(cadinane)骨格の一部が切断され、ペルオキシドによって環化されたアルテミシニンなる特異成分を含み、抗マラリア薬として用いられている。ドクウツギ科ドクウツギに含まれる神経毒成分コリアミルチン、ツチンも同じ結合が切断されながら、まったく異なる環化を経るので、アルテミシニンとは構造が大きく異なる。東南アジアの熱帯に産するツヅラフジ科Anamirta cocculusに含まれるピクロトキシニンもドクウツギの成分と同類の変形カディナンで、いずれもGABAアンタゴニスト作用に基づく神経毒なので、これをピクロトキサン(Picrotoxane)と総称することもある(以上、図5)。一方、ニガヨモギは前述のクソニンジンと同じヨモギ属の一種であるが、いずれとも異なるグアイアン(guaiane)二量体のアブシンチンなる強苦味成分を含む。サントニンを含むシナヨモギ・ミブヨモギは最近の分類学では別属(Seriphydium)に区別されたが、ヨモギ属にごく近縁であることにかわりはない。ヨモギ属はセスキテルペノイドを含む共通の化学的特徴があるが、化学的に非常に多様である。イルダン(illudane)は担子菌とシダ類の一部種に見られるシクロプロパンがスピロ結合した構造をもつユニークなセスキテルペンである。コバノイシカグマ科ワラビには発がん作用成分として知られるイルダン配糖体プタキロシドを含む。ワラビは山菜として比較的広く利用されているが、通常のあく抜きの過程で不安定なプタキロシドはほとんど分解するため、発がん性の心配はほとんどない。イチョウ科イチョウにはビロバライドなる高度に酸化されたきわめて複雑な構造をもつ成分が含まれる(詳細はこちらを参照)。ビロバライドは15個の炭素から構成されるが、前述の骨格のいずれにも該当せず、その生合成は不明とされてきた。最近の知見によると、共存するジテルペン成分ギンコライドからC5単位が失われて生成するという。
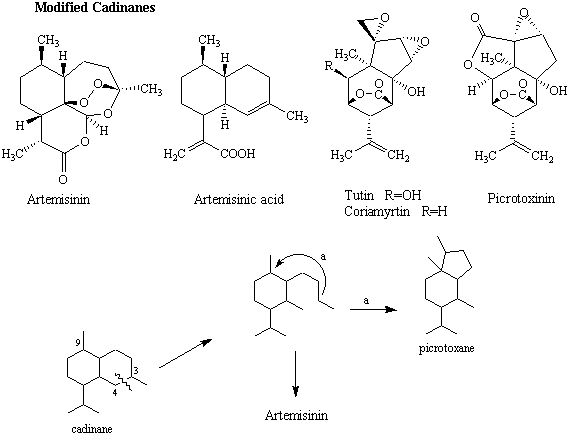
4.イチョウに含まれる”セスキテルペノイド”の生合成
イチョウ科イチョウには特有のテルペノイド成分が含まれ、欧米で人気の高いイチョウ葉エキス(EGb761)の活性成分の一つと考えられている。イチョウのテルペノイドはいずれも高度に酸化されたもので、C15とC20の2タイプがある。C20のタイプはギンコライドと称され、イチョウ葉から多くの類縁物質が報告され、生合成的にラブダン系ジテルペノイドの変形と推定されている(ジテルペノイドの生合成を参照)。一方、C15のビロバライドは以上述べたいずれのセスキテルペノイドとも生合成的関連が認められず、それもビロバライド1種のみが知られ、ほかに類縁成分は存在しない。イチョウ特有の特殊なセスキテルペノイドと考える見解もあるが、ギンコライドAとビロバライドの炭素骨格を比較してみると、図6に示すように、ギンコライドAの1つのメチル基が結合の切断に伴って隣接炭素に転位し、C51単位が除去されると、立体化学も含めてビロバライドに一致することがわかる。したがって、ビロバライドはギンコライドAの代謝産物とみるべきで、ファルネシル二リン酸に由来するセスキテルペノイドではないと考えられる。
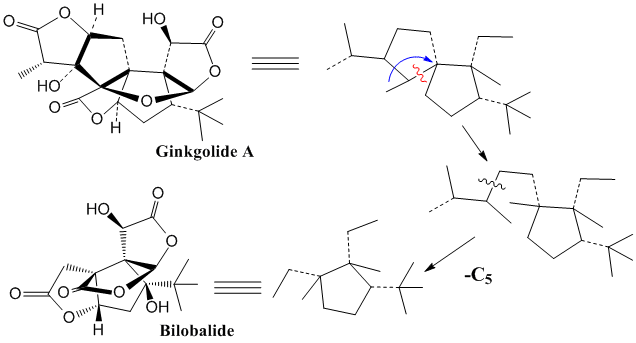
5.セスキテルペン由来のプソイドアルカロイド
スイレン科コウホネの根茎は特異なプソイドアルカロイド(pseudoalkaloid)を含むことが知られている。生合成経路はまだ明らかにされていないが、窒素原子を除いた骨格は直鎖のファルネシル鎖に近く炭素-炭素の結合で環が形成されていないので、窒素が導入されるのは生合成のかなり初期の段階と思われる。おそらく、図6に示すようにファルネシル二リン酸(FPP)から生成した鎖状の中間体にアンモニア性窒素が導入される特殊な経路により生合成されると考えられる。したがって、セスキテルペンとはいいながら、前述のいずれの骨格にも属さず、ファルネシル二リン酸の骨格を残す比較的原始的な二次代謝産物といえる。