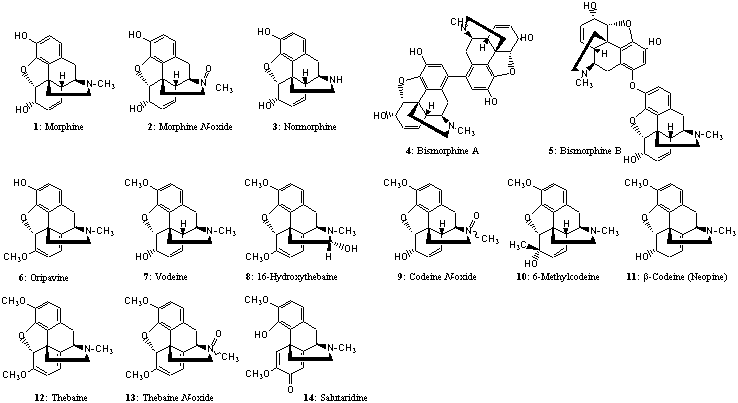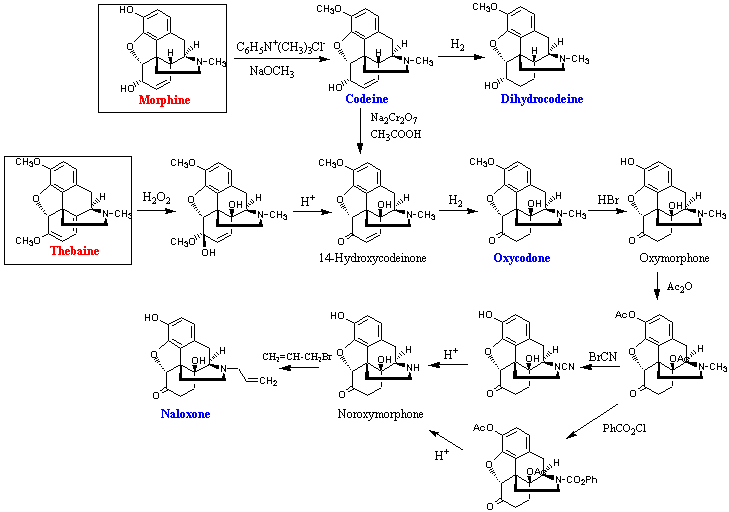1.アヘンに含まれる二次代謝成分
アヘンの効果はギリシア時代から知られていたが、多くの科学者の関心にもかかわらず長らくその薬効の本体は謎であった。 1803年、パリのデローネ(Jean-Francois Derosne, 1774 - 1855)はアヘンの麻酔作用成分としてナルコチン(Narcotine)を単離したと発表したが、後にそれには麻酔鎮痛作用はないことがわかった。アヘンの麻酔鎮痛作用成分の本体を初めて明らかにしたのはドイツの薬剤師セルチュルナー(Friedrich Wilhelm Serturner, 1783 - 1841)であり1806年のことであり、セルチュルナーはそれが前例のない有機塩基性化合物であることも合わせて指摘した。彼はこの研究結果があまり広く認められなかったことから、1817年、新たな研究結果とともにそれまでの研究をレビューとして発表し、ここで初めてアヘンから単離精製した麻酔鎮痛物質にモルヒネ(1: Morphine)の名を与えたのであった。その名の由来はギリシアの「夢の神Morpheus」に因む。モルヒネは今日でももっとも重要な医薬品の一つであり、セルチュルナーによるモルヒネの単離は化学史で有数の偉業と評価された。因みにモルヒネほか天然起源の塩基性物質に対してアルカロイドの総称名を与えたのは別のドイツ人薬剤師マイスナー(Karl F. W. Meissner)であり、1818年のことであった。モルヒネはその魔性の生物活性の故、多くの化学者がその構造の解明に参加したが、それにはその基盤となる有機化学の進歩が必須であった。マンチェスター大学(後にオックスフォード大学に移る)教授ロビンソン(Sir Robert Robinson, 1886-1975)が今日知られているのと同じ構造式を提出したのが、1925年であり、セルチュルナーが初めてモルヒネを単離してから120年を経ていた(→モルヒネの構造研究の歴史を参照)。そのモルヒネの構造式が完全証明されたのは、更に27年後の1952年であり、米国ロチェスター大学教授ゲイツ(Marshall Gates, 1915-2003)がモルヒネの全合成を初めて完成させたのであった。モルヒネに次いで、1832年にはコデイン(7: Codeine)、1848年にはパパベリン(15: Papaverine)が単離された。デローネの単離したナルコチンは麻酔作用はなかったのでノスカピン(24: Noscapine)と改称され、現在では鎮咳薬として用いられる。以上の成分はいずれもアルカロイドであり、アヘン中のアルカロイド含量は約25%を占め、約40種のアルカロイド成分が知られている。アヘンの成分はアルカロイドだけではないが、薬効的には全てアルカロイドに帰結するため、アヘン成分といえばアルカロイドを指すようになっている。アヘン中のモルヒネ含量は7~17%でもっとも多く、次いでノスカピンが3~8%、コデイン0.7~2%、パパベリン0.5~3%となっている。アヘンアルカロイドはモルヒナン(morphinan)系、ベンジルイソキノリン(benzylisoquinoline)系、フタリドイソキノリン(phthalideisoquinoline)系、テトラヒドロプロトベルベリン(tetrahydroprotoberberine)系、
1803年、パリのデローネ(Jean-Francois Derosne, 1774 - 1855)はアヘンの麻酔作用成分としてナルコチン(Narcotine)を単離したと発表したが、後にそれには麻酔鎮痛作用はないことがわかった。アヘンの麻酔鎮痛作用成分の本体を初めて明らかにしたのはドイツの薬剤師セルチュルナー(Friedrich Wilhelm Serturner, 1783 - 1841)であり1806年のことであり、セルチュルナーはそれが前例のない有機塩基性化合物であることも合わせて指摘した。彼はこの研究結果があまり広く認められなかったことから、1817年、新たな研究結果とともにそれまでの研究をレビューとして発表し、ここで初めてアヘンから単離精製した麻酔鎮痛物質にモルヒネ(1: Morphine)の名を与えたのであった。その名の由来はギリシアの「夢の神Morpheus」に因む。モルヒネは今日でももっとも重要な医薬品の一つであり、セルチュルナーによるモルヒネの単離は化学史で有数の偉業と評価された。因みにモルヒネほか天然起源の塩基性物質に対してアルカロイドの総称名を与えたのは別のドイツ人薬剤師マイスナー(Karl F. W. Meissner)であり、1818年のことであった。モルヒネはその魔性の生物活性の故、多くの化学者がその構造の解明に参加したが、それにはその基盤となる有機化学の進歩が必須であった。マンチェスター大学(後にオックスフォード大学に移る)教授ロビンソン(Sir Robert Robinson, 1886-1975)が今日知られているのと同じ構造式を提出したのが、1925年であり、セルチュルナーが初めてモルヒネを単離してから120年を経ていた(→モルヒネの構造研究の歴史を参照)。そのモルヒネの構造式が完全証明されたのは、更に27年後の1952年であり、米国ロチェスター大学教授ゲイツ(Marshall Gates, 1915-2003)がモルヒネの全合成を初めて完成させたのであった。モルヒネに次いで、1832年にはコデイン(7: Codeine)、1848年にはパパベリン(15: Papaverine)が単離された。デローネの単離したナルコチンは麻酔作用はなかったのでノスカピン(24: Noscapine)と改称され、現在では鎮咳薬として用いられる。以上の成分はいずれもアルカロイドであり、アヘン中のアルカロイド含量は約25%を占め、約40種のアルカロイド成分が知られている。アヘンの成分はアルカロイドだけではないが、薬効的には全てアルカロイドに帰結するため、アヘン成分といえばアルカロイドを指すようになっている。アヘン中のモルヒネ含量は7~17%でもっとも多く、次いでノスカピンが3~8%、コデイン0.7~2%、パパベリン0.5~3%となっている。アヘンアルカロイドはモルヒナン(morphinan)系、ベンジルイソキノリン(benzylisoquinoline)系、フタリドイソキノリン(phthalideisoquinoline)系、テトラヒドロプロトベルベリン(tetrahydroprotoberberine)系、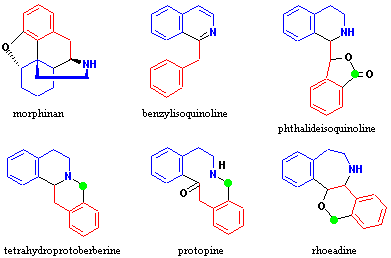 プロトピン(protopine)系、ロエアジン(rhoeadine)系という6つの骨格群に分類されるが、左図に示すように、チロシンを前駆体とするアミノ酸経路で生合成される(→アヘンアルカロイドの生合成を参照)。青く記した部分はチラミン、赤い部分はp-ヒドロキシフェニルケトピルビン酸に由来し、いずれもチロシンから生成する中間体である。緑色で記した部分はベルベリンブリッジと称されるメチオニンに由来するC1炭素である。このうち、数、含量ともにもっとも多いモルヒナン系以外は非麻薬性成分である。モルヒナン系(図1)のうち、モルヒネ、コデイン、テバイン(12: Thebaine)にはN-オキシド体も知られており、モルヒネとテバインのN-オキシド体はそれぞれR体、S体の両方が知られているが、コデインはR体のみが知られている。テバイン-N-オキシドはハカマオニゲシPapaver bracteatumからも単離されている。これらのアルカロイドの中で眠りを誘い痛みを鎮めるMorpheusの魔力がもっとも強く現れる物質はモルヒネである。あまり言及されることはないが、モルヒネの副作用としては吐き気、嘔吐を催すこと、胃腸のぜん動を減退させることによる重度の便秘(医療用に用いる場合、これらの副作用を抑える薬剤の服用が必要不可欠である)がある。古来、アヘンは必ずしも眠りを誘い痛みを緩和する目的で用いられてきた訳ではない。欧州が暗黒時代にあった頃、西半球で栄華をきわめていたのはサラセン帝国のアラビア民族であった。当時のアラビア医学ではアヘンを赤痢の治療に用いていたが、感染力の強い赤痢を抑えるにはその激しい下痢を止める必要があり、アヘンの強い止瀉作用はなくてはならないものであったと思われる。日本薬局方収載のアヘン末、アヘン散の薬効本質は止瀉薬であり、鎮痛薬としてはモルヒネ等の純薬が専ら用いられ、その止瀉作用は便秘を起こす副作用にすぎない。一方、
プロトピン(protopine)系、ロエアジン(rhoeadine)系という6つの骨格群に分類されるが、左図に示すように、チロシンを前駆体とするアミノ酸経路で生合成される(→アヘンアルカロイドの生合成を参照)。青く記した部分はチラミン、赤い部分はp-ヒドロキシフェニルケトピルビン酸に由来し、いずれもチロシンから生成する中間体である。緑色で記した部分はベルベリンブリッジと称されるメチオニンに由来するC1炭素である。このうち、数、含量ともにもっとも多いモルヒナン系以外は非麻薬性成分である。モルヒナン系(図1)のうち、モルヒネ、コデイン、テバイン(12: Thebaine)にはN-オキシド体も知られており、モルヒネとテバインのN-オキシド体はそれぞれR体、S体の両方が知られているが、コデインはR体のみが知られている。テバイン-N-オキシドはハカマオニゲシPapaver bracteatumからも単離されている。これらのアルカロイドの中で眠りを誘い痛みを鎮めるMorpheusの魔力がもっとも強く現れる物質はモルヒネである。あまり言及されることはないが、モルヒネの副作用としては吐き気、嘔吐を催すこと、胃腸のぜん動を減退させることによる重度の便秘(医療用に用いる場合、これらの副作用を抑える薬剤の服用が必要不可欠である)がある。古来、アヘンは必ずしも眠りを誘い痛みを緩和する目的で用いられてきた訳ではない。欧州が暗黒時代にあった頃、西半球で栄華をきわめていたのはサラセン帝国のアラビア民族であった。当時のアラビア医学ではアヘンを赤痢の治療に用いていたが、感染力の強い赤痢を抑えるにはその激しい下痢を止める必要があり、アヘンの強い止瀉作用はなくてはならないものであったと思われる。日本薬局方収載のアヘン末、アヘン散の薬効本質は止瀉薬であり、鎮痛薬としてはモルヒネ等の純薬が専ら用いられ、その止瀉作用は便秘を起こす副作用にすぎない。一方、
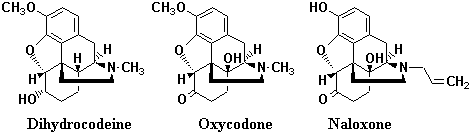
コデインはモルヒネのわずか5分の1の鎮痛作用をもつにすぎない弱オピオイドであるが、強い鎮咳作用があり習慣性も少ないので世界各国で風邪薬に配合されている。アヘン中のコデイン含量は低いので、大半はモルヒネの化学修飾(メチル化、後述)で供給されている。わが国ではコデインを還元して得られるジヒドロコデイン(Dihydrocodeine; 構造式は右)が専ら風邪薬の中に配合されている。風邪薬は薬局で医師の処方箋がなくても入手できる大衆薬(OTC)であるが、それが”麻薬起源”であることを知る人は少ないだろう。習慣性、耽溺性が少ないといっても、眠気を催す作用はコデイン、ジヒドロコデインに引き継がれており、車を運転する人にとってはこれらの服用は禁忌となっている。ただし、最近の風邪薬には覚醒作用を有するメチルエフェドリンなどが配合されているので、以前ほど眠気を催すことはなくなっている。その他のアヘン成分でテバインも重要な成分である。含量はわずかでそれ自体医薬品として用いることはないが、14位に水酸基を有し、オキシコドン(Oxycodone)やモルヒネ拮抗薬ナロキソン(Naloxone)などの製造原料として有用無比のものである(→製薬原料としてのアヘンアルカロイドを参照)。
ベンジルイソキノリン系アルカロイドではパパベリン(15: Papaverine)が鎮痙薬として使用されるほかは治療薬としての用途はない。パパベリンは現在では全合成で供給されているので、アヘンはパパベリンの製造原料としての価値はないが、それが初めて発見されたソースとしての価値は不滅である。(+)-レチキュリン(19: (+)-Reticuline)はモルヒナン系以外の多くのアヘンアルカロイドの生合成前駆体であるが、このことについてはアヘンアルカロイドの生合成として後述する。また、4環性のアポルフィンアルカロイドとして唯一イソボルジン(23: Isoboldine)が知られているが、微量成分である。
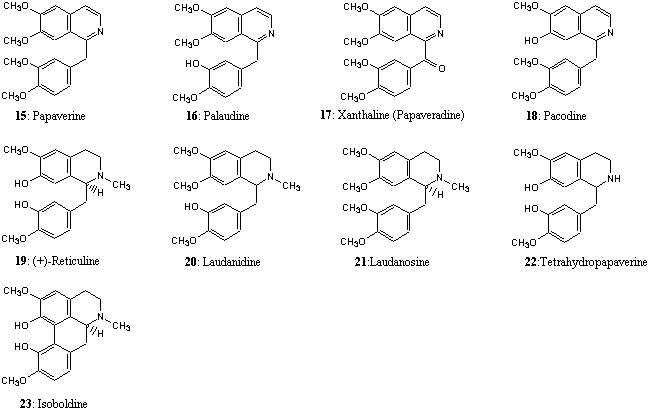
フタリドイソキノリンアルカロイドは分子内にフタリド(又はフタリミド)の部分構造を有するものであるが、後述するように生合成的にテトラヒドロプロトベルベリンに由来するものであり、二次代謝成分として決して特殊な存在ではない。ノスカピン(24: Noscapine)が中枢作用性鎮咳薬として重要な薬物であり、フタリドという構造を重視して一つのグループとしたのである。ナルセイン(27: Narceine)、ナルセイノン(28: Narceinone)もフタリド構造を取り得るものと考え、このグループに含めた。ただし、いずれもイソキノリン環部は開裂しているのでフタリドイソキノリンの名称は適当でないかもしれないが、生合成的な関連を重視した。ナルセインイミド(29: Narceine imide)はナルセインとアンモニアから生成した二次生成物(artefact)であろう。
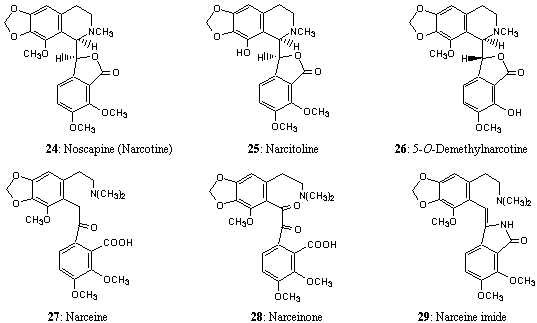
プロトピン系はケシ科に特有のアルカロイドであり、アヘンにも4種含まれている。これらの前駆体はテトラヒドロプロトベルベリンであるが、アヘンには(-)-コレキシミン(30: (-)Coreximine)と(-)-イソコリパルミン(31: (-)-Isocorypalmine)という生合成的系統の異なるものが得られている。コレキシミンは他のアヘンアルカロイドと系統的関係はなく、一方、イソコリパルミンは芳香環上の置換基から明らかにプロトピン系やロエアジン系と類縁関係が認められる。ロエアジン系はケシ属(Papaver sp.) に特有のアルカロイドであり、ユニークな構造をもつが、後述(→アヘンアルカロイドの生合成を参照)するように生合成的にはプロトピン系に由来するものである。ロエアジン系はヒナゲシPapaver rhoeasから初めて得られたので、その名の由来があり、これまでに同種と近縁種から30種以上が知られている。
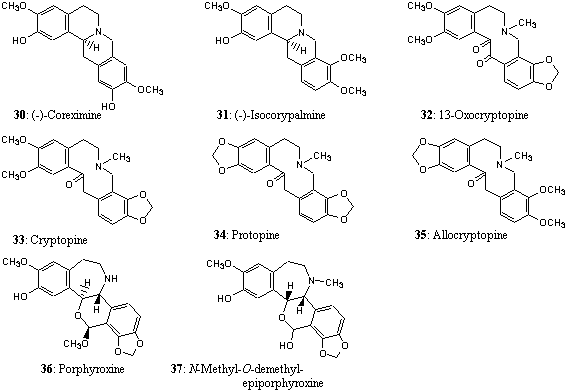
2.アヘンアルカロイドの生合成について
前述したようにアヘンに含まれるアルカロイドの構造は極めて多様である。生合成的には、アヘンアルカロイドは全てチロシンを原料とするアミノ酸経路で生合成されるベンジルイソキノリンの系統であり、レチキュリンを前駆体として生合成される。モルヒナン系アルカロイドは5個の環から構成される複雑な化合物で、フェナンスレンが基本骨格をなすのは確かだが、植物化学的には他のアルカロイドと同じベンジルイソキノリンの系統である(→これを理解するにはモルヒネの骨格はベンジルイソキノリンであるを参照)。しかし、不思議なことに、モルヒナン系アルカロイドとその他のアルカロイドとでは平面構造式では同じ前駆体だが光学的には異なる別の前駆体から生合成される。すなわちモルヒナン系は(-)-レチキュリン、テトラヒドロプロトベルベリンに由来するその他のアルカロイドはその鏡像異性体である(+)-レチキュリンから生合成されるのである。また、(+)-レチキュリンそのものもアヘン成分の一つであることが知られている。一つの植物種においてそれぞれ異なる鏡像体が生合成前駆体となる例はきわめて稀である。実際にアヘンアルカロイドとして単離されている(+)-レチキュリンが本来の代謝物(native metabolite)であり、(+)-レチキュリンオキシダーゼによりデヒドロレチキュリニウムを生成し、それが更に立体特異的に1,2-デヒドロレチキュリニウムリダクターゼによって(-)-レチキュリンに還元された後、モルヒネなどモルヒナンアルカロイドに前駆体として取り込まれるのである。このことは標識化合物を用いた実験でも実証されている。(-)-レチキュリンはサルタリジンシンターゼにより位置選択的酸化カップリングによりサルタリジン(Salutaridine)に変換される。サルタリジンのケトンはサルタリジンリダクターゼにより還元されてサルタリジノール-7-O-アセチルトランスフェラーゼによりアセチル化され、その結果生成するアリールアセテートはフェノール性水酸基によって非酵素的syn SN2置換反応が進行し、モルヒネの5番目のテトラヒドロフラン環が形成されテバインに変換される。テバインはデメチル化されネオピノンになるが、この反応に関わる酵素はまだ補足されていない。ネオピノンの互変異性体コデイノンがコデイノンリダクターゼにより還元されてコデイノンを生成する。コデインのデメチレーションにより最終産物であるモルヒネになるのだが、この反応を触媒する酵素もまだケシからは補足されておらず、哺乳動物肝臓に存在することは知られている。アヘン中のモルヒナンの含量は高いので、仮に(-)-レチキュリンの生合成をスイッチオフできればモルヒナンは生成しないことになるので、理論的にはノスカピンなどの相対含量を高くすることができるはずである。今後、この観点からの研究が進めばモルヒナン以外のアルカロイドの薬としての応用研究が進むことが期待されるよう。
アヘンは人類の歴史に数々の伝説をもたらしてくれたが、もしモルヒネが(+)-レチキュリンから生合成されたならば、人類はモルヒネのもつ眠りを誘い痛みを鎮める効果の恩恵を受けることはなかったであろし、また、アヘン中毒のような悲惨な麻薬禍に悩まされることもなかったであろう。なぜならどんな頑固な痛みも鎮めてくれる天使の作用、天国に昇ったかのような多幸感はl-モルヒナン、すなわち(-)-モルヒナンだけに与えられているからである。この事実は自然界の摂理というよりむしろ神の意志によって創造されたかのようにみえる。アヘンアルカロイドで明らかにされた一見矛盾とも見える自然界の摂理は、およそ自然発生には見えず神の意志によって創造されたようにみえるので、進化論者を論破するエビデンスに渇望していた天地創造論者を喜ばせたのではあるまいか。
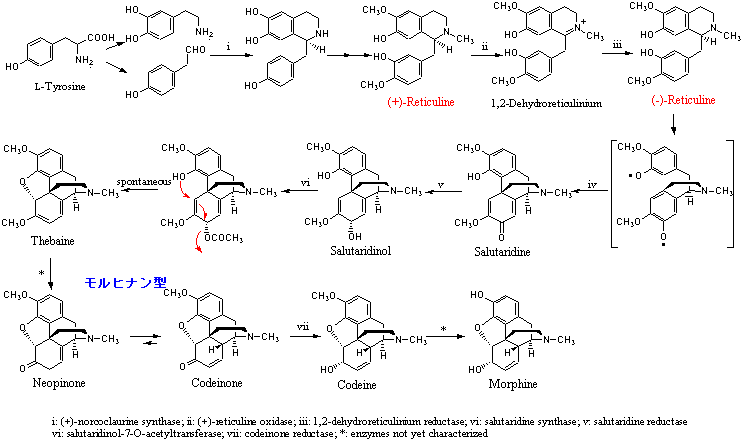
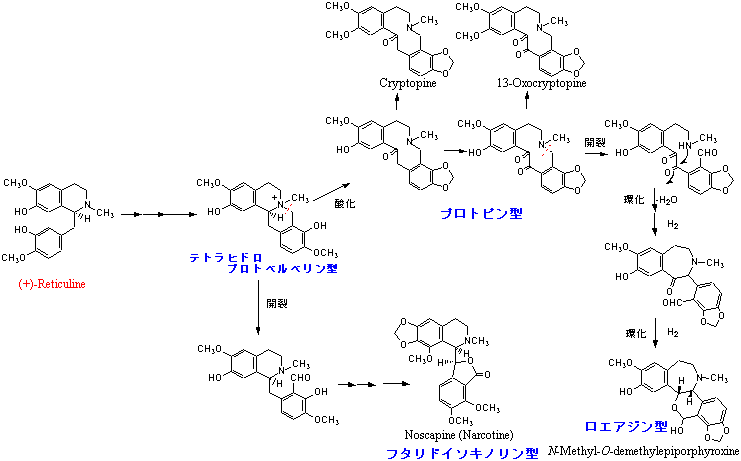
3.製薬原料としてのアヘンアルカロイド
アヘンに含まれる成分は有用な治療薬ばかりでなく、有用な医薬原料となるものも含まれる。今日では、アヘン中毒の治療にはモルヒネ拮抗薬が用いられる。アヘンの急性中毒では呼吸麻痺が起き、それによって死に至ることも多いのであるが、ナロキソンはオピオイド受容体においてモルヒネと拮抗的に作用するかけがえのない薬物の一つであり、モルヒネによる呼吸麻痺に対する治療薬として使われている。ナロキソンは複雑な構造をしたモルヒナン系化合物だが、天然には存在は知られていない物質である。アヘンあるいはハカマオニゲシPapaver bracteatumにはテバインというモルヒナン誘導体が含まれており、ナロキソンはそれから長い行程を経て創製されている(図6)。まず、テバインあるいはコデインの14位に水酸基を導入しなければならないのだが、モルヒネの構造研究の過程で発見された二クロム酸カリウム(K2Cr2O7)又は過酸化水素を用いる。次にN-メチル基を除去し、2級アミンに変換しなければならないが、これもモルヒネの化学変換反応の途上で発見されたvon Braun反応を用いて行う。すなわち、シアン化臭素(BrCN)でメチル基をニトリル基に置換し、酸で加水分解、脱炭酸して2級アミンとする。このようにして得た2級アミンをアリル化して、ナロキソンを合成する。ナロキソンはモルヒネ類縁のオピオイド薬物の創製研究の過程で偶然発見されたもので、モルヒネ拮抗作用というユニークな活性がオピオイド受容体の基礎研究の展開に大きく役立ったのである(→モルヒネの鎮痛作用とモルヒネ類縁合成鎮痛薬を参照)。モルヒネはアヘンにおいて含有率がもっとも高い成分であるが、感冒薬に鎮咳薬として配合されるジヒドロコデインはモルヒネから2行程、すなわちフェノール性水酸基をメチル化、次いで接触還元によるオレフィンの還元で調製される。有機化学的にはいずれも簡単な反応であるが、このうち前者の反応、すなわちメチル化は産業ベースで行うにはそれほど簡単な反応ではなく、その遂行にはフェニルトリメチルアンモニウム塩という実験室ではあまり用いない試薬を用いる。これもモルヒネの構造決定研究、化学変換反応の研究において見出されたもので、前述のvon Braun反応などとともにモルヒネの化学が有機化学の進歩に大きく貢献したことが理解できるだろう。また、モルヒネから調製されるコデインを経由してオキシコドン、ナロキソンも合成することができる。