1.生物多様性とは複層的な概念である
近年の地球環境保全への関心が急速に高まる中で、その共通のキーワードとして広く使われている言葉に「生物多様性 (biodiversity)」というのがある。現在では、地球環境保全のみならず、野生生物種をバイオテクノロジーによる品種改良のための貴重な生物資源(この場合はしばしば遺伝資源として言及することが多い)と捉える観点から、また将来の医薬品開発において 先導化合物の探索ソースとしても熱い注目を集めつつある。しかし、一般人の間でその意味を正確に把握している人は少ない。生物多様性とは、基本的にはあらゆる生物種(動物、植物、微生物)と、それによって成り立っている生態系、さらに生物が過去から未来へと伝える遺伝子とを合わせた概念であるが、これだけで生物多様性の全貌を把握できる人は少ないであろう。概念としての生物多様性が理解しづらいのは様々な視点から複層的に捉えなければならず具体的なイメージを掴みにくいからであろう。ここでは生物多様性について例をあげて説明するが、一言で表現することは不可能に近いことを断っておく。
2.生物多様性には「個体」、「種」、「生態系」の各レベルの多様性がある
一般に生物多様性は少なくとも3つのキーワードで捉える必要がある。一つは「個体
の多様性(diversity of the individual)」である。人間も含めて生物は多様な遺伝形質(genetic traits)をもっており、各個体に含まれる遺伝情報の総和がこれにあたり、「遺伝子変異の多様性」と言い換えることもできる。現在、クローン動物がつくられ、ひょっとするとクローン人間も出現しかねない時勢であるが、クローンは親からの遺伝子の複製であり、個体数がいくら多くても遺伝子的多様性の観点からは個体数が1の時と全く同じとなる。畑などに植えられる栽培植物は遺伝子的に均質なものであり、病害虫や異常気象などによる環境の変化があった場合、ほとんど同じようにダメージを受ける。これは遺伝形質がほとんど同じため、病害虫や異常気象などによる環境の変化に対して同じようにしか対処できないからである。一方、こうしたことは野生植物で見かけることはほとんどない。野生種は遺伝子的多様性が豊かで個体ごとに遺伝形質が異なり、その多様な形質のあるものは環境の激変に耐えうる形質をもっているからである。人類は歴史的に多くの有用植物種を利用してきたが、いずれも遺伝子的多様性の中から特定の形質を選抜してきたものである。いわゆる栽培植物の遺伝子的多様性が低いのはそのためである。バイオテクノロジーの進展とともに「
遺伝資源
(genetic resources)」確保の必要性が叫ばれてきたが、当該種における多様な遺伝形質の総和がその評価の基準となる。現在のように異常気象が常態化している時代には、食用資源など有用植物資源について個体レベルの多様性は特に重要な要素であることを理解する必要がある。例えば稲などの食糧生産で特定の品種だけを栽培するのはそれだけリスクが高くなっていることを理解しなければならない。
2番目のキーワードは「種の多様性(diversity of the species)」である。これは地球上に存在する全生物種の総数に相当すると考えればよい。種(species)とは、”一つのまとまりある個体群で他の個体群と明確に区別できる不連続的変異があってその形質変異が遺伝的に継承されるもの”をいう。遺伝形質の不連続的変異はもともと連続的に存在したもののうち特定の変異群が失われるか、または突然変異により生じる。変異は環境の変化に対する適応の結果生じるものであり,この延長線上にあるのが「種の分化(differentiation of the species)」である。また、突然変異によって生じた変異で優れた形質のみが生き残る過程を「種の進化(evolution of the species)」という。ダーウインはその著書「種
の起源」で生物の進化に言及し、「自然淘汰
(natural selection)説」として知られているが、今日的定義によれば前者の「種の分化」を論じたものと考えるべきである。現存する種は長い地球の歴史における進化と分化の結果であるが、この地球上にどれだけの生物が分布するのだろうか?最も広く支持されている推計によれば500万~1000万種が分布するというが、中には3000万種以上という見解もある。いずれにせよ、現在、環境の観点から未曾有の危機にあるといわれる地球には想像を絶する多くの生物が生息していることは事実であり、いわゆる生物多様性とは種の多様性を指すことが多い。
3番目のキーワードは「生態系
の多様性(diversity of the ecosystem)」である。生物は個々かってに生きているわけではなく、他の生物種とともに一定の生物圏の中に組み込まれて生存競争のもとで相互依存的に生息しており、それを生態系(ecosystem)と称する。生態系を構成する生物種の組み合わせは無数に存在し、気候、地質など自然環境により異なってくる。地球の自然環境は多様なので、それに伴って多様な生態系が存在することになる。生態系とそれを構成する生物種の枠組みは固定的なものではなく生物種によっては様々な生態系に生息するものがある。それは「個体の多様性」によって様々な生態系での生存を可能にする遺伝形質が存在するからにほかならない。
以上、生物多様性を包括的に理解する上で重要な3つのキーワードを挙げた。これらはそれぞれ独立して考え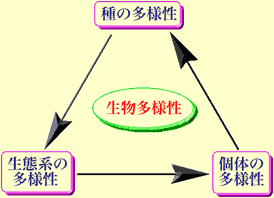 るべきものではなく右図に示すような相関関係にあり、それぞれを互いに相補的な存在として捉えることによってはじめて生物多様性を真に理解することができる。一般人の間で生物多様性の認知度が低いのは具体的なイメージとして湧いてこない点にある。例えば、第一のキーワードとして「個体の多様性」に言及したが、遺伝形質の変異すなわち遺伝子的多様性を生むのは異なる環境へ置かれたときの個体の適応能力であり、適応できなければ生存できないシステムの結果、「個体の多様性」は生まれたものである。生態系は地球上の様々な環境のもとで成立する生物のコミュニティでもあり、そこでは環境への適応だけではなく他の生物との壮絶な生存競争もある。こうした状況のもとでは各生物種は生存のため様々なかたちでの適応を余儀なくされ、同じ生物種でも異なる生態系で生息するものは互いに遺伝形質が異なってくる。このように同一の生物種が種々の異なる環境に最も適した生理的または形態的な変異を起こして多くの系統に分かれることを「適応放散
(adaptive radiation)」というが、「個体の多様性」があって初めて適応放散が可能となるのであり、「生態系の多様性」に深く依存したものであるということができる。また、「種の分化」は「適応放散」の延長線上に起きる必然的な結果と考えてもよい。以上の説明で明らかなことは、何万年、あるいは何十万年という時間的スパンで考えると種(speciesであって「たね」(seed)ではない!)は決して固定的なものではなく変動するものということである(→植物の分類と名前についてを参照)。上でも述べたが、環境への適応は遺伝形質の連続的変異の積み重ねとして適応放散を生み出し、その結果として「種の分化」が必然的に起きる。この場合、survival of the fittest、すなわち適者生存の原理が支配し、種分化は非中立的に起きる。一方、形質の不連続的変異を起こす突然変異(mutation)は必然(certain)ではなく「偶然(incidental)」に支配されるものである。それがより優れた形質、すなわち環境への適応やほかの種との共存が可能であれば新しい種として定着し、これが繰り返されれば「生物の進化」が起きる。つまり、「種分化」と比べて「種進化」はsurvival of the luckiest、すなわち生存には幸運も必要であって中立的に起きる点で区別される。今日、われわれが目にする「種の多様性」および「個体の多様性」は地球の誕生以来数十億年にわたる「生物の進化と分化の結果」であり、様々な種から構成される生態系も種の分化、進化並びに気候など環境の変動とともに進化してきたということができる。 特に生態系についてはその成立と時間的経過との間にはずれがあることに留意する必要があろう。つまり、現存する生態系は必ずしも現時点での環境に最適化されたものではなく、過去に成立したものが緩やかな変化をもって遷移途上の状態にあるということである。したがって、仮にその生態系が破壊された場合、元の生態系と同じにはならない。たとえば、本邦温帯の代表的生態系であるブナ林は倒木更新によってのみその維持が可能であり、破壊された場合、もとのブナ林には戻らない。また、生態系の構成種も必ずしもその気候環境に最適とは限らない。南西諸島南部は気候的には亜熱帯南部~熱帯北部に相当し、多くの熱帯性植物種が生育する。しかし、その生態系の中枢は関東地方南部以南の本州、九州、四国に見られる照葉樹林と質的には同じであり、隣接する東南アジア熱帯林の主要樹種であるフタバガキ科はない。フタバガキ科は地続きでないと分布の拡大はできない。南西諸島はかって大陸とは陸続きであったが、当時は現在より気温が低く南方熱帯地域から熱帯系の構成種が侵入することはなく、逆に北方系の種が分布することになったと考えられる。生態系の多様性の成立にはこのように種の地理的分布の移動の可否の要素も含まれるので、地球上のある地域がたとえ気候的、地質的に同じであっても同じ生態系にはならない。
るべきものではなく右図に示すような相関関係にあり、それぞれを互いに相補的な存在として捉えることによってはじめて生物多様性を真に理解することができる。一般人の間で生物多様性の認知度が低いのは具体的なイメージとして湧いてこない点にある。例えば、第一のキーワードとして「個体の多様性」に言及したが、遺伝形質の変異すなわち遺伝子的多様性を生むのは異なる環境へ置かれたときの個体の適応能力であり、適応できなければ生存できないシステムの結果、「個体の多様性」は生まれたものである。生態系は地球上の様々な環境のもとで成立する生物のコミュニティでもあり、そこでは環境への適応だけではなく他の生物との壮絶な生存競争もある。こうした状況のもとでは各生物種は生存のため様々なかたちでの適応を余儀なくされ、同じ生物種でも異なる生態系で生息するものは互いに遺伝形質が異なってくる。このように同一の生物種が種々の異なる環境に最も適した生理的または形態的な変異を起こして多くの系統に分かれることを「適応放散
(adaptive radiation)」というが、「個体の多様性」があって初めて適応放散が可能となるのであり、「生態系の多様性」に深く依存したものであるということができる。また、「種の分化」は「適応放散」の延長線上に起きる必然的な結果と考えてもよい。以上の説明で明らかなことは、何万年、あるいは何十万年という時間的スパンで考えると種(speciesであって「たね」(seed)ではない!)は決して固定的なものではなく変動するものということである(→植物の分類と名前についてを参照)。上でも述べたが、環境への適応は遺伝形質の連続的変異の積み重ねとして適応放散を生み出し、その結果として「種の分化」が必然的に起きる。この場合、survival of the fittest、すなわち適者生存の原理が支配し、種分化は非中立的に起きる。一方、形質の不連続的変異を起こす突然変異(mutation)は必然(certain)ではなく「偶然(incidental)」に支配されるものである。それがより優れた形質、すなわち環境への適応やほかの種との共存が可能であれば新しい種として定着し、これが繰り返されれば「生物の進化」が起きる。つまり、「種分化」と比べて「種進化」はsurvival of the luckiest、すなわち生存には幸運も必要であって中立的に起きる点で区別される。今日、われわれが目にする「種の多様性」および「個体の多様性」は地球の誕生以来数十億年にわたる「生物の進化と分化の結果」であり、様々な種から構成される生態系も種の分化、進化並びに気候など環境の変動とともに進化してきたということができる。 特に生態系についてはその成立と時間的経過との間にはずれがあることに留意する必要があろう。つまり、現存する生態系は必ずしも現時点での環境に最適化されたものではなく、過去に成立したものが緩やかな変化をもって遷移途上の状態にあるということである。したがって、仮にその生態系が破壊された場合、元の生態系と同じにはならない。たとえば、本邦温帯の代表的生態系であるブナ林は倒木更新によってのみその維持が可能であり、破壊された場合、もとのブナ林には戻らない。また、生態系の構成種も必ずしもその気候環境に最適とは限らない。南西諸島南部は気候的には亜熱帯南部~熱帯北部に相当し、多くの熱帯性植物種が生育する。しかし、その生態系の中枢は関東地方南部以南の本州、九州、四国に見られる照葉樹林と質的には同じであり、隣接する東南アジア熱帯林の主要樹種であるフタバガキ科はない。フタバガキ科は地続きでないと分布の拡大はできない。南西諸島はかって大陸とは陸続きであったが、当時は現在より気温が低く南方熱帯地域から熱帯系の構成種が侵入することはなく、逆に北方系の種が分布することになったと考えられる。生態系の多様性の成立にはこのように種の地理的分布の移動の可否の要素も含まれるので、地球上のある地域がたとえ気候的、地質的に同じであっても同じ生態系にはならない。
3.生物多様性の減少は危機的な地球環境への警鐘である
現在、地球環境保全の観点から多くの科学者によって危惧されている「生物多様性の危機」とは、「種の多様性」の急激な喪失すなわち多くの生物種がかってないほどの速度で絶滅しつつある状況のことを指している。「種の多様性」の喪失は生態系の破壊によってもたらされ、科学者の推計では熱帯雨林(現在、地球上で最も危惧される生態系である)に生息する生物種(地球上の総種数の3分の2以上といわれている)の5パーセントから10パーセントが今後30年間の間に絶滅するとしている。熱帯では主に経済発展に伴う開発圧力が背景にあるが、一方で温帯地域にも酸性雨などによる森林の立ち枯れがあって多くの生物が絶滅の危機にあることは確かである。中には何百万種以上もいる生物種の中で高々10パーセント絶滅することが何故そんなに深刻な問題なのかと疑問を呈する意見もあろう。既に述べたように全ての生物が地球上の生物圏の中にある多様な生態系においてコミュニティを形成しながら相互依存的に生息し、また依存なく生存できる生物種は皆無であることを考えれば、この問題の深刻さは容易に理解できよう。この場合の生物とは人類を含めたいわゆる動植物のほか、土壌中に生息する微生物など通常目に触れないものも含む。各生物種は激しい生存競争の一方で、相互依存的に微妙なバランスのもとで生息している。もしまとまった数の種が絶滅したとしたら、微妙なバランスの相互依存関係が非可逆的に崩壊することを意味する。自然界の生態系は非常に複雑なシステムであり、その構成要素が欠ければ根底から破壊されるのは必定であることを認識する必要がある。例えば、コンピュータで中核となるシステムファイルを一つでも削除した場合、確実に重大なシステム障害が起きる。それと似たことが自然界のシステムで起きても決して不思議ではないのである。これを理解するには、1977年、スタンリー・テンプルという生態学者が米国の権威ある学術雑誌『サイエンス』誌上で報告した”ドードーの絶滅と激減した植物種”の例を引用することがもっとも有効であろう。インド洋の大陸から遠く離れた孤島モーリシャス島の高地には、アカテツ科のCalvaria majorという固有種が生育しているが、1970年代には十数本しかなくいずれも樹齢数百年という古木ばかりだったことが知られている。この植物はよく結実するものの自然状態では全く発芽しないので、世代交代ができずいずれ絶滅は避けられない。この不思議な事実にテンプルはその原因は生物間の相互依存の断絶によるものと推定し、1681年に絶滅したドードーという鳥類と密接な関連があるのではないかと考えたのである。実際、内果皮が石のように硬いこの木の果実は種子に切れ込みが入らなければ発芽しない。ドードーに食べられてその胃袋と砂嚢での消化を経てはじめて種子に切れ込みが入り、体外に排出されて発芽、世代交代を繰り返してきたというのがテンプル説の概要である。ドードーではなくインコとコウモリの激減がその原因とする説もあるが、いずれにせよモーリシャス島におけるCalvaria majorの激減が生態系の相互依存の断絶によってもたらされたことは科学者の間で広く認められている。幸い、導入種の七面鳥がその実を食べることがわかりこの木は絶滅を免れたのであるが、一つの種の消滅が全く無関係にみえる生物種の生殺与奪を握っていることがこの例でよくわかるだろう。
前述した酸性雨についても、何らかの策をとらなければ森林の根底的破壊をもたらすと危惧されている。酸性雨は木を枯らすだけではなく、確実に昆虫など小動物や土壌中の微生物社会にも破壊的インパクトをもつからである。微生物は眼には見えないが、自然界では物質循環を担当し有機物質を分解するという重要な役割を果たしている。昆虫などの小動物も木や草を食べて土壌中の有機物を豊かにし、他の生物のための栄養分を提供する。昆虫など小動物や土壌中の微生物に何らかの異変があれば、すなわちこの循環サイクルに異変が起きれば、森はいずれ単なる枯れ木の山と化するであろう。台風などでダメージを受けた杉林で倒木が放置されたままになっている光景をよく眼にするが、それは倒木が物理的に他の植物の繁殖を妨げているため限られた植物しか生えない。こうした状況では土壌の保水力も低下し、大雨になれば土砂崩れを起こし、いずれ荒地となる。局地的に荒地ができたとしても、他地域から風にのって、あるいは鳥が種を散布し時間さへかければもとの豊かな森に戻るはずである。しかし、環境破壊が地球規模で起こり生物多様性が失われたのであれば自然のもつ治癒力によるこうした復元は限定的なものになる。この地球上には「種間の相互依存」の無数の組み合わせがある。また、われわれ人類は優れた知能で地球の生態系の頂点に立っていることは間違いのない事実だが、大規模な生態系の破壊は必然的にそれを構成する種の多様性、個体の多様性の喪失を招き、またそれが他の生態系の多様性にも影響を与えるスパイラルとなって、いずれ頂点にある人類の将来にも影を落とす結果となるであろう。すなわちわれわれ人類も地球環境の激変に無関係ではない。したがって「生物多様性の危機」は、すなわち「人類生存の危機」であることを認識する必要がある。
4.生物多様性条約(CBD)の真の目的
1992年、ブラジルのリオデジャネイロで、生物多様性に関する国際会議が開催された。ここで締結された議定書は生物多様性条約(CBD; Convention on Biological Diversity) と呼ばれている。CBDでは1.生物多様性の保全(preservation of biodiversity)、2.生物多様性の持続的利用(sustainable development of biodiversity)、3.遺伝資源としての生物多様性から得られる利益分配(sharing of benefits obtained from biodiversity)を骨子として合意がなされたが、先進国、発展途上国では国益という観点から全く相反する見解を表明しているのが現状である。発展途上国、とりわけ生物多様性の豊かな熱帯圏諸国は生物多様性を石油、鉱物資源などと同等の価値をもつ資源、すなわち遺伝資源と考え、それを対象とした開発、応用で得られる利益分配の権利を主張している。一方、先進国側は利益分配で譲歩する代わりに熱帯雨林の伐採などを規制し持続的開発の遵守を途上国側に強く求めている。先進国の主張の背景には途上国の爆発的な人口増加が森林の加速的消失を招き、それがCO2の増加、すなわち地球温暖化の主因と考えているからである。もともとCBDは「生物多様性の最大の価値は環境保全にある」とする自然環境保護グループにより提唱されたものであり、遺伝資源としての価値は生物多様性の価値そのものを高めて途上国側を納得させるための方便にすぎなかったものである。もともと資源としての生物多様性は、加工すれば確実に利益を生む鉱物資源とは異なり、長期にわたる応用研究を経てやっと価値を生むという潜在的なものに過ぎないのであるが、途上国側は早期の利益を求める傾向がある。したがってバイオテクノロジーや新薬開発などは長期の応用研究が必要なので、企業側にとっては生物多様性に関わることはすなわちハイリスクとして敬遠しがちである。現在、CBDの未締結国は米国、イラク、ソマリア、アンドラの4カ国であるが、米国は生物多様性は地理的保有国だけに帰するものではなく人類共有の資産と主張し、CBDには批准しなかったばかりか、上述の途上国側の対応を強く批判している。わが国の学識経験者の中にもこれに同調する意見があったが、もともと政治家の間でCBDに関する関心は薄く、各国首脳(米国はクリントン大統領が参列)が参列したリオ会議にも首相(当時は宮澤喜一首相)は出席しなかった。リオ会議から10年以上経た今日でも、遺伝資源、製薬資源としての価値は未だ潜在的レベルにすぎないにもかかわらず、生物多様性を対象とした開発応用研究に対する途上国側の姿勢は厳しいままである。皮肉なことに途上国では現在でも大規模な森林の伐採、消失が続いており、持続的開発の状態とはほど遠く、CBDの当初の目的である生物多様性の保全が遵守されているとはいいがたい。CBDで求められた生物多様性の保全並びに持続的利用は途上国は関心がないようである。
生物多様性の最大の価値はエコロジカルバリューとする環境保全グループの主張は絶対的に正しいが、CBDによってバブル的に暴騰した生物多様性の真の価値は途上国にはあまり認知されていないようである。このような状態が続けば確実に生物多様性は失われると思われるが、その結末はフィリピンルソン島を見ればよく理解できる。ルソン島はフィリピン最大の島であるが、もっとも開発が進み、またもっとも自然破壊の著しいところでもある。既に同島の植物種の40%は絶滅したと推定され、その多くが地球上のどこにもない固有種とされている。ラワン材は戦後の経済復興に伴い大量に輸入された木材だが、もともとはフィリピン産ティンバーの地方名である。しかし、現在のルソン島にはほとんど残存しておらず、略奪的皆伐の結果、広大な荒れ地が残ってしまった。また、河口域や海岸には広大なマングローブ林があったが、これも価値のないもの(大半の熱帯途上国はマングローブは無価値と考える意見が根強い)として大半は消失してしまった。この結果、台風や大雨になれば河川の水位はたちまちにして上がり、下流域は洪水となる。森林の非持続的開発はこのような自然災害という形でも降り掛かってくるのである。次に生物多様性の喪失は将来得られるかもしれない利益の可能性を奪ってしまう例をあげよう。筆者は文献上ルソン島北部に存在するとされるクサミズキを現地協力者とともに、長年、捜してきたが、未だに見つからず、今では絶滅したと考えている。クサミズキはカンプトテシンを含み抗癌薬イリノテカンの製造原料となる有用植物であるが、現在、イリノテカンの年間販売額は約1000億円なので、もしクサミズキがフィリピンに現存していれば栽培による薬用原料の供給だけでもかなりの利益が得られたにちがいない。クサミズキが薬用原料としての価値が認められたのはここ10年足らずのことであり、この例は現時点では全く価値はないものでも将来価値が生み出される可能性があることを示すもっともよい例といえよう。前述のラワンはその逆であり、その時点での価値は大きくても資源が枯渇すれば無価値となってしまう。ここでは非略奪的持続的開発が必要であることが理解されよう。
(引用資料)
- ドードーの絶滅
- Stanley A. Temple (1977) "Plant-Animal Mutualism: Coevolution with Dodo leads to Near Extinction of Plant" Science, 197, 885-886.
- 木村資生、『分子進化の中立説』(向井、日下部訳)、紀伊国屋書店、1986年。