1.漢方医吉益東洞が知っていた呼吸器疾患の要薬マオウ(麻黄)
右下の写真はマオウ科シナマタマオウ(Ephedra sinica)というわが国には自生しない植物で、顕花植物の中ではマツなどと同じ裸子植物に属し、もっとも原始的な分類群に属するものである(植物の系統分類参照)。写真で見る緑色の細い部位は木質茎から伸びた草質の茎であり、退化した小さな鱗片葉が節で対生して目立たず、黄色い塊状のものが花序である。この珍奇な植物の緑色の細い茎が、生薬マオウ(麻黄)の基原(ほかにE. distachyaが用いられる)であり、麻黄湯、葛根湯、麻杏甘石湯などを始め多くの漢方処方に配合されるもっとも重要な生薬の一つである。 マオウは中国最初の薬局方ともいうべき「神農本草経」で中薬120種の一つとして収載されており、その植物的珍奇性ならびに中国の奥地にしか産しないという神秘性はまさに「魔女の秘薬」を彷佛させるに十分であるが、これが、2000年後、世界中の気管支喘息に苦しむ患者に至福の朗報をもたらすとは神農皇帝も想像できなかったにちがいない。中薬とは「臣であり、性を養うを主とする。人に応じ、無毒と有毒がありその宜しきものを斟酌する。病を遏め虚羸(疲れや痩せること)を補うことを欲するものは中経を本とする」薬であり、マオウのほか、よく知られた漢方薬ではトウキ(当帰)、キキョウ(桔梗)、ボタンピ(牡丹皮;ボタンの根皮)、ボウフウ(防風)、カッコン(葛根;クズの根)など漢方で繁用される生薬が列挙されている。この中で、マオウは「中風、傷寒頭痛、牡瘧(マラリアのこと)を主治する。表を発きだし汗を出す、邪熱気を去る、止咳し上気を逆ける、寒熱を除く」などと記載されている。一方、江戸時代安芸の国出身の名医であった吉益東洞は、その著作「薬徴」で、マオウ(麻黄)の薬効について「喘咳、水気を主治するなり。旁ら、悪風、悪寒、無汗、身疼、骨節痛、一身黄腫を治す。」と書き記している。喘咳は咳がでてぜいぜいとのどが鳴る状態、水気は浮腫、悪風は悪寒の弱いもの、無汗は汗の出ない状態、身疼は全身の痛み、一身黄腫は全身に黄色がかった浮腫の状態を指し、東洞はマオウ(麻黄)によりこれらの症状を改善できるとしている。神農本草経を始め、中国の古文献では「傷寒表実」、つまり発熱悪寒があって汗が出ず、体の各所に疼痛のある場合にマオウ(麻黄)を用いるとしており、古方派漢方医である東洞も同じ見解を示している。今日、動物を用いた実験で、マオウエキスには発汗、抗炎症作用が確認されているので、マオウに伝承された薬効は確かなものといってよい。古文献で記載された薬効のうち、後に世界中の喘息患者を堪え難い苦しみから解放することになるのは止咳(神農本草経)、喘咳(東洞)の効である。咳といっても風邪をひいた時の軽いものから気管支喘息の発作の重篤なものまで千差万別であるが、とりわけ東洞の指摘した喘咳は”気管支が痙攣して気道が細くなり呼吸困難な状態”を指すと解釈されている。中国の古文献とは異なり、「薬徴」の原文では「主治喘咳水気也。旁治悪風---」と喘咳水気の主治をことさら強く主張する。喘咳には、今日、多くの人々を苦しめ、ときに致命的症状にいたる気管支喘息の発作も含まれることは容易に想像できることであり、おそらく、東洞は”マオウ(麻黄)が気管支喘息を含めた呼吸疾患に有効”であることを明言した最初の人物であろう。しかし、不幸にしてその主張はわが国も含めて世界の誰にも注目されることなく、歴史の中に埋没してしまったのである。これについては後に触れることとする。
マオウは中国最初の薬局方ともいうべき「神農本草経」で中薬120種の一つとして収載されており、その植物的珍奇性ならびに中国の奥地にしか産しないという神秘性はまさに「魔女の秘薬」を彷佛させるに十分であるが、これが、2000年後、世界中の気管支喘息に苦しむ患者に至福の朗報をもたらすとは神農皇帝も想像できなかったにちがいない。中薬とは「臣であり、性を養うを主とする。人に応じ、無毒と有毒がありその宜しきものを斟酌する。病を遏め虚羸(疲れや痩せること)を補うことを欲するものは中経を本とする」薬であり、マオウのほか、よく知られた漢方薬ではトウキ(当帰)、キキョウ(桔梗)、ボタンピ(牡丹皮;ボタンの根皮)、ボウフウ(防風)、カッコン(葛根;クズの根)など漢方で繁用される生薬が列挙されている。この中で、マオウは「中風、傷寒頭痛、牡瘧(マラリアのこと)を主治する。表を発きだし汗を出す、邪熱気を去る、止咳し上気を逆ける、寒熱を除く」などと記載されている。一方、江戸時代安芸の国出身の名医であった吉益東洞は、その著作「薬徴」で、マオウ(麻黄)の薬効について「喘咳、水気を主治するなり。旁ら、悪風、悪寒、無汗、身疼、骨節痛、一身黄腫を治す。」と書き記している。喘咳は咳がでてぜいぜいとのどが鳴る状態、水気は浮腫、悪風は悪寒の弱いもの、無汗は汗の出ない状態、身疼は全身の痛み、一身黄腫は全身に黄色がかった浮腫の状態を指し、東洞はマオウ(麻黄)によりこれらの症状を改善できるとしている。神農本草経を始め、中国の古文献では「傷寒表実」、つまり発熱悪寒があって汗が出ず、体の各所に疼痛のある場合にマオウ(麻黄)を用いるとしており、古方派漢方医である東洞も同じ見解を示している。今日、動物を用いた実験で、マオウエキスには発汗、抗炎症作用が確認されているので、マオウに伝承された薬効は確かなものといってよい。古文献で記載された薬効のうち、後に世界中の喘息患者を堪え難い苦しみから解放することになるのは止咳(神農本草経)、喘咳(東洞)の効である。咳といっても風邪をひいた時の軽いものから気管支喘息の発作の重篤なものまで千差万別であるが、とりわけ東洞の指摘した喘咳は”気管支が痙攣して気道が細くなり呼吸困難な状態”を指すと解釈されている。中国の古文献とは異なり、「薬徴」の原文では「主治喘咳水気也。旁治悪風---」と喘咳水気の主治をことさら強く主張する。喘咳には、今日、多くの人々を苦しめ、ときに致命的症状にいたる気管支喘息の発作も含まれることは容易に想像できることであり、おそらく、東洞は”マオウ(麻黄)が気管支喘息を含めた呼吸疾患に有効”であることを明言した最初の人物であろう。しかし、不幸にしてその主張はわが国も含めて世界の誰にも注目されることなく、歴史の中に埋没してしまったのである。これについては後に触れることとする。
2.マオウ(麻黄)の薬効成分エフェドリンは日本人により発見された
日本薬学会本部のある東京都渋谷区の薬学会館には、わが国”天然物化学の金字塔”となったある化学成分の標本が保管されている。19世紀に入ってから、欧州の科学者たちは薬用植物の薬効成分を次々と単離した。長い中世の暗黒時代から目覚めた欧州では、ルネッサンスの勃興で文化のあらゆる面で活気を取り戻しつつあった。その途上で誕生した科学の黎明は19世紀初頭には「天然物化学」の領域にまでおよんだ。1806年、Serturnerがアヘンからどんな頑固な痛みも鎮める万能鎮痛薬モルヒネを(これに関しては「麻薬アヘンのお話」を参照)、1820年、PelletierとCaventouがアマゾンの秘薬キナから熱帯に進駐した植民地主義者を数世紀にわたり苦しめたマラリアの特効薬キニーネ(→「植物起源医薬品」を参照)を単離した。科学の先進地欧州にはまだ遠く及ばなかったが、明治維新以降は、半植民地化の憂き目をみた中国を他山の石として、富国強兵政策によりひたすら欧米列強の後を追いかけた結果、わが国の科学水準も着実に上昇していった。阿波の国出身であり、現東京大学の前身である東校在学中、維新政府による第1回海外留学生としてドイツに派遣された長井長義は、本国の要請を受けて13年に及ぶ留学を終え、帰国して東京帝国大学薬学科教授に就任した。着任後まもなくの1887年、長井はマオウから一つのアルカロイドを単離し、エフェドリン(Ephedrine)と命名した。長井は「エフェドリンの発見」で天然物化学史に名を残すことにはなったが、それはSerturnerらが受けた栄誉とは比較にならなかった。何故なら、当時、中国の長い歴史の中で連綿と伝承されてきた要薬マオウの成分として、エフェドリンがいったい何に効くのか、長井を含めて誰も知らず、当初は付加価値のない天然有機化合物にすぎなかったからである。
マオウの主アルカロイドの薬効を明らかにしたのは陳克恢とカール・F・シュミットであ
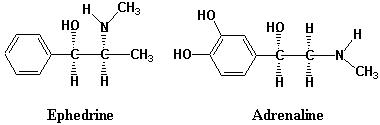
り、長井がエフェドリンを発見してから40年近く経った1924年のことであった。彼らはエフェドリンに気管支喘息の発作を劇的に抑える作用のあることを発表し、当時の欧米の医学会に衝撃を与えた。この発見は決して唐突なものではなく、周到な中国古文献の探索の結果、マオウが呼吸疾患の伝統的治療薬であること、およびエフェドリンが内因性の交感神経作動性物質アドレナリン(Adrenaline)との化学構造の類似性から達観したものであった。当時、既にアドレナリンが気管支喘息の発作に有効であることは知られていたが、経口的に服用できないばかりか作用の持続時間が短いという致命的な欠点があり、欧米の医学界はながらく経口投与が可能でより長時間効力の持続する代替薬を求めていたのであった。エフェドリンのような物質は当時の欧米には全く知られていないタイプのアルカロイドであったから、長井の単離したエフェドリンは欧米の科学者の注目を集め、当初は様々な利用をしたようである。たとえば、瞳孔を散大させる薬として眼科領域で用いたこともあった。陳・シュミットの報告以後は、エフェドリンは気管支喘息の特効薬として高い評価を受けることになった。エフェドリンはα,βの両受容体に作用し交感神経興奮作用があるほか、大脳に対する直接作用による強い中枢興奮作用があり、そのため副作用として不眠、神経過敏などが起きる。エフェドリンのこの作用は覚醒剤であるアンフェタミンより若干弱いが、容易にアンフェタミンに変換できるため、覚醒剤原料物質に指定されている。さらに血管収縮作用による血圧上昇もエフェドリンの治療薬としての重要な作用の一つであった。手術の際の脊椎麻酔に伴う血圧降下はときに致命的にさえなるが、これを改善するためエフェドリンが麻酔薬と併用された。喘息発作を緩和するのは、気管支拡張作用、鼻腔容積拡大作用のためである。米国でエフェドリンが枯草熱(hay
fever)に対して多用されてきたのは鼻腔容積拡大作用があるためである。枯草熱はブタクサなど植物の花粉に対する感受性に起因するアレルギー症状であり、わが国の花粉症と基本的には同じものである。エフェドリンはくしゃみや鼻腔のかゆみを一時的に緩和するにすぎないが、米国人は実に粘り強くエフェドリンをスプレーで投与したり、軟膏として塗ったりして枯草熱の不快さから少しでも逃れようとしたのである。消費されるエフェドリン量では枯草熱ははるかに気管支喘息を上回っていた。現在では、エフェドリンの治療薬としての重要性は低い。たとえば、気管支喘息治療薬としてはメタプロテレノールなど選択的β2受容体作動薬が主流である。しかし、エフェドリンをシード物質としてこれら多様な交感神経作動薬が創製されたのは紛れもない事実であり、その歴史的重要性は明らかである。わが国ではエフェドリンと類似の作用をもつメチルエフェドリン(Methylephedrine)が多くの風邪薬に配合されている。マオウにも少量含まれるが、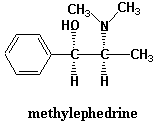 専ら合成によりd,l-メチルエフェドリンとして供給されている。特に、催眠作用のある鎮咳薬ジヒドロコデインに配合して使うことが多いが、この場合は中枢興奮による覚醒作用効果を目的とするものである。近年、再びエフェドリンが注目を集めたことがあったが、それは気管支喘息の治療とは全く関係のないものであった。米国では、エフェドラないしマファン(ma
huang;麻黄の漢音)の名の下でマオウをダイエット用サプリメントとして用いるのが流行し、わが国でもインターネット上で通信販売されていた。エフェドリンには食欲減退作用があり、ダイエット効果が期待できるとしてサプリメントとして販売されていたのであるが、特に、それまで用いられてきた食欲減退剤フェンフルラミンが心臓や肺に対して重篤な副作用があるとして販売禁止されてから売上高が急増した。しかしながら、エフェドリンの副作用である血圧上昇作用等による弊害が続出し、米国では100人を超える死者がでたとされるが、米国の監督官庁が消費者に対してエフェドラの服用を控えるよう警告を発したのはごく最近のことである(2003年12月30日、米国医薬品食品局(FDA)はエフェドラあるいはそれを含むサプリメントを販売禁止とする意向をニュースリリース(通達)として発表し、現在では禁止されている)。わが国であれば大薬害禍とされ大騒ぎになっているであろう(2002年中国製ダイエット食品事件、2003年アマメシバによる健康被害事件があった)が、おそらく、米国では肥満による健康障害の方がエフェドラ禍よりもより深刻と考え、エフェドラによるダイエット効果を評価してきたのかも知れない。およそわが国では考えられない米国流合理主義の所産というところであろうか。かって、わが国で青少年がエフェドリンを含む風邪薬を大量服用してその覚醒作用に溺れる事件が社会現象として蔓延したことがあったが、米国でもその目的で服用して健康被害に遭遇するケースも少なくなかったと思われる。一般に、肥満者は血圧が高いので安易にマオウをダイエットに用いるのは危険である。因みに、わが国ではマオウは食薬区分上ではエフェドリンは”専ら医薬品に用いるもの”なのでエフェドラを広義の食品であるサプリメントとして販売するのは困難である。因みに米国FDAがエフェドラの販売禁止に踏み出したとき、既にサプリメントメーカーは代替品の開発、販売のめどをつけており、メーカー側にはほとんど実害はなかったと伝えられる。そしてエフェドラの代替品となったのはダイダイなど柑橘類の果皮から創製されたサプリメントであり、肥満に悩む米国人の旺盛な食欲を押さえる役割はエフェドリンから同じフェネチルアミン誘導体であるシネフリンにバトンタッチすることになったのである。
専ら合成によりd,l-メチルエフェドリンとして供給されている。特に、催眠作用のある鎮咳薬ジヒドロコデインに配合して使うことが多いが、この場合は中枢興奮による覚醒作用効果を目的とするものである。近年、再びエフェドリンが注目を集めたことがあったが、それは気管支喘息の治療とは全く関係のないものであった。米国では、エフェドラないしマファン(ma
huang;麻黄の漢音)の名の下でマオウをダイエット用サプリメントとして用いるのが流行し、わが国でもインターネット上で通信販売されていた。エフェドリンには食欲減退作用があり、ダイエット効果が期待できるとしてサプリメントとして販売されていたのであるが、特に、それまで用いられてきた食欲減退剤フェンフルラミンが心臓や肺に対して重篤な副作用があるとして販売禁止されてから売上高が急増した。しかしながら、エフェドリンの副作用である血圧上昇作用等による弊害が続出し、米国では100人を超える死者がでたとされるが、米国の監督官庁が消費者に対してエフェドラの服用を控えるよう警告を発したのはごく最近のことである(2003年12月30日、米国医薬品食品局(FDA)はエフェドラあるいはそれを含むサプリメントを販売禁止とする意向をニュースリリース(通達)として発表し、現在では禁止されている)。わが国であれば大薬害禍とされ大騒ぎになっているであろう(2002年中国製ダイエット食品事件、2003年アマメシバによる健康被害事件があった)が、おそらく、米国では肥満による健康障害の方がエフェドラ禍よりもより深刻と考え、エフェドラによるダイエット効果を評価してきたのかも知れない。およそわが国では考えられない米国流合理主義の所産というところであろうか。かって、わが国で青少年がエフェドリンを含む風邪薬を大量服用してその覚醒作用に溺れる事件が社会現象として蔓延したことがあったが、米国でもその目的で服用して健康被害に遭遇するケースも少なくなかったと思われる。一般に、肥満者は血圧が高いので安易にマオウをダイエットに用いるのは危険である。因みに、わが国ではマオウは食薬区分上ではエフェドリンは”専ら医薬品に用いるもの”なのでエフェドラを広義の食品であるサプリメントとして販売するのは困難である。因みに米国FDAがエフェドラの販売禁止に踏み出したとき、既にサプリメントメーカーは代替品の開発、販売のめどをつけており、メーカー側にはほとんど実害はなかったと伝えられる。そしてエフェドラの代替品となったのはダイダイなど柑橘類の果皮から創製されたサプリメントであり、肥満に悩む米国人の旺盛な食欲を押さえる役割はエフェドリンから同じフェネチルアミン誘導体であるシネフリンにバトンタッチすることになったのである。
3.維新政府の「漢方医学」放逐が喘息薬エフェドリンという大魚を逃した
以上エフェドリン誕生の逸話について述べたが、それには二人の日本人が関わっているにもかかわらず医薬としてのエフェドリンは米国で生まれた。これに疑問を抱かない人の方が少ないだろう。何故ならマオウが喘咳に効くと世界の誰よりもはっきりと明言したのは日本人の吉益東洞であり、マオウからエフェドリンそのものを単離したのは同じ日本人の長井長義であったからである。この二つの偉大な知見が結びついておれば、おそらく、天才でなくともエフェドリンが気管支喘息の治療薬として有効であることは気付いたはずなのに何故だろうか。この二人の偉大な日本人の間にはわずか100年足らずの時間差しかなく、エフェドリンという大魚を逃したのは長井の勉強不足に起因するのだろうか。実際、長井はマオウからエフェドリンを世界で初めて単離精製に成功した同じ年に、東京帝国大学医科大学にエフェドリンの薬理作用の検討を依頼しており、決して手をこまねいていた訳ではなかった。しかし、翌年、出された結論はエフェドリンには医薬品として開発するに値する価値はないというものであった。東洞が「薬徴」で記した貴重な知見は当時の医学者や長井の目には届いてはいなかったのである。これを説明するには、この二人の間に日本史上、最大の歴史的変革があったことを忘れてはなるまい。それは明治維新であり、新政府は東洋の超大国中国が欧州列強により半植民地化された状態を見聞しており、その二の舞を避けるべく先進の科学技術を導入し欧米列強に追いつき追い越せの国是で猪突猛進していたのである。したがって、学問の世界では欧州の科学を導入し、中国からもたらされた在来の学問を時代遅れとして一斉に切り捨てたのである。それは医学の分野でもっとも顕著であった。江戸時代は医学といえば漢方医学が”オフィシャルな医学”であったが、維新政府は既にわが国に蘭医学として一部導入されていた西洋医学を正規の医学とし、漢方医学の実践を禁止した。このとき、焚書坑儒の名のもとで、多くの漢方医学書も処分されたと思われる。こういう状況では、長井は東洞の著作「薬徴」にふれる機会は少ないというよりむしろ、当時の医学者や薬学者にとって江戸期の漢方医学書の記述は学術的検討の対象とすらならなかったのであろう。東洞は漢方生薬でも附子(トリカブトの根を基原とする)、麻黄など作用の激しいものを好んで用いたが、当時の漢方医の多くは麻黄は恐れてあまり用いなかったようである。それは東洞の次の記述でうかがい知ることができる。「甚だし。世医の麻黄を恐るるや。---学者、以って耳食して飽くことなかれ。」耳食とは人から伝え聞いただけで信用することをいい、まず自分で試してみよといっているのである。東洞は「薬徴」で53種の生薬について記載しているが、古文献に従うだけでなく、自らの経験に基づいて独自の見解も交えてこの書を記した。こういう革新的な伝統医学の大家の見解が後世の医家や科学者の耳に届かなかったのは実に残念というしかない。当時、江戸時代の漢方を継承する医師も少なからずいたと思われるが、彼らも長井の近代科学の成果(マオウからエフェドリンの単離)を素直に受け入れる柔軟性を欠いた単なる守旧派にすぎなかったようである。したがって、エフェドリンという大魚を逃した元凶は、明治維新前後の当時の守旧、革新両学徒の激しい確執に由来する相互否定という視野の狭い硬直した思考にあったといえるだろう。
今日では、世界の趨勢は伝統医学や民間療法に蓄積された薬物情報もかってのように”魔女のたわごと”として一笑することはなくなった。これは20世紀になって民族植物学的研究によりこれらが新薬開発の”宝の山”である可能性の大きさを明らかにしたからである。
↑ページトップへ戻る