1.ダイオウ(大黄)は漢方でもっとも重要な薬の一つである
ダイオウ(大黄)は別名を「将軍」とも称され、漢方医学においてはもっとも重要な生薬の一つとされている。江戸時代の代表的な実証主義的漢方医である吉益東洞は著書「薬徴」の中でダイオウの薬効について「主通利結毒也。故能治胸満、腹満、腹痛及便閉、小便不利。旁治発黄、瘀血、腫膿。」と記述している。簡単にいえば、「停滞している病毒を排出することにより、胸腹の膨満感、腹痛、便秘、小便の出の悪いのを治す。また、黄疸、血液の停滞による症状、できものも治す。」ということであるが、ダイオウは病気の基となる諸毒を排する作用がある漢方の要薬として認識されていた。通常、漢方薬といえば副作用がないと認識されがちだが、古代中国の本草書「神農本草経」ではダイオウを「治病を主とし、地に応じ、多毒、長期にわたって服用してはならない」薬である”下薬”に分類している。漢方でも抵抗力が低下し、生理機能が衰えた虚証体質の患者には禁忌とされている(→虚実証の診断に関しては漢方医学概説を参照)。現在では漢方処方に限らずダイオウ末、あるいは複方ダイオウ・センナ散などのように配合剤として広く瀉下薬として用いられるが、副作用として腹痛、腹鳴、悪心・嘔吐などが知られている。そのほか、子宮収縮作用や骨盤内臓器の充血作用があるため、妊婦は服用を控えるのが好ましいとされている。授乳婦の場合では母乳中にダイオウの成分(アントラキノンなど)が移行し、そのため乳児が下痢を起こすことがあるので授乳婦もダイオウの服用を控えるべきとされている。ダイオウは英語名をrhuburbと称し古くから欧州でも有用な瀉下薬として使用されており、その使用は原産地中国やその近傍の東アジアに限らず汎世界的である。
2.ダイオウ(大黄)の瀉下作用は優れたDDSによるものである
ダイオウの基原は日本薬局方では「タデ科Rheum palmatum、R. tangusticum、R. officinale、R. coreanumまたはそれらの種間雑種の根茎」(ママ)とされている。ダイオウは薬用に適さない種(ショクヨウダイオウR. rhaponticumやカラダイオウR. rhabarbarumなどのハーブ系ダイオウ)が混じることがしばしばあり品質管理上の問題点であったが、近年、R. palmatumとR. coreanumの種間雑種(信州大黄)がわが国で創出され、生薬市場で錦紋大黄と称される良品に匹敵あるいはそれ以上の品質であることがわかり、北海道などで栽培、供給されるようになった。ダイオウの薬効成分はセンノシドA(Sennoside A)などのジアンスロン誘導体であるが、真の薬効成分ではない。経口投与でセンノシドは胃、小腸では吸収されずに大腸まで移行し、そこで腸内細菌(ビフィズス菌やペプトストレプトコッカス菌など)による代謝をうけて生成したレインアンスロン(Rheinanthrone)が大腸壁を
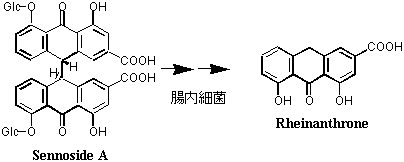
刺激して蠕動運動を活発にして瀉下効果をもたらすとされている(図)。このため抗生物質や正露丸のような腸内細菌を減少させるような薬物を投与した場合、ダイオウの瀉下効果は必然的に減弱するので、”薬の飲み合わせ”に十分注意する必要がある。レインアンスロンがダイオウの真の薬効成分であり、センノシドはその前駆体であるプロドラッグということになるが、今のところレインアンスロンを直接瀉下薬として用いることはなさそうである。一つには適当量のレインアンスロンを大腸まで輸送しなければならないというドラッグデリバリー(drug delivery;薬物輸送)上の問題がある。レインアンスロンには激しい嘔吐を起こすという副作用があるので、大腸壁に適度な刺激を与える程度の用量を継続的に輸送するというのは容易ではない。この点、生薬製剤として投与した場合、有効成分センノシドは配糖体(糖が結合したもの)であるから、消化管に吸収されずに大腸まで輸送され、そこで徐々に代謝されて瀉下効果を起こすので、よほどの大用量を投与しない限り副作用が顕在化することは少ない。すなわち、ダイオウはほぼ理想的な薬物輸送系(DDS; drug delivery system)をもっているといえる。もう一つは薬効成分の製造コストであり、このため現在でも精製センノシド製剤(プルゼニド錠剤など)を使うに留まり、依然として生薬製剤が主流である。プルゼニドなどのセンノシド製剤は重篤な便秘に対して用いられるべきであり、通常の瀉下薬としては安価な生薬製剤で十分である。ダイオウは他にラタンニン(Rhatannin)と称されるタンニンが含まれている。ダイオウ末に渋味があるのはこのためである。したがって、大量投与の場合、副成分タンニンの収斂作用により止瀉作用、便秘作用が現れることがある。このため、重篤な便秘、たとえば末期ガン患者が除痛のためモルヒネの大量投与をうけて起きる便秘などにはダイオウを用いるのは避けるべきである。この場合は同じ有効成分を含む生薬センナあるいはセンノシド製剤(プルゼニド錠剤など)が適している。
- 薬徴
- 安芸の国出身の古方派漢方医吉益東洞(よしますとうどう;1702年-1773年)の著したもの。発行は天明4(1784)年で東洞の没後であるが
 、没する少し前(1771年)に著したと伝えられ、薬効の確かな53種の生薬について薬効、選品などについて論じている。東洞の漢方医としての生涯の経験、知見が記載されたものとして高く評価されるべきものである。東洞は万病一毒の説を立て、空理空論を避け実証に基づいて一切の治術を行うべしと説いた。この精神は現在のEBM(evidence-based
medicine;医学的証拠に基づいて治療を行うこと)に合い通じるところがあり、当時としては革新的なものであった。この精神は江戸時代に門下生に脈々と伝えられた。また、東洞は発汗、催吐、瀉下の峻剤(作用の激しい薬)を積極的に使用したことでも知られている。特に、マオウ(麻黄)が喘息様呼吸器疾患に効能があることを予見していたことは高く評価される(→詳細は抗喘息薬エフェドリンの製造原料マオウ(麻黄)を参照)。薬徴の原本は現存しないが、門下生による写本が今日に伝えられている。
、没する少し前(1771年)に著したと伝えられ、薬効の確かな53種の生薬について薬効、選品などについて論じている。東洞の漢方医としての生涯の経験、知見が記載されたものとして高く評価されるべきものである。東洞は万病一毒の説を立て、空理空論を避け実証に基づいて一切の治術を行うべしと説いた。この精神は現在のEBM(evidence-based
medicine;医学的証拠に基づいて治療を行うこと)に合い通じるところがあり、当時としては革新的なものであった。この精神は江戸時代に門下生に脈々と伝えられた。また、東洞は発汗、催吐、瀉下の峻剤(作用の激しい薬)を積極的に使用したことでも知られている。特に、マオウ(麻黄)が喘息様呼吸器疾患に効能があることを予見していたことは高く評価される(→詳細は抗喘息薬エフェドリンの製造原料マオウ(麻黄)を参照)。薬徴の原本は現存しないが、門下生による写本が今日に伝えられている。
- 神農本草経
- 中国最古の本草書(現在でいう薬局方のような存在で生薬の基原とその薬効を記載したもの)で原本、原文は伝えられていないが、わが国に11巻が残存する「新修本草」や宋代の「證類本草」の写本にその内容が引用記載されている。365種の医薬品を収載し、上薬、中薬、下薬の三つに分類している。上薬120種は「君であり、生命を養うを主とする。天に応じ、多量に長期にわたって服用しても人を害わない。軽身益気、不老延年を欲するものは上経を本とする」ものとし、桂皮(ケイヒ)、遠志(オンジ;ヒメハギ科イトヒメハギの根)、甘草(カンゾウ)、人参(ニンジン;ウコギ科オタネニンジンの根)、柴胡(サイコ;セリ科ミシマサイコの根)、黄連(オウレン;キンポウゲ科オウレンの根)、牛黄(ゴオウ)などを挙げている。中薬120種は「臣であり、性を養うを主とする。人に応じ、無毒と有毒がありその宜しきものを斟酌する。病を遏(と)め虚羸(きょるい;疲れや痩せること)を補うことを欲するものは中経を本とする」ものとし、当帰(トウキ;セリ科トウキの根)、桔梗(キキョウ;キキョウ科キキョウの根)、牡丹皮(ボタンピ;ボタン科ボタンの根皮)、防風(ボウフウ;セリ科ボウフウの根)、麻黄(マオウ:マオウ科マオウの地上茎)、葛根(カッコン;マメ科クズの根)などを挙げている。下薬125種は「佐使であり、治病を主とし、地に応じ、多毒、長期にわたって服用してはならない。寒熱邪気を除き積聚を癒そうと欲するものは下経を本とする」ものとし、大黄(ダイオウ)、附子(ブシ;キンポウゲ科トリカブトの根)、半夏(ハンゲ;サトイモ科カラスビシャクの根)、杏仁(キョウニン;バラ科アンズの種子)などを挙げている。現在でも漢方薬として使われているものが多く収載されていることから、実用経験に基づいて選抜された当時としては世界的水準の薬物書といってよい。後漢時代に書かれたものと推察されているが、著者は明らかでない。