1.アルカロイドの分類について
植物の中には分子内に窒素を含み塩基性を示す化合物を含むものがある。これらは古くからアルカロイド(alkaloid)と総称されているが、”アルカリのようなもの”という意味からわかるように語源的にはアルカリ(alkali)と同じである。和訳として「植物塩基」が用いられた時期もあったが、今日では動物起源のアルカロイドも知られていること、また以下に述べるように、一般にはアルカロイドと認識されていても塩基性でないものも実際に存在するので、この訳語を用いるのは適当ではない。これまでに単離されたアルカロイドの化学構造は極めて多様であるので、様々な分類法が提唱されている。最近、よく用いられるようになったのは生合成的起源による分類法であり、またこれが新しいアルカロイドの定義ともなっている。まず次の3つのタイプに大別されている(定義:最新の知見に基づいて2012年4月に修正)。
- 基本骨格、窒素源ともにアミノ酸に由来し、生合成過程でアミノ酸は脱炭酸を伴う
- 基本骨格がアミノ酸に由来せず、窒素源はアンモニア性窒素ないしアミンである
- 基本骨格、窒素源ともにアミノ酸に由来するが、脱炭酸を伴わないで生成する
1に属するものを真正アルカロイド(true alkaloid)、2に属するものをプソイドアルカロイド(pseudoalkaloid)、3に属するものを不完全アルカロイド(protoalkaloid)と称し、真正アルカロイドについてはさらに前駆体となるアミノ酸の種類によって、例えばトリプトファン由来アルカロイドなどのように分類される(→詳しくはアミノ酸経路を参照)。プソイドアルカロイドとしては、ジャガイモの芽に含まれるソラニン(Solanine)などに代表されるステロイドアルカロイド(steroid alkaloid)、 アコナン系ジテルペンを母核しトリカブト毒素として名高いアコニチン(Aconitine)*やコウホネアルカロイドなどテルペンアルカロイド(terpenoid alkaloid)、 セリ科ドクニンジンの有毒成分コニイン(Coniine)などポリケチドアミン(polyketide amine)などがある。不完全アルカロイドとは、具体的には特殊な芳香族アミノ酸であるアントラニル酸、ニコチン酸を前駆体とするアルカロイドであるが、これらは生合成経路の上で脱炭酸を伴わない点で通常のアミノ酸を前駆体とするアルカロイドと区別される。ミカン科植物にはアントラニル酸を前駆体とするアルカロイド(例 ゴシュユアルカロイド)が特に多いことで知られる。不完全という名前を冠しているので生合成反応が未完成という意味で名付けられたようであるが、ゴシュユアルカロイドについてはトリプタミンとアントラニル酸のアミド縮合体にC1単位が導入されただけなので”不完全”というのは理解できるが、アントラニル酸、ニコチン酸由来のアルカロイドの中には複雑な生合成過程を経るものも多くあるので誤解しやすい。アントラニル酸、ニコチン酸はアミノ酸に似て非なるものとして”いわゆるアミノ酸”に含めないこともある(特に生化学領域では)ので、そのような定義に立てば不完全アルカロイドは「窒素源をアンモニアないしアミン、アミノ酸に由来しないアルカロイド」ということになろう。
*日本薬学会第132年会(札幌、2012年)において、折原らはアコニチンのエチルアミン部がアミノ酸のセリンに由来することを13C-標識物を用いた実験で明らかにした。また、セリンが脱炭酸されたヒドロキシエチルアミンもアコニチンのエチルアミン部に効率よく導入されることも確認している。一方、バリンについては検討していないが、その脱炭酸体であるエチルアミンはほとんど導入されないことから、エチルアミン部の前駆体ではないと結論づけている。この結果からアコニチンはアミノ酸であるセリンから生合成されることになり、真正アルカロイドの一種とみることも可能となるが、基本骨格のアコナンの構築には関与していないので、やはりプソイドアルカロイドとみるべきであろう。ただし、薬剤師国家試験など各種試験においてはアコニチンの生合成が「アミノ酸由来か否か」という設問は大いに問題があることに留意すべきであろう。(2012年4月1日追記)
植物化学でいうアルカロイドはこれらのいずれかに属するものであるが、その定義の境界線はかなりあいまい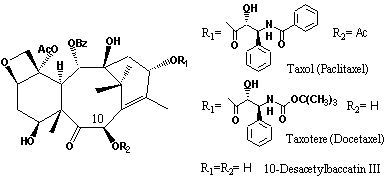 である。例えば、抗癌薬パクリタキセル(Paclitaxel)は臨床薬理学ではビンクリスチン(Vincristine)やカンプトテシン(Camptothecine)などとともにしばしば植物アルカロイドと呼称されている。確かに窒素原子を含むのであるが、基本骨格のタキサン上ではなくエステル結合した複合置換基の中に含まれている。この含窒素部だけを取り上げれば非アミノ酸由来のプソイドアルカロイド(あるいは不完全アルカロイド)であること、そして抗癌活性を示す上で重要な部分構造であることがパクリタキセルをアルカロイドと称する理由であろう。因みに基本母核を命名の基準とする傾向の強い植物化学領域ではパクリタキセルをアルカロイドとは見なすことはほとんどない。また、トウガラシの辛味成分であるカプサイシン(Capsaicine)とその類縁体がアルカロイドとして実際に学会で発表されたこともある(日本生薬学会第50回年会、東京、2003年)。カプサイシンも窒素原子を含むが、バニリルアミン(簡単な構造のプソイドアルカロイドと考えられる)と脂肪酸部のどちらが基本母核かきわめて微妙である。タキソール、カプサイシンのいずれも窒素原子はアミド基であって中性なのでアルカロイドではないとする意見もあるが、真正アルカロイドであっても塩基性でないものもある。例えば、イヌサフラン科イヌサフランに含まれ、抗通風薬として用いられるコルヒチン(Colchicine)の前駆体であるチロシンに由来するアミノ基がたまたまアセチル化されアミドとなっているにすぎず、アミド化されていない類縁成分も知られているので純然たる真正アルカロイドといえる。ミカン科Pilocarpus jaborandiに含まれ、副交感神経興奮薬と
である。例えば、抗癌薬パクリタキセル(Paclitaxel)は臨床薬理学ではビンクリスチン(Vincristine)やカンプトテシン(Camptothecine)などとともにしばしば植物アルカロイドと呼称されている。確かに窒素原子を含むのであるが、基本骨格のタキサン上ではなくエステル結合した複合置換基の中に含まれている。この含窒素部だけを取り上げれば非アミノ酸由来のプソイドアルカロイド(あるいは不完全アルカロイド)であること、そして抗癌活性を示す上で重要な部分構造であることがパクリタキセルをアルカロイドと称する理由であろう。因みに基本母核を命名の基準とする傾向の強い植物化学領域ではパクリタキセルをアルカロイドとは見なすことはほとんどない。また、トウガラシの辛味成分であるカプサイシン(Capsaicine)とその類縁体がアルカロイドとして実際に学会で発表されたこともある(日本生薬学会第50回年会、東京、2003年)。カプサイシンも窒素原子を含むが、バニリルアミン(簡単な構造のプソイドアルカロイドと考えられる)と脂肪酸部のどちらが基本母核かきわめて微妙である。タキソール、カプサイシンのいずれも窒素原子はアミド基であって中性なのでアルカロイドではないとする意見もあるが、真正アルカロイドであっても塩基性でないものもある。例えば、イヌサフラン科イヌサフランに含まれ、抗通風薬として用いられるコルヒチン(Colchicine)の前駆体であるチロシンに由来するアミノ基がたまたまアセチル化されアミドとなっているにすぎず、アミド化されていない類縁成分も知られているので純然たる真正アルカロイドといえる。ミカン科Pilocarpus jaborandiに含まれ、副交感神経興奮薬と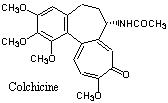 して用いられるピロカルピン(Pilocarpine)はヒスチジン由来と考えられている。通例、アミノ酸由来のアルカロイドにはアミノ基が窒素源となるのであるが、ピロカルピンは生合成過程でアミノ基由来の窒素原子が失われ、イミダゾール環以外に窒素原子はない。しかしながら、イミダゾール環に由来する塩基
して用いられるピロカルピン(Pilocarpine)はヒスチジン由来と考えられている。通例、アミノ酸由来のアルカロイドにはアミノ基が窒素源となるのであるが、ピロカルピンは生合成過程でアミノ基由来の窒素原子が失われ、イミダゾール環以外に窒素原子はない。しかしながら、イミダゾール環に由来する塩基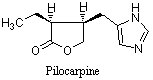 性によってアルカロイドと称するのが慣例となっている。一方、ミカン科ゲッキツ属ナンヨウザンショウ(オオバゲッキツ)節植物に含まれるカルバゾール誘導体、同ゲッキツ節植物に含まれるプレニルインドールも生合成的にはトリプトファン由来でありながらそのアミノ基が生合成過程で失われており、残存する窒素原子はピロカルピンと同様に前駆体の非アミノ基(インドール骨格)に由来する(→以上、高等植物の化学系統分類学を参照)。ピロカルピンと異なり、インドール、カルバゾールには塩基性はないのであるが、これらも慣例によってアルカロイドと称されてきた。以上、例外的な存在のアルカロイドを取り上げたが、ウマノスズクサ属植物に含
性によってアルカロイドと称するのが慣例となっている。一方、ミカン科ゲッキツ属ナンヨウザンショウ(オオバゲッキツ)節植物に含まれるカルバゾール誘導体、同ゲッキツ節植物に含まれるプレニルインドールも生合成的にはトリプトファン由来でありながらそのアミノ基が生合成過程で失われており、残存する窒素原子はピロカルピンと同様に前駆体の非アミノ基(インドール骨格)に由来する(→以上、高等植物の化学系統分類学を参照)。ピロカルピンと異なり、インドール、カルバゾールには塩基性はないのであるが、これらも慣例によってアルカロイドと称されてきた。以上、例外的な存在のアルカロイドを取り上げたが、ウマノスズクサ属植物に含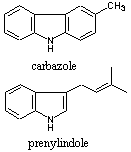 まれる腎毒性成分であるアリストロキア酸(Aristolochic acid) を除外するわけにはいくまい。何故ならこの物質はアルカロイド起源なのに酸性物質という極めてユニークな存在だからである。窒素はニトロ基として分子内に存在し、これまでに多くの類縁物質が知られ、中には窒素のないものすらある。基本骨格の構造だけを見ればフェナントレン誘導体であり、しかもカルボン酸基を含むので純然たる酸性物質だから、アルカロイドという名前にそぐわないように思える。天然物質としてはほとんど例のないニトロ基をもつので、あたかも人工合成によって創製されたもののようである。しかし、生合成的観点ではこの物質は紛れもなくベンジルイソキノリンアルカロイ
まれる腎毒性成分であるアリストロキア酸(Aristolochic acid) を除外するわけにはいくまい。何故ならこの物質はアルカロイド起源なのに酸性物質という極めてユニークな存在だからである。窒素はニトロ基として分子内に存在し、これまでに多くの類縁物質が知られ、中には窒素のないものすらある。基本骨格の構造だけを見ればフェナントレン誘導体であり、しかもカルボン酸基を含むので純然たる酸性物質だから、アルカロイドという名前にそぐわないように思える。天然物質としてはほとんど例のないニトロ基をもつので、あたかも人工合成によって創製されたもののようである。しかし、生合成的観点ではこの物質は紛れもなくベンジルイソキノリンアルカロイ.gif) ドに分類されるもので、アポルフィン型アルカロイドの変形にすぎない(→詳細はフェニルアラニン、チロシン由来のアルカロイドを参照)。アリストロキア酸の構造で特筆すべき存在であるニトロ基およびカルボン酸基もイソキノリン(isoquinoline)環の酸化的開裂によって生成したものであり、本物質がアルカロイドに見えないのは基本骨格のイソキノリン環が失われているためである。何事も例外はつきものであるが、窒素原子を含む二次代謝産物をアルカロイドと呼ぶかどうかは上述の定義の厳格な運用によってではなく、是々非々で慣例的に処理されてきたことに留意する必要があろう。
ドに分類されるもので、アポルフィン型アルカロイドの変形にすぎない(→詳細はフェニルアラニン、チロシン由来のアルカロイドを参照)。アリストロキア酸の構造で特筆すべき存在であるニトロ基およびカルボン酸基もイソキノリン(isoquinoline)環の酸化的開裂によって生成したものであり、本物質がアルカロイドに見えないのは基本骨格のイソキノリン環が失われているためである。何事も例外はつきものであるが、窒素原子を含む二次代謝産物をアルカロイドと呼ぶかどうかは上述の定義の厳格な運用によってではなく、是々非々で慣例的に処理されてきたことに留意する必要があろう。
以上述べた定義ではアルカロイドの構造的多様性及び自然界における分布の偏在は全く見えてこないので、次のような伝統的な分類法も根強く併用されている。
- A.植物系統の名を冠して呼称する
- B.基本骨格の名を冠して呼称する
Aの方式によるものとしてアヘン(ケシ)アルコロイド、トリカブトアルカロイド、トコンアルカロイド、ヒガンバナ科アルカロイド、ニチニチソウアルカロイド、ラウオルフィアアルカロイド、キナアルカロイド、エリスリナアルカロイド、ユズリハアルカロイドなどの例がある。これはアルカロイドがある種(または分類群)の植物に偏在し、またそれぞれにおいて特異な構造をもつことが多いので、この呼び名は今日でも広く使われる。B方式では各アルカロイドの窒素を含む特徴的な複素環部の分類を基盤にしたもので、植物化学的見地からではなく有機化学的見地から命名されたものである。通例、高等植物由来のアルカロイドでは次のような骨格が分類項目として採用されることが多い。この方式では前述のプレニルインドール、カルバゾールなどをアルカロイドと称しても違和感はない。以上の分類方式のうち、生合成的起源に基づくものだけが全てのアルカロイドを対象として分類を試みるものであり、そのほかはどちらかといえば便宜的なものに過ぎないといえよう。
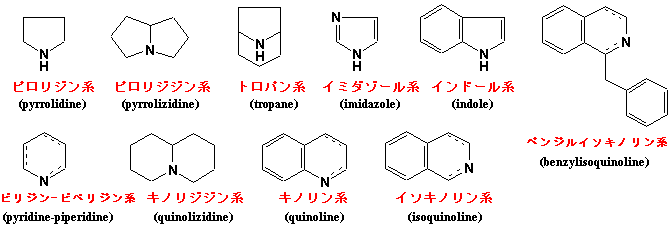
2.天然界におけるアルカロイドの分布と存在意義について
現在まで知られているアルカロイドの大部分は高等植物の顕花植物、特に被子植物門双子葉綱(→植物の分類と名前を参照)に集中し、その他では小葉植物門(シダ類の一部が属する)ヒカゲノカズラ綱のヒカゲノカズラ科や、下等植物では麦角菌(麦角アルカロイドを産する)など1、2の科に限られている。アルカロイドの分布は他の二次代謝産物と比べて偏在しており、例えば、医薬原料としての価値が高いとされるモノテルペンインドールアルカロイドは生合成的にはトリプトファンとセコイリドイドの複合経路で生成する(→トリプトファン由来のアルカロイドを参照)が、マチン科(Loganiaceae)、キョウチクトウ科(Apocynaceae)、アカネ科(Rubiaceae)の3科にほぼ限られている。しかし、この3科に属する全ての植物種に含まれているわけではなく、アルカロイドを含むものと含まないものがある。一方、ケシ科に属する植物は全てベンジルイソキノリン及びそれに派生する類縁のアルカロイド(→フェニルアラニン、チロシン由来のアルカロイドを参照)を含む。一般に、一つの植物種(群)に含まれるアルカロイドは生合成的起源による分類の1系統だけを含み、複数の系統のアルカロイドが共存する例はごく少ないので、アルカロイドの分布を指標として分類を行うことも可能である(→高等植物の化学系統分類学を参照)。
アルカロイドは植物組織の中で細胞活性の強い葉根、根皮、種子に局在し、死細胞より生細胞に多く存在する。また、合成と蓄積の場は必ずしも一致しないようであり、含量は時間的変動が激しく、細胞内の液胞内に蓄積する。これらのことからアルカロイドは窒素の老廃物、あるいは何らかの解毒作用の結果であるという説もある。 しかし、この視点における研究は現在ではほとんど行われていない。
3.アルカロイドは重要な医薬原料である
アルカロイドは総じて強い生物活性を有し医薬品として利用されるものが多い(→植物起源医薬品を参照)。また、今後の医薬品の創製においても、アルカロイドはもっとも期待できる先導化合物のソースとして重要な存在である。一方、激しい生理作用や生物活性の故、有毒物質として存在するものも多い。中にはトリカブトアルカロイドのように致死性成分も多く、生薬でアルカロイドを多く含むものは使用に細心の注意が必要である。近年、高等植物起源の素材をサプリメント、機能食品などとして病気予防、健康の増進に用いる傾向が世界的に進行している。サプリメント、機能食品のいずれも食品の範疇に含められるので、含有される二次代謝産物によって食薬区分を決定する(→食薬区分についてを参照)。アルカロイドなどのような生物活性の強い成分を含む場合、医薬品と判定されることが多い。また、単にアルカロイドを含むというだけで認可されないということもあるという。真正、プソイドアルカロイドのような典型的なアルカロイドを含む場合はとりわけ慎重に検討すべきなのはいうまでもない。しかし、前述したように、近年、カプサイシンのようなものまでアルカロイドに含めると以上のような天然素材のサプリメントとしての利用が大きく制限されることになる。アルカロイドの定義を植物化学の観点から見直す必要があろう。
→ページのトップへ戻る