味など人間の感覚に作用する成分群を官能成分と呼ぶ。においをもつ成分、例えば精油もこのカテゴリーに入るのだが、視覚に作用する成分(色素)とともに別項目として記載した(→精油、色素)。ここでは味覚成分について概説する。
1.甘味成分(natural sweetner)
(→天然甘味成分の構造式、甘味物質を含む植物)甘味のある成分として代表的なものはショ糖などの糖質であるが、中には非糖質で甘味を有する物質もある。アジサイ科アマチャに含まれるフィロズルチン(Phyllodulcin)が代表的なものであり、これはイソクマリン骨格を有するフェノール性成分である。甘味の質は糖類とはかなり違い、やや癖のある甘味である。アマチャは伝統的な生薬製剤(丸薬など)の矯味料として用いられ、今日でも釈迦の命日には各地の寺院で甘茶として供される。新鮮アマチャ葉中のフィロズルチンの含量は低く、多くは配糖体の形で存在する。この配糖体は苦いので新鮮アマチャ葉に甘味はなくやや苦い程である。そのためアマチャ葉を調製するとき、β-グルコシダーゼによる発酵でフィロズルチンの生成を促すためゆっくり乾燥(ときに湿気を与えることさえある)させる。二次代謝産物の配糖体で甘味を呈するものがある。糖が結合しているので完全な非糖質ではないが、ショ糖の100倍以上の強い甘味をもち、また味も糖質に近いので配糖体系甘味成分は天然甘味料としてダイエットを志向した食品に用いられる。南米パラグアイ原産のキク科植物ステビアの葉に含まれるジテルペン配糖体ステビオサイド(Stevioside)はその代表的なものであり、お菓子などの甘味料として用途が拡大している。そのほか、中国原産のウリ科植物Siraitia grosvenoriiの果実(羅漢果)に含まれるモグロシドVや、生薬カンゾウ(マメ科ヨーロッパカンゾウGlycyrrhiza glabraなど)に含まれるグリチルリチン(Glycyrrhizin;日本薬局方ではグリチルリチン酸と称する)は、サポニンの一種である。生薬カンゾウはわが国で用いられる一般用漢方製剤のうち約7割の処方に含まれ、薬効以外に矯味料としての役割もあると思われる。配糖体の大半は、糖が結合しているにも関わらず、苦味を呈し、甘味のあるものはごく例外的である。甘味をもつ二次代謝成分の中で、通称ニッキの甘味成分はl-エピカテキンが3個縮合したシンナムタンニンと称する縮合型タンニンの1種である。一般にタンニンは渋味、えぐみの本体として知られているので、甘味をもつシンナムタンニン(こちらを参照)の存在は極めてユニークといえる。ニッキはニッケイの根皮を基原とし、ニッキ飴やニッキ水など伝統的な菓子の甘味料として用いられてきた。ニッケイは本邦では江戸時代から栽培されているが、中国原産のCinnamomum sieboldiiがその植物学的起源として長い間当てられてきた。しかし、『琉球植物誌』の編者である鹿児島大学初島住彦博士によれば、ニッケイは沖縄本島、徳之島、久米島に産するものであるといい、ニッケイの学名をC. okinawenseとしている。これによれば、琉球王国を支配していた薩摩藩によってニッケイが本土へはもたらされた可能性もあり得る。一部の植物学者に支持されたが、最近の分類学ではこの学名は認められておらず、沖縄産のCinnamomum属の詳細はなお検討の余地があるようだ。同属種のヤブニッケイの根にもシンナムタンニンが含まれ、ニッケイの代用とされることがある。
2.苦味成分(bitter substance)
(→苦味成分の構造式、強い苦味物質を含む植物)
「良薬は口に苦し」と諺にあるが、実際、ほとんどの生薬エキスには苦味がある。このことは苦味成分は特殊な存在ではないことを示唆する。配糖体はオリゴ糖が結合した二次代謝産産物であるが、ほとんどは苦く、前述の甘味配糖体はごく例外的な存在である。配糖体の中でもとりわけ苦味の強いグループがあり、これを苦味配糖体と称する。わが国古来の民間薬であるリンドウ科センブリ(全草を生薬センブリとする)はスウェルチアマリン(Swertiamarin)、同リンドウ、ゲンチアナ(それぞれの根を生薬リュウタン、ゲンチアナとする)にはゲンチオピクロシド(Gentiopicroside)というセコイリドイド配糖体が含まれ、これが苦味の本体であり、いずれも苦味健胃薬として用いる。これらの生薬はいずれもリンドウ科植物を基原としており、セコイリドイドは広くリンドウ科植物に含まれる成分群である。
その他の苦味成分としてはアルカロイドや変形トリテルペノイドが挙げられる。アルカロイドは一般に苦味があるのだが、中には強い苦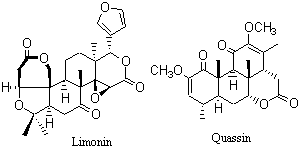 味を呈するものがある。マメ科クララの根は生薬クジン(苦参)として苦味健胃薬として用いられるが、苦味の本体はマトリン(Matrine)なるキノリチジン系アルカロイドである。ミカン科キハダやキンポウゲ科オウレンに含まれるアルカロイドであるベルベリン(Berberine)も強い苦味を示すことで知られる。ニガキ科ニガキの心材は生薬ニガキ(苦木)として苦味健胃薬とするが、クァシン(Quassin)ほかクァシノイドと総称される高度に酸化された特異な変形トリテルペン誘導体が苦味の本体である。類似の変形トリテルペンとしてはミカン科柑橘属(ダイダイなど)の皮に多く含まれるリモニン(Limonin)、センダン科センダンの樹皮や果実に含まれるトウセンダニンがある。リモニンには強い昆虫接触阻害があり、資源的に豊富なミカン類から得られるリモニンを農薬として応用することが試みられたこともある。
味を呈するものがある。マメ科クララの根は生薬クジン(苦参)として苦味健胃薬として用いられるが、苦味の本体はマトリン(Matrine)なるキノリチジン系アルカロイドである。ミカン科キハダやキンポウゲ科オウレンに含まれるアルカロイドであるベルベリン(Berberine)も強い苦味を示すことで知られる。ニガキ科ニガキの心材は生薬ニガキ(苦木)として苦味健胃薬とするが、クァシン(Quassin)ほかクァシノイドと総称される高度に酸化された特異な変形トリテルペン誘導体が苦味の本体である。類似の変形トリテルペンとしてはミカン科柑橘属(ダイダイなど)の皮に多く含まれるリモニン(Limonin)、センダン科センダンの樹皮や果実に含まれるトウセンダニンがある。リモニンには強い昆虫接触阻害があり、資源的に豊富なミカン類から得られるリモニンを農薬として応用することが試みられたこともある。
3.辛味成分(pungent substance)
(→辛味成分の構造式、辛味物質を含む植物)
一般に料理で用いる香辛料(スパイス)は辛味をもつ。その代表的なものがトウガラシであるが、辛味の本体はカプサイシン(Capsaicin)などアミド誘導体である。カプサイシンは極めて強い辛味を有するが、薬理作用の観点からも興味深い成分である。すなわち、アドレナリンの分泌を促進して代謝亢進作用、食事性体熱生産作用、発汗作用などを示し、他に強い抗菌、駆虫作用、防腐作用が報告されている。トウガラシを香辛料の東の横綱とすれば、西の横綱としてコショウをあげるのに異論はないだろう。コショウの辛味の本体はピペリン(Piperine)であり、抗菌作用や防腐作用などが知られている。因みにカレー粉の辛味は同属種のインド産ヒハツであり、また沖縄県で広く香辛料に用いられるヒハツモドキも同じ辛味成分ピペリンを含む。本邦で葉を香辛料とするサンショウの辛味成分α-サンショオール(α-Sanshool)もアミド誘導体であり、局所麻酔作用や殺虫作用、魚毒作用などが知られている。その他、通称ハトウガラシと称するキク科オランダセンニチにはα-サンショオールに酷似するアミド誘導体スピラントール(Spilanthol)が存在する。
薬用、食用に繁用するショウガの辛味成分は6-ジンゲロール(6-Gingerol)なるフェノール性成分であるが、官能基としてのアミドはないが、芳香環に長いアルキル基が結合し、カプサイシンと分子全体の構造は似ている。しかしながら、「蓼食う虫も好き好き」の諺にあるタデ、すなわちタデ科ヤナギタデに含まれる辛味成分は以上述べた辛味成分とは構造的に全く関連のないセスキテルペン誘導体(タデオナール)である。本物質はアルデヒド基を2個もつ特異なセスキテルペンで、構造の酷似する物質には昆虫の摂食阻害作用が知られており、諺の意味を考えると興味深い。
4.その他の味を示す成分について
甘味、苦味、辛味以外の味として、渋味、旨味があげられる。このうち、渋味については天然物質ではタンニンなどに代表されるいわゆるポリフェノールが渋味をもつことで知られる。柿やお茶の渋味がポリフェノールであることはよく知られている。一方、旨味をもつ二次代謝産物については報告がない。